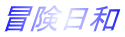
| 日陰に咲く花 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の終わりを告げる鐘が鳴った。 ガルグ=マク大修道院の中に併設されたこの士官学校には、 担任教師への質問をする時間というのが設けられている。 そんなの質問をしたい人がすればいいのに、学校側は生徒に「質問する日」の順番を割り当てた。 生徒と教師の円滑なコミュニケーションを図るべく公平に――だそうだが、まったく余計なことを。 異例の抜擢で黒鷲学級を受け持つことになった新任教師は、 一番最初の授業の後で、こう言った。 「みんなのことが知りたいから、少しでも話をさせて。質問が無ければ、何か雑談をしても構わない」 対人恐怖症で万年引き籠もりのベルナデッタにとって、これはなかなかの難題である。 たったいま先生への質問を何とか終えたベルナデッタは、教科書と筆記用具を抱えると 一目散に教室を出て、寮の自室を目指すのだった。 今日の用事は終了した。 グループ課題は先週終えたばかり、掃除や炊事の当番でもない…ということは、 つまり久方ぶりの自由な放課後。 これまで身の丈に合わぬ頑張りを見せて堪え忍び…ついに今、念願の 引き籠もりライフを取り戻したのである! 彼女は知らず知らずのうちに、うきうきとスキップしていた。 「待ちに待った我が世の春よ、こんにちは! ああ、今日は何をしよう?」 すれ違ったクラスメイトが怪訝そうな顔をした。寒そうに肩をすくめて、ベルナデッタを一瞥する。 今は星辰せいしんの節、フォドラは本格的な冬に突入したばかりだ。 山の上に建つ、ここ――ガルグ=マク大修道院では、そろそろ雪がちらつこうか、という時季である。 しかし今のベルナデッタには、凍てつく風もどこへやら。 ぴう、と鳴り巻き上がった中庭の枯れ葉が、祝福の紙吹雪にすら見えてくるようだ。 ところが、いつもながら重厚で冷たそうな石の建物の角を曲がったところで、 ベルナデッタはぎくりとした。冷たい風が吹き、急に背筋が寒くなる。 …否、正確に言えば、入ろうとしていた部屋の前で待ち構えていた人影に肝を冷やしたのだった。 「ベルナデッタ!」 「ひゃ、ひゃいい!」 ベルナデッタは、服の襟から背中に氷でも入れられたような声を出した。 慌てて曲がり角のこちら側に引っ込み隠れたが、無駄だったことを知る。 …そもそも返事をしてしまった時点で、『ここに居る』と自ら認めるようなものだ。 ベルナデッタは―― 一瞬逃げようとはしたのだが、相手がひょっこり顔を出す方が早かった―― 止せばいいのに、応対してしまった。 「なな何でしょおおう!」 早くも山の向こうに傾きかけた太陽。 斜めに差し込んだ日差しを受けて、柔らかそうに波打った髪が輝いた。 金と茶の間のようなそれは、光を透かすと温かみのある橙だいだいに見える。 真っ直ぐ見つめてくる大きな瞳も、同じ色。 ベルナデッタの故郷アドラステア帝国の――宰相エーギル公爵家の子息、 フェルディナント=フォン=エーギルだ。 「やっとこちらを見てくれたな。話があるのだ」 「はっ、話…?」ベルナデッタはどぎまぎした。 意味もなく視線を彷徨さまよわせるので、目が泳ぐ。「ベルにはありません!」 「な…っ」 フェルディナントは面食らった。 何も危害を加えようとしているわけではないのだが、彼女は一事が万事この調子。 たまにきちんと話が出来ていると思っても、些細なきっかけであっという間に取り乱す。 先生から直々に相談があり、あのエーデルガルトも困っているのを見て、 自分ならベルナデッタの抱えている悩みを何とかできる、してみせよう、と 宣言したまでは良かったのだが。先日、事件――いや、どちらかと言うと『事故』が起きた。 フェルディナントは、ベルナデッタが、引き籠もりから脱却できない自分を恥じていると思っていた。 それを払拭する手伝いをしようと決めたのだが、 手を差し伸べた途端、彼女はフェルディナントを頑なに拒絶したのだ。 「引き籠もりのままで居たい」と言って。 フェルディナントからすれば、予想外の返答だった。 その後ちょっとしたアクシデントがあり、フェルディナントは手首を痛めた。 幸い軽傷ですぐに治ったが、以来ベルナデッタはフェルディナントを避けて距離を取り、 顔を合わせても逃げ出すようになってしまった。 頼みの綱である先生はフェルディナントの心中にも鈍感だから、 こんな時に限って課題のグループも別々である。 ヒューベルトは「貴殿の報復を恐れているのですよ」などと物騒な事を言い笑っていたが、 そもそも『報復』しようなどとは思っていない。 だいたい、見た目も中身も真っ黒なあのヒューベルトならばともかく、 自分が彼女を怖がらせるような顔をしたつもりもなかった。 言い方が悪かったのだろうか?…とにかくショックだった。 「頼む、ベルナデッタ。まず聞いてくれ。落ち着いて」 「怪我させちゃったことは謝りますううう!! ごめんなさいいいい」 「それはもういい! いいから…」 「いやあああ、怒っていますううう! 許してえええっ!」 ちょっと語気を強くするとこの通り。全く困ったものだ。 これでは、端から見た人間が誤解するではないか。「宰相エーギル公爵家の子息ともあろうものが、 傷つきやすいヴァーリ伯のご令嬢を苛めている」と! 焦って掴んだ手首が、渾身の力で引き剥がされる。 どんな魔法か、ベルナデッタは立ち塞がったフェルディナントをするりと かいくぐって、自室に駆け込んだ。 「………」 フェルディナントは白い溜め息をつく。――今日も、失敗だ。
「び、びっくりした…もう、もうだめぇ…」 文字通り脱兎の勢いで逃げ出したベルナデッタは、 扉を閉めて鍵を掛けるや、その場にへたり込んだ。ぜえぜえときらした息を整え、そっと様子を覗う。 …フェルディナントの気配は無かった。 ほっとすると同時に、心の中でごめんなさい、と独りごちる。――いつもこうだった。 人と接するのが怖い。怒った顔が怖い。――だから いつもついつい逃げてしまうのだけども、気づくと寂しくなっている。 今度は、嫌われるのが怖い。たとえ嫌われたとしても、原因を作っているのは自分なのに。 「………」 息を整える。何だかまた申し訳ないことをしてしまった、と…しょんぼりした。 大いなる矛盾を抱えたまま、ベルナデッタは引き籠もるのだった。 ベル自身、これでいいと納得している。寂しくはあるけれど、外の世界は怖いから。 出ていって傷つくより、部屋の中で一人で過ごす安心を取る。 そんな具合だ。 もちろん、必要最低限の外出はする。講義には出るし、当番も課題もこなす。 食事もきっちり取る。 先生も、これで文句はあるまい。 そして求められる最低限のことさえこなしていれば、級長のエーデルガルトに怒られる心配も無い。 ――ふと、窓の外から、楽しげな笑い声が聞こえてきた。 今節は舞踏会が開かれる。そのためか、士官学校の生徒たちは浮き足立っていた。 舞踏会の前には『白鷺杯』という催しがあるそうだ。 各学級の先生方が選んだ代表選手が踊りの優劣を競う。 ――うちの学級から出るのは、きっとドロテアさんだな、とベルナデッタは一人頷いた。 何しろ、彼女はアドラステア帝国が誇る『ミッテルフランク歌劇団』の歌姫だ。踊りも難なくこなす。 先生が「一度みんなの踊りを見たい」と言ったその時、 ドロテアは、それはそれは見事な舞踊を披露した。 失笑を買ったベルとは違う。 艶やかに舞い踊る彼女にぼうっと見とれていたフェルディナントのことを思い出し、 ベルナデッタはほんの少し落ち着かなくなった。 小首を傾げ、胸に落ちかかった変な気分は気にしないようにした。 今日は編み物の続きをしよう、と思い立つ。 机の上に置いてあった籠を取ると、ベルナデッタは黙々と指を動かした。 こうして没頭していると、落ち着く。…アイボリー色の毛糸は、着々と編まれていった。 ――『上手ねぇ! 誰のため? 気になるひとでも出来たの、ベルちゃん!?』 ベルナデッタの器用さに心底感心し褒めてくれたドロテアは、 ベルに意中の相手が現れたのではと色めき立ったが、 そもそも対人恐怖症であるベルナデッタに、そんな相手が現れようはずがない。 念願叶ってドロテアとは仲良くなれたものの、 だからと言って他の人たちとも急に同じようにはできない。 親しくなるにもタイミングと時間、そして勇気が必要だった。 (せめて、もうちょっと何とかならないかな…) 実は、ベルナデッタはフェルディナントが苦手だ。 彼に悪いと分かっていても、ついついあんな態度を取ってしまう……。 …それをドロテアに相談してみたところ、ドロテアは至極当然のようにこう言った。 「ベルちゃんが気に病むこと無いのよ。フェル君の自業自得なんだから」 彼女が急に冷たい言い方をしたのでびっくりしたが、否定する気にもなれなかった。 フェルディナントは、思い込みが激しいところがある。 ドロテアが彼を毛嫌いするのも、ひょっとしたらそういう、ちょっと面倒なところが原因か。 …まあ、面倒を掛けるのはベルも一緒だ。せっかく仲良くしてもらえるようになったのだ、 ドロテアには、できるだけ迷惑を掛けないようにしないと。 「悪い人じゃ、ないんだけどなぁ…」 フェルディナントは明るく朗らかで、力強かった。 屋内に閉じ籠もるベルナデッタにさえ惜しげもなく光を投げかける、太陽のよう。…それが怖い。 彼に一度頷いてしまったら、そのままあの笑顔に呑まれて、自分が消えてしまいそうで…。 何よりまず『貴族の男性』という時点で、ベルナデッタは真っ先に自分の父親を思い出すのだった。 金銭欲の強い父は、ベルナデッタを厳しく躾けた。 その方法が酷い。四六時中椅子に縛りつけたりするのだから。 父が繰り返すのは「とにかく良い相手と結婚しろ」だった。 訳も分からず期待に応えようとしていたのは幼い頃からずっと。 しかし何をやっても父は怒るばかりで、「そんなんじゃ良い相手と結婚できない」と叱る。 そんなある日、気持ちの糸がぷつりと切れた。 心と体は見事に連動したようで、ベルナデッタは部屋を出ることが出来なくなっていたのだった。 部屋から引きずり出されて半狂乱になったベルナデッタは、結果、大怪我をした。 …それ以来、父はベルナデッタを無視するようになった。 期待に応えられなかった娘を責めるように、だ。 しかし、ベルナデッタにはそれで幸いだった。 ごめんなさい、とは思いながらも、父の期待に応えることがどうしても出来なかったから。 そして何より、父親がいつしか嫌いになっていた。怖くて、怖くて。 あんな剣幕で怒られ続けるんなら、無関心で居てくれた方がよっぽど、ベルにとっては平和だ。 「ごめんなさい、フェルディナントさん…」 もちろん、フェルディナントは父と違うと思う。 が、自身の理想を信じて疑わぬその様が、はきはきと強い言葉が、 時にベルナデッタを怯ひるませるのだ。 何より、フェルディナントは『貴族』であることを誇りにしている。 事あるごとに「貴族たる者」「貴族とは」と強調する。そこがまた、苦手たる所以だった。 貴族の勤めを果たすだなんて、自分には到底無理だ。 その点では、面倒臭がりのリンハルトとの方が、まだ話は合いそうである。 エーデルガルトも、フェルディナントやカスパルも――帝国貴族は、どうしてああなんだろう? 強くて、眩しい。 ベルナデッタには、どうしても真似できそうになかった。
次の日は待ちに待った休日だったが、ベルナデッタの部屋を訪れる者が居た。 先生だ。 当たり前のように扉越しに会話するこの担任に、ベルナデッタは いつものように鍵を開けることもなく返事する。 話題はどうしても、今節に控えた舞踏会と『白鷺杯』になった。 「貴族の皆さんはいいですよ、そりゃ。もう舞踏会とか済ませてるでしょうからね! あたしだって貴族なのに、そんなの一度も出たことがありません!」 ベルナデッタは、この士官学校に入学させられるまでは ずっと自宅の部屋に引き籠もっていたのだから、当たり前だ。 自分はそれで良い、と思っていたのに、なぜかひがみっぽい言い方になってしまう。 先生が小さく笑う。その声には女性特有の柔らかさがあった。 …よかった。先生はやっぱり先生だ。強い人だけど、父のように頭ごなしに怒ったりしない。 『白鷺杯』の代表者はやはりドロテアに決まったそうで、ベルナデッタは内心ほっとした。 「先生は、踊ったことありますか?」 そう訊くと、否の返答がある。 「フェルディナントが上手だそうだから、二人で教わろうか?」 「えっ!? いやいやいやいや、遠慮します!! 結構です! あたしはいいので、先生だけ教わってきてください!」 そう、と相槌を打つ先生。愛想を尽かされる感じは無い。 押しつけがましく主張するでも、一方的な教えをゴリ押しするでもなく―― 丁度良い距離感を保ってくれているので有難かった。 先生は言った。 「舞踏会は自由参加だけど、『白鷺しらさぎ杯』の前には会場に集合して。 点呼があるんだ。その後でご馳走が待ってるそうだから、ね。食事は一緒に摂ろう」 …さすがは先生、飴と鞭を心得ている。 先生との食事は、何故なぜか緊張しなくて済む。ベルナデッタは、「はい」と返事した。 なんだかくすぐったい気持ちになって、でもそれが嬉しい。 さあ今日も編み物を始めよう、と意気込んだ途端、再びノック音が響く。 ベルナデッタは扉に向かって呼びかけた。 「…先生? どうしたんです? 何か言い忘れですか?」 「ベルナデッタ、少しいいだろうか? 以前のことで……」 噂をすればフェルディナントだ! ベルナデッタは真っ青になった。 「で、出たああああ! 助けてくださいいいいいい!」 「ベルナデッタ、落ち着きたまえ。扉は開けなくていい。聞いてくれないか」 開けなくていい、と聞いて、ベルナデッタはあっさり手のひらを返した。 なら聞きます、と頷く。…これが結果的に、ベルナデッタのちょっとした転機になった。 ほんの少しだが、フェルディナントとの距離が縮まった気がする。 怖さも薄れた。扉越しに接したフェルディナントが、 会話の最後には、とても朗らかに笑ってくれたから。
翌日すっきりした顔で授業に出席したベルナデッタを、先生がにこりと笑って迎えた。 放課後、中庭で練習をする生徒たちに混じって、先生はフェルディナントに社交舞踏の基 本を習う。女性の踊り方と作法は、昨日ドロテアやエーデルガルトから教わったそうだ。 「さすがの先生も、踊りは苦手か?」 「仕方ないわよ。傭兵をやってた人が踊りまで上手かったら、私、妬いちゃうわ」 「いやあ、でも筋は良さそうだよ。飲み込みが早い」 遠巻きに眺めていたベルナデッタの前で、 カスパル、ドロテア、リンハルトら三人のクラスメイトが、先生に対して好きなように言う。 「先生、踊りも、練達の域、接近です」 フォドラの外から来たペトラは、まだたどたどしい独特の言葉で褒める。 級長のエーデルガルトが頷いた。 「本当ね。まさか一日で形になるとは思わなかったわ」 まだぎこちないが、先生の踊りはだんだんと様になってきていた。 相手の足を踏むことも無くなり、立ち姿や動きが素敵に見える。 (いいなあ) ベルナデッタは思った。が、 「でも、あれではちょっと踊りにくそうね」 エーデルガルトの言葉を聞いて、まじまじと様子を見る。 目立たぬよう、少しずつ踊る人たちの輪に近づいた。 「どうかね、先生!」 フェルディナントは一挙一動が大きい。 ダイナミックなのは良いことだと思うが、初心者の先生は付いていくのが精一杯のようだ。 「確かに、あれでは少々気の毒ですな。ぐるぐると引っ張り回される子供のようです」 くく、と吸血鬼のように真っ黒な印象のヒューベルトが笑う。 見ると、フェルディナントも少々息が上がっている。 ふと、「ヒューベルト」とエーデルガルトが自分の従者を呼んだ。 「彼と交替して、師に踊り方を教えてあげて」 「それは、ご命令ですか。私は踊りに興味などございませんが…」 「『お願い』よ。フェルディナントも疲れているようだし、代わってあげて。 師はまだ続けるつもりみたい。 …他ならぬ私たちの担任なのだから、何でも上手くなってくれた方がいい」 「は。仕方ありませんな」 ヒューベルトは、渋々なのか淡々となのか――フェルディナントと先生の居る方へ歩いていった。 若干の言い争いの後、フェルディナントに代わって先生の練習相手を引き受ける。 先生に向かって、慇懃に礼をした。 ちょっと驚いたようだった先生が、作法に乗っ取って女性側のおじぎを返すと、 そっと手を取りステップを踏む。 「そうです。一、二、三、一、二、三…」 ヒューベルトは先生を優しくリードしているように見えた。…すごく意外だ。 「じ、上手なんですねぇ、ヒューベルトさん」 ベルナデッタは思わず言った。誰にも話しかけるつもりは無かったのだが。 「ああ見えて、ね。器用なのよ。もっとも、 相手ならどう動くか…あれは、先読みの成せる技だと思うけれど」 「同意、です。動き、無駄ありません。完璧です」 「はあ…」 ベルナデッタは、ぽかんとして相槌を打った。 あれも戦術の延長というわけか。――まったく、ヒューベルトらしい。 一方、不本意ながら先生の相手役を交代したフェルディナントは、 こちらへやって来て、なおもどこか不満そうにヒューベルトの方を見ていた。 「あの…どうぞ」 ベルナデッタは、ベンチに引っ掛けてあったフェルディナントの上着を手渡した。 動きやすさを考えたのと、途中から暑くなったので脱いでいたのだ。 「ああ、ありがとう」 「着ないんですか?」 「まだ暑いからね」 「でもでも、汗が冷えちゃいます」 指摘するが早いか、っくしゅ!とフェルディナントがくしゃみする。 「ほら! 風邪ひいちゃいますよ。今節はいろいろあるんですから、大事にしておかないと」 「そうだな。君の言う通りだ。今日は暖かくして、早々に休むとしよう。 ……。ところで、ベルナデッタ。この後一緒に、紅茶でもどうかね」 「へっ!?」 ベルナデッタは素すっ頓狂とんきょうな声を出してしまった。 確かに昨日ベルナデッタは、扉越しに彼と会話した。 ずっと気になっていた怪我のことを謝ることができたし、 フェルディナントが笑ってくれてちょっと打ち解けられた気がした。 が、まだそこまでではない。紅茶を一緒に、などとは何と恐れ多い…。 「あああ、あの、結構です! あた…あたしは用がありますので!」 「そうか。では明日では…」 「明日もです! 仕上げてしまいたい絵がありますので!」 「…ほう。君は絵も描くのかね」 しまった。興味を持たれた。 「そ、それではベルはこれで!」 ベルナデッタは、そそくさとその場を後にした。怖くて恥ずかしくて、気づくとダッシュしている。 (お願いだから、ベルのことは放っておいてえぇ!) 心の中だけで、思いっきり叫んだ。
フェルディナントは困惑していた。 何故だか黒鷲学級の女性には、よく逃げられてしまう気がする。 エーデルガルトにも、ドロテアにも、そしてベルナデッタにも。 ベルナデッタ。昨日はやっと歩み寄れたと思ったのに。 今日だって、途中までは割と普通に会話できていた。 「何が悪かったのだろうな、先生」 お茶を出してくれた担任教師は、静かに微笑んだ。 フェルディナントが言葉を続けるのを分かっていて、無言で促す。 「私は何も、脅かすつもりはなかったのだ。嫌われたいわけでもない」 東方製の着香茶からは、異国の地を彷彿とさせる松葉の香りがする。 フェルディナントはこの香りが好きだ。一口飲むと体が温まり、気持ちが安らいだ。 「そうだね」担任教師は言った。「私も、嫌われるのは寂しい。もっと仲良くなりたい」 「先生も?」 「うん。だからこうしてお茶を飲みながら、君の出方を探っている」 「ははは、さすがは元・傭兵は言うことが違う。これも心理戦というわけか」 「お手柔らかに頼むよ。何しろ今日は踊りの練習で、もうくたくただ」 「ああ…そうか。その…悪かったな、先生」 「何が? こちらは助かったよ。 おかげで息の合わせ方や間の取り方が分かった気がする。相手との距離感もね」 「そう言ってもらえると救われるが…ヒューベルトやドロテアに言われたのだ。 私の踊りは独りよがりなところがある、と」 「そう? 私は、ノウハウが分かっている君に付き合ってもらって、有難かった。 何しろ踊るなんて初めてだったから、戸惑うことばかりで… 実を言うと、下手な踊りの相手を頼むのも、ちょっと気が引けてたんだ」 「そうだったのか」フェルディナントは目を見張った。「私で良ければ、いつでも練習相手になるよ。 また、声を掛けてくれたまえ。節末まではまだ時間もあるし」 「ありがとう。頼りにしている」 担任――先生は笑った。不思議だ。この人にこう言われると、もっと応えたくなってしまう。 「先生は、何というか……相手の懐に入るのが上手い人だな。いろいろと語ってしまう」 「そんなことはない。いつも探り探りで、実は必死。この学校に来てからはね」 「本当かい?」 「本当だよ。正直、教師だなんて務まるかどうか分からなかった。 私が分かっているのは、せいぜい戦の心得と剣の扱い方くらいだ。 魔法も専門外。教える前に自分が勉強しないといけない。必死だ。 …今は、社交舞踏を覚えるので精一杯」 ちらと肩を竦めた先生に、フェルディナントは軽やかな声を立てて笑った。 「細かい作法も難しい。舞踏会なんてものに出席する機会があろうとは思わなかったよ」 「舞踏会か……帝都での初めての舞踏会を思い出すな。 宰相である我が父の催す舞踏会……そこで私は見事な踊りを見せたのだ」 「フェルディナントは、踊り方も小さいうちから習ったの?」 「もちろんだよ。母や家庭教師から教わった」 「武器の扱い方や乗馬も?」 「ああ。その道で名高い教師がついてくれていた。もっとも、私にとって最初の教師は、 厩舎番やエーギル家のお抱え商人たちだったな。 私は子供の頃から乗馬や武芸が好きでね……もっと貴族らしくあれと躾けられたものさ」 「へえ」と先生は感心する。「貴族らしくあれ、か…」 「貴族として生を受けたからには、貴族として出来ることをする。 すなわち民の模範となり、皆を導かなくてはな。 そのためには、何でも出来るように日々の研鑽を怠りなくするのも大事なことだと思っているよ」 「何でもできるのが貴族?」 「まあ、それが望ましいね」 「フェルディナントはそうやって、ご両親の期待にも応えてきたんだな。実に前向きだ」 「ああ。……ありがとう。先生にそう言ってもらえると嬉しい」 そう、と先生は言った。ふと、思案する素振りを見せる。 「…ベルナデッタは、どうだろうね?」 「え?」 この話の流れで彼女の名前が出るとは思わなかったので、フェルディナントは驚いた。 エーデルガルトならばともかく。 「君と同じように考えていると思う?」 「いや…」彼は思い返してみた。「おそらく違うのだろう。何故だろうな」 「うん…そこから始まる」 先生は、ぽつりと呟くのだった。フェルディナントは問うた。 「どういうことだね?」 「自分と違う考えを持った相手に出会った時は、『何故だろう』から始まるんだ」 先生はフェルディナントの問いに答えると、茶を一口飲む。 「学校っていうのは、他人と関わる訓練をするには絶好の場所だね。 私はここに来てから、本当にいろいろ教わった。 例えば、君が言う『貴族らしく』というのも…その人が『貴族』をどう捉えているかで変わる。 『価値観』というやつだ。 『価値観』は、人によって違う。 育ってきた環境、親の教え、経験…その人にはその人の『価値観』があって、 自分が思っていた『常識』が、『常識』じゃなかったりする」 「…そうだな」 「『価値観』は、人の数だけあるんだ。私も最初は驚きの連続だったけど、 世の中にまったく同じ人間なんて居ないんだから、当然だよね」 「その通りだ」 「それを踏まえて、私はまず相手を観察することにした。たとえば君が、何故そんなことを言うのか。 何故、そんな行動をするのか」 深い青の瞳に見つめられて、フェルディナントはぎくりとする。心の奥まで見透かされそうで。 …そんな彼をよそに言葉を一旦切ると、先生は話を戻した。 「ベルナデッタは、フェルディナントを嫌っているわけじゃないよ」 「そうだろうか?」 「あの子は怖いんだ」 「怖い!? それは『嫌っている』と同義ではないのかね。怖い…この私が? 何故!?」 「さて、何故だろう?」 「くっ…むう。なるほど、そこから実習が始まるというわけか」 ふふ、と先生は微笑んだ。 「他人と接するにも、それぞれの距離感がある。 十年来の友人と、たった今会った人間では、君だって接し方や心持ちが違うだろう? きっとベルには、扉一枚隔てているくらいが丁度いいんだ」 ――扉一枚、隔てた距離。 「ああ…そうか。そうだな…私も――昨日、話をしたのは扉越しだった。 彼女は最後まで話を聞き、落ち込んでいた私を励ましてくれたよ。一生懸命、とても親身に」 「仲良くなるにも、順序があるしタイミングがある。 『価値観』と同じように、親しくなる方法も、『これが絶対に正解』というのは無くて… きっと何通りも、人の数だけあるんだよね」 「……っ」 「君は『貴族は模範となり、皆を導く』と言ったね。素敵だと思うよ。 その言葉通り、これからも他の子が悩んでいたら、そっと相手に寄り添って手を引いてあげて。 今日、私に踊りを教えてくれたみたいに」 「それは、先生の役目だろう」 「逆になることもある。私だって、迷ったり悩んだりするよ。人間なんだから。 …というわけで、明日もよろしく」 ははは、とフェルディナントは笑った。舞踏練習の約束だ。 「もちろんだ。さて…馳走になったよ、また声をかけてくれたまえ。私はいつでも応えよう」 悠然と立ち上がった彼だったが、どことなくそわそわ部屋を出る。 「先生、見ていてくれたまえ。私は『貴族』として、迷える級友にも道を示すよ!」 自信満々で宣言するのだった。 担任教師は空になった茶器をカチャン、と片付けながら、閉まった扉に向けて呟いた。 「いってらっしゃい」 …自分の意図するところが正確に伝わったのかどうかは怪しいが、 フェルディナントは、目標を立てたらそれに邁進する。 彼は誠実に相手のことを理解しようと努めるから、 徐々に距離を詰めて相手の懐に入るのも時間の問題だろう。
――『ベルには、扉一枚隔てているくらいが丁度いいんだ』 フェルディナントは、その足で即ベルナデッタの部屋の前に向かった。扉の前に立ち、ノックする。 「ベルナデッタ、ベルナデッタ! 居るかね」 ところが、今日に限って返事は無かった。 「ベルちゃんなら居ませんよ」 右隣の部屋が開いて、ドロテアが顔を出す。「まったく、なんの騒ぎ? 静かにしてください」 早速実践だ、とフェルディナントは意気込む。そうだ、まずは相手との距離感を測るのだ。 「と…すまない。取り急ぎ用があったのだ」 「用、ねぇ…。どんな用かしら?」 ドロテアは明らかにフェルディナントを嫌っている。 物言いが相変わらずフェルディナントに対しては冷たく、隙を見せない。 彼女は、フェルディナントを頭からつま先まで検分して――睨んだ。 「女性の部屋の前で待ち伏せなんて、無粋ですよ。 はっきり言ってさしあげますけど、貴方が事あるごとに大きな声で話しかけるから、 ベルちゃんは怯えてます。…可哀想に、今日だってビクビクして…これ以上脅かさないであげて」 「そ、それは悪かった。今しがた、反省してきたところだ」 「それで謝りに? 律儀ですこと」 「なぜ君は、私をそんなに嫌うのだね」 「言ったでしょ? 答えは、私の出したなぞなぞを貴方が解いてから。…さよなら、蜜蜂さん」 フェルディナントは歩み寄ったが、鼻先で扉をバタンと閉められる。 …まったくだめだ、と思った瞬間、ドロテアが再び顔を出した。内心喜んだのも束の間、彼女は言う。 「ベルちゃんに何かしたら、私が許しませんから」 ドロテアは聞こえよがしに大きな音を立てて、扉を閉めた。 「………」 フェルディナントは途方に暮れてしまった。 扉一枚が隔てた距離が、こんなにも遠いとは。
しかし、その後もフェルディナントの挑戦は続いた。 ドロテアの厳しいガードにもめげず、ベルナデッタに一定の距離を保って話しかけることにする。 授業で隣に座った時は、椅子を離し、なるべく声を抑えて。 食堂で見つけた時には、脅かさないようにテーブルを挟んだはす向かいから。 上手くいくこともあったが五分五分で、大抵は逃げられてしまうのだった。 ベルナデッタは花が好きなようで、温室にもよく通っていた。 彼女が花を世話する様子を、そっと遠くから見守る。脅かさないように、怖がらせないように…。 「……。あえて伺います。何をしているのですかな」 「どぅあ! …ヒューベルト!? な、何とは…いや、別に」 装いも心の中も真っ黒な、この皇女殿下の忠実なる僕しもべは、含みある笑いを漏らした。 「下手な嘘はやめていただきたい。監視はもっと気づかれないようにするものですよ」 水やりを終えたらしいベルナデッタが、フェルディナントとヒューベルトに気づいて そそくさと横を通り過ぎていく。――また話しかける機会を失ってしまった。 「最近の貴殿の行動は、ベルナデッタ殿に似てまいりましたな。くくく…」 ヒューベルトの発言は、いつもながら神経を逆撫でする。 フェルディナントは一瞬むっとしたが、すぐに思い直す。 ベルナデッタに似てきた…ということは、ベルナデッタに近づけたということだ。 これで、彼女の気持ちが少しは分かるようになるかもしれない。 「まあ、努力は評価しましょう。相手を真似たとて、そう簡単に理解できるとは思えませんが」 「真似? そうか!」フェルディナントは一人納得した。 「ヒューベルト、よく言ってくれた!『学ぶ』は『真似ぶ』、というではないか!ああ、よし!」 ぱっと顔を上げ、ベルナデッタを追いかける。 「やれやれ…」 ヒューベルトは踵を返し、温室の奥に入った。
空になったじょうろに再び水を汲んだベルナデッタは、寮の裏手へ向かった。 ちょうど建物の影になるこの一角に、自身がこっそり育てている鉢植えを置いてある。 ウィンターローズだ。 名前通り冬に咲き半日陰を好むこの花は、『薔薇』と名が付いているが、キンポウゲ科の植物だ。 開花開始時期である『星辰せいしんの節』とその花の形から『星薔薇』とも呼ばれていた。 花言葉は、「慰め」「中傷」「私を忘れないで」「私の不安を和らげて」――この花言葉と 日陰で控えめに首を下げて咲く様子に、なんとも親近感が湧くベルナデッタなのだった。 「おはよう、お花さん。今お水をあげるね」 この様子では、開花までもう少し。『白鷺しらさぎ杯』を待たずに咲くかもしれない。 この花は寒さに強い品種だが、気温の低い時間帯に水をやると根が凍ってダメージを受ける。 そのため、水やりのタイミングには気をつけていた。 ベルナデッタは、うふふと笑った。 「お花はいいなぁ…可愛いし、話しかけてこないし」 ところが、至福の時間を邪魔する者が現れる。…フェルディナントだ。 「ベルナデッタ、ここに居たのか!」 ベルナデッタは小動物さながら、ぴゃっと声を上げて跳び上がった。 「フェッ、フェルディナントさん! 奇遇ですねぇ!どうしたんですか、こんな朝早く」 また脅かしてしまったと見るや、フェルディナントは咄嗟に声を抑えた。 「いや、朝の散歩を…冬の早朝は寒いが、爽やかで良いものだね」 君を探してきたのだ、とは言わずにおく。慎重に近づいた。 「さっ、爽やか…? そ、そうですねぇ!」 「…む。それは、君の育てている花かね」 「そ、そうです」 「蕾を持っているではないか。もう少しで咲くのだね」 「はい」 「……」 「……」 奇妙な間が空いた。 お互いにもうだめか、と思った時には、相手が目の前に居る。 フェルディナントは微笑みかけた。 一方ベルナデッタは、気が気ではない。 「実に可愛らしいね。どうだろう、花が咲くまで、私にも水やりを手伝わせてくれないだろうか?」 『学ぶ』は『真似ぶ』を早速実行しようとするフェルディナントである。 「へっ!? いえいえ! 貴族の務めでお忙しいフェルディナントさんのお手を煩わずらわせるわけには いきませんから!」 (――駄目か) 今のは遠回しに断られたのだな、と彼は察した。 (いやいや、焦るなフェルディナント。彼女には、彼女の良しとする『距離感』があるのだから) 「では…咲いたら私にも見せてくれまいか」 「はっ!? いつでもどうぞ! 鉢ごと、ここに置いてありますので」 「そうか」だがフェルディナントは、ここで食い下がった。 「しかし、私もいろいろ忙しくてね。…花が咲いたら、君が知らせてくれないか?」 「え、えぇ…?」 「嫌かい?」 「め、滅相もありません!! わかりました!!」 ベルナデッタは全力で返答する。もしここで断ったら、何をされるか。 …たとえ嫌でも、嫌とは言えなかった。ほとほと困ってしまった時、鐘が鳴った。 ベルナデッタはこれ幸いとその場から立ち去る。 「でっ、ではベルはこれで!」 慌てて駆けていくベルナデッタの背を見送りながら、 フェルディナントは手応えを感じ、ぐっと拳を握りしめた。
数日後、ベルナデッタは授業を欠席した。 いつもの引き籠もりだろうと皆が言う。ところが、級長のエーデルガルトが進んで席を立ち 寮の部屋まで呼びにいくと、彼女は熱を出して寝込んでいた。 「風邪ね」 …ベルナデッタの心身を考慮して、医務室から彼女の部屋まで 出張してきたマヌエラ先生が診断する。 「誰かさんが追い回すからですよ」と、ドロテアがフェルディナントを批難した。 「昨日もベルちゃんの部屋の前に居たでしょう。ベルちゃん、帰れなくて外をウロウロしてたんだわ」 とんだ言いがかりだが、もし本当ならば申し訳ない。 授業を終え、先生の踊りの練習に付き合った後、フェルディナントは見舞いに行こうとした。 だが、ふと我に返る。 見舞いに行ったとしても中に入れてはもらえないし、彼女の精神衛生上よろしくない。 下手をすると悪化させるやもしれぬ。見舞いは、ドロテアや先生に任せた方が良さそうだ。 他に何か出来ることはないかと考え、フェルディナントは思い立つ。 「そうだ!」 ベルナデッタの鉢植え。今日は水をやったのだろうか? フェルディナントは急ぎ寮の裏手へ回り込み、鉢植えを確かめた。…土は乾いている。 早朝の水やりが行われたかどうかは不明だが、水は多い方が良いだろう。 じょうろに水を汲んできて、たっぷり鉢に撒いた。 「…おっと」 更に、フェルディナントは気づいた。ここでは陽が当たらない。 光をたっぷり浴びた方が花も喜ぶだろう。――そう思って、鉢植えをずらした。 ベルナデッタが寝込んでいる数日間、彼は人知れず鉢植えの元へ赴き、世話をした。 おとぎ話の世話好き妖精にでもなったような気分だった。 これで、数日後には綺麗な花が咲くだろう。 ベルナデッタが喜ぶ顔を想像し、フェルディナントは一人、悦に入った。 ――ところが、それからまた数日経ったある日の放課後。 悲鳴を聞きつけフェルディナントが寮の裏手を覗き込むと、ベルナデッタがそこに居た。 どうしたのだろう。鉢植えを前にへたり込み、ひどく狼狽えている。 「どうしたのだ、ベルナデッタ!」 「ふぇ、フェルディナントさん…」 彼女は青い顔をして、フェルディナントを見上げた。 「具合が悪いのか? 無理をするな。さ、部屋に戻るんだ」 「お花が」ベルナデッタは、か細い声で言った。「ベルの可愛いお花がぁ…!」 「!」 フェルディナントは絶句した。 ベルナデッタとフェルディナントが二人して手塩に掛けた花は、 綺麗に咲くどころか、見事に萎れていたのである。
「申し訳ないことをした……」 落ち込んだフェルディナントは呟くように言った。 「それは私じゃなくて、ベルナデッタに言ってちょうだい」 エーデルガルトが小さな溜め息をつく。「……貴方でも落ち込むことがあるのね」 結局、今日もベルナデッタは部屋に引っ込んで授業に出てこなかった。 誰がこんなことを――萎れた花を見て取り乱す彼女に、 自分が良かれと思ってやったのだ、と――フェルディナントは、どうしても言えなかった。 好敵手に弱みを見せたくはなかったが、エーデルガルトもまた花の手入れをしているのを見て、 彼は事の顛末を打ち明けた。…誰かに聞いてほしかったのかもしれない。 鉢植えを世話した白い手は、泥に汚れていた。 フェルディナントも入学当初、温室管理係の指導の下で薔薇を育てた経験があるが、 エーデルガルトの鉢植えに咲く花が何なのかは知らなかった。 縁だけが紫がかった白い花びらは、うつむくように下を向いている。 「ずいぶんといじけた…いや、奥ゆかしい咲き方をする花だな」 フェルディナントは言葉を選び直した。 「…これは、日陰に咲く花よ。寒さに強いけど、霜に当たると枯れてしまう。 寒くなる時間帯に水をやると根が凍って駄目になるし、 かと言って陽の光に当てすぎると、今度は葉がダメージを受ける… 育て方も単純そうに見えて、繊細なの。貴方、知らなかったの?」 「え?」 「この花のことよ。ベルナデッタも育てていたでしょう」 「……!」言われてみれば、この葉の形。見覚えがある。「こんな花が咲くのか…!」 うつむいた花は、可愛らしい星の形をしていた。 「色は、いろいろあるけど。彼女が育てていたのも、これと同じかしら?」 「む…だと思うが…分からない。何しろ、蕾つぼみのまま駄目にしてしまったから」 「そう…。じゃあ、代わりにはならないかもしれないわね。 でも、もし彼女が興味を示すようだったら、『元気になったら見に来て』と貴方から伝えて。 鉢植えをお見舞いに持っていくわけにはいかないから」 「エーデルガルト…だが、私は」 「怖じ気づいたの? 貴方らしくもない」 「私が…らしくない?」 「いつもの自信家で誠実なフェルディナントのままで、ベルに会いに行くといいわ。 彼女は…あの通りだけれど、話せばきっと分かってくれる」 「だが…」 「自分の過ちは自分で何とかしなさい。 私と張り合おうという人が、鉢植え一つ駄目にして、謝罪することもできないの?」 「……っ 言われなくても謝りに行くさ!」フェルディナントはむきになって宣言すると、ぱっと踵を返した。 「ありがとう、エーデルガルト!!」 捨て台詞のような調子で、しかし律儀に礼を言う。 呆気に取られたエーデルガルトは…次の瞬間、人知れず小さく失笑した。 ――その日の晩、部屋に籠もったベルナデッタの元に、 手紙と小さな見舞いの花が一輪、扉の下の隙間から届けられた。 手紙を見たベルナデッタはびっくりして思わず扉を開けたが、 そこには既にフェルディナントの姿は無かった。
翌日、食堂の一角。 冬は暖気を逃がさぬよう衝立で仕切られたスペースの――ちょうど空気が抜けて寒い 出入り口寄りに、珍しくベルナデッタの姿があった。何やら無心で編み物をしている。 もう具合は良いのだろうか?…見つけた途端フェルディナントはどきりとしたが、 意を決して彼女の方へ行くのだった。 やはり、手紙での謝罪はフェアじゃない。今日は嫌われようと、真っ正面から謝ろう。 「ベルナデッタ、すまなかった!!」 「ひえっ! 近寄らないでくださ~い!!」 案の定の答えが返ってくる。 フェルディナントは内心、自嘲気味に笑った。…先生、やっぱり嫌われてしまったよ、と。 だが、しかし。衝立の向こうから声がする。 「あんまり近寄ると、風邪、うつしちゃうかもしれないですから…そ、そっち側に居てください…」 「っと、そうか…。これでいいかい」 フェルディナントは、衝立を挟んで少し下がった。 「は、はい。いいです」 衝立越しに、二人は話し始めた。 「フェルディナントさん。昨日はお見舞いのお花、ありがとうございました。 それと…手紙、読みました。あたし」 「ああ…そうか。だが改めて謝らせてくれ。 君の大切にしていた鉢植え…私が駄目にしてしまった。 本当にすまなかった」 「いいんです。ちゃんと説明しなかったベルが悪いんですから」 「だが、私がもっときちんと話を聞いていれば、こんなことには」 「その前に、ベルがちゃんとお話聞かないし、できないですから!」 「……っ」全力で言い切るのか。「ははっ…あははは」 フェルディナントは、思わず笑い出してしまった。直前まで悲壮な顔をして謝っていたのに。 いつぞやの、扉越しの会話の調子が再現されたようだった。良い感じだ。 「わ、笑いますかぁ? そこで…」 「あ、ああ…これは申し訳ない」 「しかもそこで謝るんですね」 「……君は私にどうせよというんだね」 衝立越しで見えないが、フェルディナントの困惑顔を想像すると何だか可笑しくなって、 ベルナデッタはくすくすと笑った。 「これは珍しい。君が笑ったぞ!しかも声を上げて」 「あっ」 慌ててベルナデッタは我に返る。 フェルディナントは余計なことを指摘した自分の口を呪った。 衝立を隔てたこの丁度良い距離感…気づけば今日は 仲直りできる絶好の機会だったというのに。 「今のは忘れてください! でっ、では!用も済みましたので、ベルは失礼しますね」 そう言うと、まだ途中の編み物を慌てて籠に仕舞い込む。勢いよくガタッと椅子から立ち上がった。 また、そそくさと去ろうとする。 「待ちたまえ! どうして君は、そう――」 ――『あの子は怖いんだ』 フェルディナントは、はっとした。 ベルナデッタが引っつかんだ籠の中から、暖かそうな色味の毛糸玉が音も無く転がり落ちる。 「わわっ」 毛糸玉はちょうど編みかけの作品と繋がっていたようで、 だいぶ長くなったマフラーらしきものが目に入った。 編み棒ごと、それも床に落ちる。 マフラーにしては幅が広くて大判だった。――誰のために編んでいるのだろう。 慌てるベルナデッタの目の前で、毛糸玉はころころと尾を引いて、 フェルディナントの足元に到着した。 フェルディナントは、咄嗟に毛糸玉に手を伸ばす。 ベルが珍しくここに居たのは、こうして話をするためだ、と彼は思い当たった。 病み上がりの引き籠もり娘は、意を決して――おそらく相当な覚悟で、 ここで待ってくれていたのだろう。他ならぬ、自分の事を。 怖いだろうに、こんな場所では寒いだろうに。…待ってくれていたのだ。 つん、と毛糸が引かれた。 編み物を手に今日は逃げることもせず立ち尽くす彼女を見て、予感は確信に変わった。 二人を隔てる扉や衝立は、もう目の前には無かった。 床の上に線を描いたアイボリーの毛糸が、二人を繋いでいる。 フェルディナントは毛糸玉を拾うと、立ち上がりざまベルナデッタを見た。 そのまま毛糸を巻き取っていけば、自然と距離が詰まる。 どこまでなら、と――言葉に出さずに彼女に問うた。 (どこまでなら、近づいても許される?――私は) ふと手繰り寄せた毛糸の先、 編みかけのマフラーを手にして固まったベルナデッタも、こちらを見ている。 フェルディナントは毛糸を頼りに、一歩、また一歩とベルナデッタに近づいた。 ――『ベルは引き籠もりのままでいたいの! 邪魔しないでええええ!』 ――『失敗しちゃった日は、やっぱり外に出られません。怖くて。でもでも、翌日はまた、頑張ります』 ――『フェルディナントさんがいつも努力してるのは知ってますから……』 (ああ、そうだね。私も知っていたよ) 出来ないことを出来るようになろうと必死に努力する、君のことを。 フェルディナントは微笑み、ベルナデッタに巻き取った毛糸玉を手渡した。 「あ、ありがとうございます…」 ベルナデッタは、うつむき気味に礼を言った。 「…そうだ。エーデルガルトが言っていた。もし君さえ良ければ、彼女が育てた花を見においでと」 「…ほぇ?」 「部屋に帰るなら私が送っていこう。だが、その前にどうだね。案内するよ」 「…。はい」 ベルナデッタは思わず頷いてしまった。 断りにくかったのは、彼の言葉に有無を言わせぬ響きがあったから。 しかし、その他に別の――正体不明の感情が湧いて出たのを、彼女は感じた。
「わあ、こんな色のもあるんですね!きれい…」 「君の育てていたのも同じ色かい?」 「いえ、ええと…ベルのはたぶん、原種に近いやつなので…もっと濃い、 真っ茶色の花が咲くんじゃないかと思います」 「ま、真っ茶色?」 「それはそれで素敵ですよ。『燻し銀』てやつですかね」 「茶色なのに?」 「はい」 フェルディナントは、明るい声で笑った。 ベルナデッタも安堵したように微笑んでから、またうつむく。 「フェルディナントさん。あ、あの…ベルも謝らないと。ごめんなさい」 「何だい?」 謝罪の理由が分からず、フェルディナントはきょとんとした。 「ベル…ずっとフェルディナントさんのことが怖かったんです」 「そうか」 知っていたよ、と言うのはやめておく。 ベルナデッタは、目の前で祈るように組んだ両手の指を動かした。 「フェルディナントさんは何でもできますし、いつも自信満々で……太陽みたいに、眩しいから」 「…。それは、褒め言葉とも受け取っておこう。君は、晴れの日が嫌いかね?」 「晴れの日は好きですよ? でも、例えば夏の日差しは強くて怖いなぁ、と思うこともあります。 あんまり明るくて眩しいと、怯んじゃうというか……」 ベルナデッタは言い淀み、しかしまた言葉を続けた。 「あたし、ひとと話すの苦手なんです。特に、父みたいな怖い人は…」 「…お父上が?」フェルディナントは首を傾げたが、その話はさて置いた。「私も怖いかい?」 「…あの、その…はい。ごっっ、ごめんなさい!」 「いいんだ。謝らなくていい」 予想通りだったものの、フェルディナントは内心落胆した。 「何故なぜかな。訊いてもいいかい?」 「……。強そうな人は、怖いです。大きな声で話しかけられると、次は何をされるかって…。 もっ…もちろん、フェルディナントさんは優しい人だって、分かってるんですけど! …あっ、こないだ分かった、かな」 「そうか。それなら良かったよ」 ははは、とフェルディナントは笑った。ちょっと、ほっとしたのだった。 「羨ましいな、とも思います。周りから期待されて、その期待にきちんと応えることもできて。 あたしには、どうしても無理だったから… お父様は、『どうしてお前は出来ないんだ、そんなんじゃ嫁のもらい手も無い』って。 貴族の役目は、賢く社交的に振る舞って、家を存続させてより優秀な血を残すこと、ですよね。 特に女は、良い結婚をするためにも程良く賢く、程良く馬鹿で可愛げが無きゃいけない。 押すところと引くところをわきまえて、男を立て、優秀な女になって優秀な男に嫁げ。 優秀な人間の元にはお金が集まる。そのお金で貴族は繁栄していくんだって…延々と聞かされて」 「ヴァーリ伯が、そのようなことを」 それは一理あるが、何とも極端な主張だとも思える。 「でもベルは駄目なんです」ベルナデッタは、更にうつむいた。 「フェルディナントさんみたいだったら、あたしにももっと違った人生があったでしょうか? フェルディナントさんみたいに明るくて朗らかで、何でも出来たら、何者をも恐れず…」 「それは違うぞ、ベルナデッタ」フェルディナントは、優しく言ってベルナデッタを止めた。 「それはあくまで、お父上の『価値観』で量った君あって、 君自身が『駄目だ』と断定する根拠にはならない。思い違いだよ」 「思い違い……?」 彼女はおずおずと顔を上げる。探るようにフェルディナントを見て、問いかけた。 「ああ。それに、私にだって出来ないことや、恐れることはあるぞ」 「何なんですか?」 「…何故嬉しそうなのだね…まあいい。分かるだろう? 君の大切な花を、きちんと咲かせることができなかった」 「そ、それは…」 「そして今、私は心底恐れているよ。君との距離感を取り違えたまま、君に嫌われてしまうことを」 ベルナデッタは、何と言っていいか分からず立ち尽くしてしまった。 フェルディナントは、エーデルガルトの育てた鉢植えの元にしゃがみ込み、 縁が紫がかった白い星形の花に触れる。 花は、恥ずかしそうに下を向いていた。 「こうして改めて見ると、日陰に咲く花も可憐なものだね」 そう言うと彼は、すっと立ち上がる。 帰ろう、と促され、ベルナデッタは頷いた。部屋まで送ってもらい、別れる。 ぱたん、と扉を閉めると、フェルディナントの声がした。 「ベルナデッタ」 「は、はい!」 「いや、その…また明日」 「は、はい。ありがとうございました!」 相手から見えないにもかかわらず、ベルナデッタは深々とお辞儀をする。 扉にもたれかかると、ほーっと息をついた。 それを気配と音で感じ取ったフェルディナントは、不思議と自分もほっとしていることに気づいた。 なるほど、他人と関わるには、嫌われるかもしれぬという不安がこうして付きまとうものなのだ。 自分が相手に好かれたいと、思えば思うほどに。 …酷いジレンマだった。 彼は、再び担任教師の言葉を思い出す。一人納得した。 ――『ベルには、扉一枚隔てているくらいが丁度いいんだ』 自分も相手も傷つけない、傷つかない距離が。
とうとう『白鷺杯』の日がやって来た。 ドロテアは見事な舞踊を披露し、他の学級の選手を抑えて優勝した。 「おめでとう、ドロテアさん!」 「ありがとう、ベルちゃん。…まあ、それ…」 「うん、あの…あのね」ベルナデッタはもじもじしたが、 ドロテアの隣で先生が頑張れ、と拳を握るのを見て思い切った。 「ドロテアさんにプレゼント! ひ、膝掛けなんだけど…」 「嬉しいわ。ありがとう、ベルちゃん!」 ベルナデッタの方こそ嬉しかった。喜びのあまりぼうっとしてしまい、てへへ、と笑う。 「優勝祝いになって良かったよ~」 「さあ、次は先生の番ですよ」ドロテアはきらきらと瞳を輝かせて笑う。「ふふっ… 練習の成果を見せてください」 大丈夫かな、と先生は躊躇した。 ベルナデッタは、声に出さずに「大丈夫」と請け合う。 だって、先生だもの。 『白鷺杯』の後も、日を改めた舞踏会の前も――夕食の卓は、学級毎に囲んだ。 エーデルガルトと共に先生の両隣を挟んで座ったベルナデッタは、ご馳走を堪能した。 賑やかな食卓は落ち着かなかったが、そんな中に在っても先生の隣は不思議と落ち着く。 食後は、すぐに部屋に引っ込もうとした。 舞踏会への参加は耐えられない。 だが、浮き足立つ男女が楽しそうに舞踏会場となった大広間へ向かうのを見ると、 ちょっぴり羨ましくなった。 遠くから見るだけなら、と思い、ベルナデッタは大広間に入る。 先生が心細そうだったら、柱の陰からでも応援しよう、と心に決めた。 気づけば、先生はみんなの人気者だった。 踊りの相手をお願いしようとして牽制し合う生徒たちの視線の先に、 見事に壁の花と化した先生が突っ立っている。 やがてこの日のために招かれた管弦楽団がワルツを奏ではじめると、 生徒たちはほぼ男女二人でペアになってしずしずと進み出、踊り始めた。 先生は誰からも声が掛からずほっとしていたようだったが、そうは問屋が卸さない。 金鹿学級の級長クロードが何食わぬ顔で先生の手を取り、ウィンクをした。 手を引き、フロアの中心にエスコートする。 (――ぬう。やりますね、クロードさん。先生、頑張れ~!) ベルナデッタは唸った。そのまま、自身は会場の柱になったつもりで先生を見守った。 先生がそっと会場を離れたのは、宴もたけなわになった頃だった。 「あれ、先生…?」 どこに行くんだろう? 先生が踊らぬのなら、応援する必要もない。 …何だか疲れちゃったし、そろそろ部屋に帰ろうかな、と思ったが、先生は中庭に出ていく。 大聖堂の方に行くということは…女神の塔に入るつもりだろうか? 興味を惹かれて、ベルナデッタは後を追いかけた。 大聖堂は静かだったが、思ったより多くの人が居た。 立ち入り禁止のはずの女神の塔周辺にも生徒が居て、示し合わせたように中に入っていく。 それもそのはず、 舞踏会の夜には、『女神の塔で男女が何かを約束すると、それを女神様が叶えてくれる』と いう噂があるのだ。 ベルナデッタはそんな噂知りもしなかったが、 どことなく場違いな気がして先生の捜索をあっさり諦めた。 「やっぱり部屋が一番かも…」 はあ、と溜め息をついた。 外は寒いし、一人ぼっちは寂しい。 空気は澄んでいて星が綺麗だが、ベルナデッタには 一人寂しい舞踏会の夜を無駄に演出されているようで、何ともやりきれなかった。 (――やっぱり帰ろうっと) 中庭に戻ったところで、フェルディナントと行き会った。 「やあ、ベルナデッタ」 いつもながらの溌剌はつらつとした笑顔だ。この人が居ると、そこだけ明るく華やいで見える。 「これは奇遇だな。舞踏会を抜け出し、一休みしようとしたところで出会うなんて……」 「そ、そうですね。最近よく会いますよね。 あれ…そっちから来るということは…もしや、フェルディナントさんも先生を探して来たんですか?」 「な、何を言うんだね。ただの偶然だよ、偶然。 エーギル家の嫡男たる私が、女性の後をつけるはずも……!」 「そうですか。ベルは追いかけたんですけど、見失っちゃって。帰ろうかと」 「か、帰るのかね」 「はい。舞踏会もそろそろ終わりですし、他に用もありませんし」 逃げるようにその場を去ろうとした時、 「待ちたまえ!」 フェルディナントが呼び止めた。 その強い調子に、ベルナデッタは条件反射でびくっとする。 (何だろう? あたしまた、何かまずいこと言っちゃったかなぁ…!?) ざっざっ、と大股で歩み寄ってくる気配がした。 (女神様、もし見ていらしたら助けてください!) だが助けなど現れるはずもなく、あっという間にフェルディナントに回り込まれてしまう。 寒さと緊張で震えだしたベルナデッタに、フェルディナントは――手を差し出した。 躊躇いがちに…けれど確かに。 大広間からは音楽が漏れ聞こえてきている。 曲が終わり、しばし静かになった後、また別の曲が流れ出した。 しんしんと冷える中庭は静かで、とくにベルナデッタたちの周囲は、人もまばらだ。 ほとんどの生徒たちは舞踏会場となっている大広間の中か、女神の塔周辺にいるのだろう。 フェルディナントは、ごほん、と咳払いをした。 「一曲お相手願えないだろうか」 「え!? あ、ああああたしですか? フェルディナントさんてば、冗談きついです! ベルの踊りを見たでしょう! フェルディナントさんまで笑われちゃいますよ!」 「大丈夫。誰も気にしやしないよ」ははは、とフェルディナントは笑った。 彼もクラスメイトも――ベルナデッタが踊りを何の気なさそうに――しかし、 いとも羨ましそうに眺めていたことを知っていた。 なんとなくもじもじしながら、彼女は実は拍子を取っている。 今さっき流れ始めたこれは、毎年舞踏会の一番最後に流れるという、 女神たちの祝宴を表した曲だった。 「――最後は私と踊ってくれないか?」 「……っ」 ベルナデッタは言葉を失い、真っ赤になった。 一体何が起こっているのだろう? ――困って振り返ると、窓の灯りがちらちらと瞬いている。 仰いだ空に星が輝き、ベルを見守りながら微笑んでいるようだった。 彼女はうつむき――やがて恐る恐る顔を上げ、上目遣いにフェルディナントを見る。 「……はい」 瞬間、フェルディナントが、ぱっと瞳を輝かせた。いかにも嬉しそうな顔をする。 二人は曲の途中からタイミングを合わせて礼をし、そっと近づいた。 フェルディナントが颯爽と差し出した手を、ベルナデッタがおずおず取ろうとする。 触れるか触れないかのところで、フェルディナントはベルナデッタの手を強く引いた。 「きゃっ!」 「す、すまない。痛かったかい?」 二人の、どことなくぎこちない踊りが始まった。 相変わらずフェルディナントの動きは伸びやかで大きい。 だが、歩幅などを小さくして精一杯合わせようとしてくれているのが、ベルナデッタには分かった。 「大丈夫です」と、笑う。 「…つっ!」 「ひぃぃ!? ごごごごめんなさいぃ!」 お約束的に、ベルは相手の足を踏んでしまう。だが、フェルディナントは笑顔だった。 ベルを見て怒るでもなく、落胆するでもなく。 「大丈夫だ。続けよう!」 ベルナデッタは、夢中で踊った。本当に、夢でも見ているようだった。 曲の最後に、ベルナデッタをくるりと回し、フェルディナントは至近距離で告げる。 お互いに触れている箇所が、温かかった。 「君には申し訳ないが…私はやはり、話すのならば君の顔が見たいよ。 だから、今日は私の申し出を受けてくれて嬉しかった。ありがとう」 「……」頬をぼうっと上気させたベルナデッタは、はにかんで笑った。 「フェルディナントさんは、いつも唐突なんですよね」 「唐突?」 「はい。前向きだし、押しは強いし自信満々だし、ベルとは正反対です。でも…」 「でも?」 「二人揃ってちょうどいい感じじゃないでしょうか。ベルとフェルディナントさん、足して割って、ちょうど」 「…なるほど。そうかもしれないな」 フェルディナントは、晴れやかに笑った。 ちょうど塔を降りて大聖堂から戻ってきた彼らの担任教師は、 一連の出来事が丸く収まったのを見届けて、嬉しそうに微笑んだ。 だが――このあと、事態は急展開を迎える。 礼拝堂への襲撃を皮切りに、先生も、フェルディナントとベルナデッタも―― 徐々に激しさを増す戦いの渦に放り込まれる形になるのだが、それはまた別の話である。 そして『その後のフェルディナントとベルナデッタがどうなったか』も、 あるいは別の話となるのかもしれない。 |
|||||||||||||||||
| 【使用お題】 ①フェルディナントとベルナデッタで『足して割って、ちょうど』 ②フェルディナントで『手繰り寄せた糸の先』 ③ベルナデッタで『最後は私と』 お題提供:診断メーカー「140文字で書くお題ったー」 |
 |
 風待つ季節へ |
 アドラステアの、赤い薔薇へ |
 小説ページへ |
 サイトトップへ |