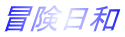
| アドラステアの、赤い薔薇 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝国歴1185年、孤月の節。 このフォドラで戦争が始まってから、丸五年が経とうとしていた。 新皇帝エーデルガルト率いるアドラステア帝国が、セイロス聖教会に対し宣戦布告をしたのが―― ちょうど今と同じ、春の気配が濃くなる時季だった。 土が水を含んでふかふかと軟らかくなり、木々が芽吹いて花を咲かせる準備をする時。 しかし本来なら生きる喜びを謳うはずのこの季節に、命はまるで怯えたように気配を潜めている。 大地が踏み荒らされて埃が舞い、瑞々しい草木の匂いを戦火の煙が消してしまっていた。 「エーデルちゃん…」 ドロテアは呟いた。五年前の孤月の節、一緒に士官学校を卒業するはずだった級友の名を。 美しく透き通る水晶のような髪と、アイリスの瞳をした皇女――いや、皇帝の名を。 エーデルガルトが何を思って反旗を翻したのか、ドロテアにはわからない。 共に師を慕って学級を転属した、カスパルやベルナデッタに訊いてみても同じ。 答えに辿りつくことはできず、彼らも首を傾げるばかりだった。 そしてドロテアは今、このミルディン大橋に居た。 どういう運命の悪戯か――帝国の敵、レスター諸侯同盟軍のメンバーとして。 自分の選択を後悔するつもりはない。 けれど、現に戦場で顔見知りに会うかもしれないと思うと、気が重かった。どうか、会いませんように―― しかしドロテアは、自身の願いがあっさり天上の女神に捨て去られたと知る。 聞き覚えのある快活な声。 探してはだめ、という自分の内なる声を振り切って…思わず敵軍の方に向けた視線が、 見覚えのある姿を探し当てた。歌劇の中から抜け出てきたかのような白馬の騎士。 ドロテアは、我知らず目を見開く。――五年ぶりの再会だったが、見間違いようがない。 故郷アドラステア帝国の――宰相エーギル公爵家の子息、フェルディナント。 柔らかそうに波打った髪が輝いた。洒落たつもりなのか…長く伸ばした金茶色の髪は、 光を透かすと温かみのある橙色に見えた。 (なんで居るのよ) 大嫌いな貴族の筆頭。できることなら一番、会いたくなかったのに。 そんな気持ちとは裏腹に、ドロテアは元・金鹿学級の仲間たちが開いてくれた血路をひた走っていた。 気づくと仲間の後ろから、自軍を率いフェルディナントの前に進み出ている。 「……!」 ハッと彼が息を呑んだことを気にも留めないふりをして、ドロテアは言った。 「あら、フェルくん」 自分でも驚くほど冷静な声で、彼に呼びかけていた。これは劇よ、と、彼女は自分に言い聞かせる。 …大丈夫、上出来だ。 何しろ、ドロテアは帝国のミッテルフランク歌劇団が誇る歌姫。 士官学校入学のため一時退団していたにせよ、今も演技力は落ちていない。 悟られてはいけない。今のこの気持ちを。 「エーデルちゃんにずっと対抗心を抱いてたのに……!結局、付き従ってるのね。 それも貴族の務めかしら?」 ドロテアは、わざと侮蔑を露わにした。 その態度で、言葉で――昔と変わらず批難し頑なに拒絶するドロテアに、 フェルディナントは悲しげな目をして答えた。 「君にはわからないさ。私やエーデルガルトが背負っているものは」 押し殺した声で紡いだ言葉の先、意志の光が瞳に宿る。 「本当はわかってほしかったが……今更かける言葉はない!」 槍を構えて、騎馬と共に突進せんとしたフェルディナント。 咄嗟にドロテアを庇おうと出たのは、彼と同じく馬に跨がったローレンツだ。 …が、両者が槍を交える前に、決着はついた。 (――トロン!) すらりと伸ばしたドロテアの手から、魔道による電撃が放たれる。 その輝きは一瞬で宙を奔り、一直線にフェルディナントを貫いた。
背後に足音と共に人の気配を感じ、ドロテアは顔を上げた。 同志の墓に供えるため摘んだ白いカーネーションを、両手に抱き締める。 現在レスター諸侯同盟軍が拠点にしている――ここ、ガルグ=マク大修道院には、温室があった。 カーネーションの開花時期は本当ならもう少し先だが、ここで栽培されたものは開花が早い。 ドロテアはゆっくりと振り返る。 「…先生」 つい士官学校生時代と同じく、そう呼びかけてしまうのだった。 セイロス聖教会の大司教が教師に大抜擢して目を掛けていたこの青年は、 五年前の混乱の折に行方不明になっていた。 が、ある日、五年前と全く変わらぬ姿で元・金鹿学級の教え子たちの前に現れた。 昔、大司教に聞いたところによれば――「神祖である女神の力を授かった」ということだったから (それに伴い、五年前のある日に突然目や髪の色が変わってしまった)、不思議と頷けてしまう部分もある。 本当に、出自から経歴から――どこを取っても不思議な青年だった。 ドロテアは、そんな元・担任教師を目の前に、少し怯むのを自覚した。 ともすれば人外を思わせる容姿に…ではなく、昔と全く変わらぬ物腰と態度に、である。 見つめてくる碧玉さながらの瞳は、ドロテアの心の中にある汚いものを見透かすよう。 …この人には、敵わない。 ドロテアは、いつものように言葉でやり込める元気も無く、言った。 「ミルディン大橋、五年前に見た時よりも、遙かに軍備も充実してましたね……。 兵もあんなにたくさん詰めてて……」 そして、みんな死んでいった、と、ドロテアは噛みしめるように呟く。 まるで物語の響きだ――しかし、言葉にした途端に真実は重みを増して、たちまちズンと胸に落ちかかる。 元担任は、教え子の言葉の続きを静かに待つのだった。 優しく促されているようなその視線に、ドロテアはつい言葉を重ねた。 「それに…私たちはフェルくんも殺したわ」 五年前は何を言ってもほとんど無表情だった青年の顔が、ふと痛みを堪えた――のが、 ドロテアにも、今ならば分かる。 「昔は同じ仲間、級友だったのに……」 ……これは罪を背負う決意か、それとも後悔か。 自分でも分からない。これが歌劇だったら、登場人物が持つ答えがあるのに。 自分で自分の気持ちが分からないのだから、これを聞いた先生にだってうまく伝わらないのは当然だった。 案の定、元担任の――先生は、首を傾げた。 そして彼は、ドロテアが取り落とした白いカーネーションを数本、拾った。 残りを拾って抱えなおしたドロテアに、先生の静かな声が降る。 「行こう」 ガルグ=マク修道院の敷地に急遽掘られた戦没者の墓に、二人は赴いた。 献花したカーネーションは、黒く真新しい墓石に白く広がった。 ミルディン大橋で散った多くの仲間が、ここに眠っていた。
ミルディン大橋の戦いを制した同盟軍の噂を聞きつけ、拠点のガルグ=マク大修道院には 人が戻りつつあった。騎士や従士、修道士に商人… 大修道院の膝元にある町は、にわかに活気づいている。 市場にも人が増え、賑やかさを取り戻していた。 「アンナさん」 「あら! ローレンツ君。頼まれてたもの、入ったわよ」 「すまないね」 ローレンツは箱の中に入った品物を入念に確認すると、代金を支払う。 紙幣の枚数が明らかに多いのを見てアンナが釣り銭を出そうとしたが、 ローレンツはそれを手振りで止めた。 「これは危険手当も込みの代金だ。とっておきたまえ」 「それじゃ、遠慮無く…と言いたいところだけど。返すわ」 「しかし、この戦時下で商売も大変だろう? 労働には、相応の対価を払わなくては」 「気持ちは、ありがとう。でも実際、この戦時下とはいえ、貰いすぎね。じゃあ、 そうね…これくらいが妥当かしら」 アンナは改めて値段を提示した。当初の金額の二割増しだ。 「商人には商人の、流儀とプライドがあるの」 「わかったよ」ローレンツは頷いた。「だが、端数は切り上げでいい。…これで」 「毎度あり♪」 交渉成立だ。代金を受け取り、にっこりと笑ったアンナに、ローレンツも笑顔を返す。 彼は軽く手を振って、大修道院に戻った。 そのまま温室に向かう。すると…遠目に、自分と入れ違いで出ていく先生とドロテアを目撃した。 手にしているのは白いカーネーションだ。 弔いの花だ、と、ローレンツは瞬時に察する。…近づかずに見送った。 いつもは強い輝きを湛えたドロテアの緑の瞳が、今日は翳りを帯びていた。 無理もあるまい。彼女は、戦場で再会した友を、直接手に掛けたばかりなのだ。 (フェルディナント君……) 皆が頭では理解していながら怖れていたことが、現実になってしまった。 これが戦争だ。 たとえ唯一無二の友と対面しようと、目の前に敵として立ちはだかる以上は受けて立たなければならない。 そして勝たねば、信念が砕かれることになる。お互いに譲れぬものがあるのだ…だから戦う。 今思えば、ローレンツたちが士官学校に入学した、あの年。 異例の抜擢で担任教師となった先生が傭兵上がりだったからなのか――金鹿学級の課題は、 他と比べると特殊なものが多かった。 揉め事の解決に、盗賊の征伐。――魔獣退治などは、気づけば何度も経験済みだ。 その経験が、今こうして帝国との戦争の役に立っている。皮肉なものだ。 ましてや、学友同士で命のやりとりをするなど。 だが、国を思えば当然だ。ローレンツは由緒正しい貴族だ。名門グロスタール家の跡継ぎ。 当主である父の名を汚さぬよう、常に家の利を考え、 清く正しく――ローレンツは生きてきたと、自負している。 貴族とは、上に立つ者だ。そして、迷える民を導き、民の安寧のために尽力する。 こんなことを声に出して言うとまた「その貴族が戦争をして、平民を巻き込んでいるのに?」と 誰かから揶揄されそうだが、今は同盟の未来のため、戦う他ない――そう、ローレンツは判断した。 『目の前の些事より、大局を見据える目を養え』…とは、父の教えだ。 グロスタール家は親帝国派ではあるが、 それも帝国の介入を最小限に留め波風を立てないためだと、ローレンツ自身、理解している。 帝国に強く出られれば、抗するだけの国力を同盟は持たなかった。 級友リシテアと、彼女の家――コーデリア家が受けてきたという仕打ちが、何よりの証拠だ。 苛烈で犠牲を厭わない帝国のやり方は、ローレンツの考える『正しき貴族』からは外れた行いに見えた。 『強くある』ことは美徳だが、犠牲を顧みないやり方は美しくない。なにより、死人が出すぎる。 『策士』と言われる盟主クロードのやり方も、 ローレンツにしてみれば無茶苦茶で…綱渡りもいいところだが、 エーデルガルトに比べれば民への被害が少ない。 認めるのは癪だが、事実は事実。此度のミルディン大橋の戦いが、それを証明した。 ローレンツは思った――今回ばかりは、父の意向に背きクロードの作戦に乗って正解だった、と。 ローレンツの父は、クロードに不信感を募らせている。ローレンツも、かつては同じだった。 しかし現在は、複雑な心境でありながらもクロードを認める自分が居た。 断絶の危機にあったはずのリーガン家に、突如現れた嫡子――出自も人柄も胡散臭すぎて 信用ならなかったクロードだが、共に過ごすうちに見えてきたものがある。 それに、個人的な感情に囚われていては決して見えないものもある。 覚悟はとうにしていた。ローレンツは先頭に立って戦うのだ。 誇り高き貴族として、同盟の――いや、同盟だけでなく、フォドラ全土の民と、未来を守るために。 (だが、彼女は?) ドロテアは、どうだろうか? 彼女は、平民の出とはいえ優秀だった。心身も強い。祖国を敵に回すことになるというのに、 この軍に入るため馳せ参じるくらいだ。 『平民出の孤児でありながら、高貴な薔薇のように咲き誇る歌姫』――いつだったか、 今は亡き親友フェルディナントが言っていたのを思い出す。 言い得て妙だと頷いたが、ローレンツは内心、懐疑的だった。 平民は平民だ。生まれながらに「上に立つ者」「導く者」としての教育を受けてきた貴族とは違う。 貴族ならば「国」や「世界」を広く見据える目も養えようが、平民は目の前の暮らしを見つめるので精一杯だ。 そんな平民に、貴族と同等の重責を負わせるわけにはいかない。そもそも、立場が違うのだから。 現に、ドロテアは、ローレンツと同じ視点で物事を見ることができない。 揺らいでいるように見えた。…フェルディナントを手に掛けてしまったことで。 「………」 辛いだろう。 こうなることは分かっていた。だから、彼女がフェルディナントと戦場で顔を合わせぬよう―― 手を下さずに済むよう、細心の注意を払って立ち回っていたのに。 「…本当に、皮肉なものだな…」 ローレンツは、小さく溜め息を落とした。 アドラステア帝国の宣戦布告直後、フェルディナントと交わした最後の会話を思い出していた。 ――『本当に行くのか? 君がここに残ってくれたら、こんなに心強いことはないと思っていたのだが』 ――『ああ…戻るよ。私は、祖国で何が起こっているのかを、この目で確かめたい。 エーデルガルトに会って、直接問いたい。その上で、もし私の信ずる正義と道を違えるのなら… 彼女に進言できるのは、この私しか居まい』 ――『そうか…。そうだな』 ――『私は、自らが正しいと思うことを実行するよ。次に会う時は敵同士かもしれない…。ローレンツ、元気で』 ――『ああ。もし、互いの道が交わることがあれば――また会おう』 「………」 ローレンツは、胸の前の箱を大切に抱え直し、持っていった。温室の管理係に預ける。それは、 敵国アドラステアの赤い薔薇――親友フェルディナントの故郷にも咲くという、大輪の薔薇の新苗だった。 高い山の上にある大修道院だが、ここならば苗が寒さで駄目になることはあるまい。 季節は春――大樹の節。日中は暖かくなってきたが、山肌を吹き下ろす風は、まだ冷たかった。
ドロテアは墓参りを終えて戻ってくると、なんとなく寮棟の二階に上がった。 自身の部屋は一階にある。 二階は、士官学校時代から貴族に連なる生徒が使っていたから、そんな生徒に お茶会に招待された時以外、好き好んで上がったことは無かったのだが。 「………」 久々に足を踏み入れた廊下はガランとして、うら寂しい感じがした。 ドロテアは、ゆっくりと廊下を突き当たりに向かって歩いた。…と、 空いていると思っていた一室に、見知った後ろ姿を発見する。 「おや、ドロテアさん」…ローレンツだ。 ドロテアは微笑んだ。 知り合ったばかりの時こそ『鼻持ちならない貴族の典型』のような気がして嫌いだった彼は、 話してみると予想外に真摯で誠実だった。 かっちり固まった彼の価値観については、個人的に疑問を呈したい部分もあるが、 仲間としては信頼できるし、気も許せる。 …ドロテアは訊いた。 「ローレンツくん。貴方の部屋、ここだったかしら?」 「いや、僕の部屋はこの隣だよ。昔はよくここに来て、語り合ったものだけどね」 …誰と、とは訊くまでもなかった。 机に残った槌の跡。 ローレンツが見ていた窓辺の棚の片隅には、置き忘れられて ずっとそのままになっていた空の油入れ。 「彼は、武具の蒐集が趣味だったからな。自慢の逸品を見せてもらったこともある」 「フェルくんの、部屋だったのね…?」 「ああ」ローレンツは、頷いた。「懐かしいよ。まるで昨日の事のように思い出せる」 窓から見える空を見つめて追憶の向こうに思いを馳せた彼は、少し困ったような笑みを浮かべる。 ドロテアも苦笑した。 「ええ…本当ね」 あの時は、こんな未来など知る由も無かった。 …まさか、戦場でフェルディナントをこの手に掛けるなど―― ドロテアは安堵している自分に気づいた。 ローレンツが、この自分ですら量りかねている心の内を察し、よく理解してくれていると思ったのだ。 振り返れば、彼とは身分は違えど通じ合う部分がある…そんな気は、昔からしていた。 ローレンツが、自分と同じように『心から想い合える伴侶』を探していると知った時から。 しかし、 「ドロテアさん」 次に出てきた言葉に、ドロテアは凍りついた。 「君は、これ以上戦場に立たなくていい。もう止めたまえ」 「な…なにを言ってるの?そんなわけにはいかないでしょう。 私だって同盟軍の一翼を担う将なのよ?先生は頼りにしてくれているし、クロードくんにだって…!」 「なればこそ、だ。今の君では、戦場に出ても危険が及ぶだけ…皆の士気も下がる」 「………」 それは、言われずとも重々承知していたことだった。…だから、気持ちを鎮め、立て直そうと 努めていたというのに。 「辞めろ、ですって?」 言葉にした途端、哀しみが、悔しさが、怒りが、次々と湧いてくる。 だが、ドロテアの口調はまだ静かだった。…否、冷ややか、と言った方が正しいだろう。 「貴方、何の権限があって私にそんなこと言うの?」 「権限がどうという話ではないよ。僕はただ、事実を述べたまでだ」 分かっている。だが、辞めたらここには居られなくなる。衣食住の保証が無くなる―― 帝都の裏通りで物乞いをしていた、少女の頃の記憶が甦った。 ぼろを纏ったドロテアに哀れみの目をむける『高貴な』人々。侮蔑と嘲笑――そして、 噴水で水浴びしながら歌っていたドロテアを睨んで去っていった、あの日の少年の瞳。 自分のしたことは棚に上げ、さも自分が正しいという態度で、己に都合の良い正義を説く貴族たち。 平民を道具としか思わず、平民から搾取するだけ搾取して、必要がなくなればあっさり捨てる…… 「そう…貴方も、私からこの居場所を奪うの?」 いつしか開き掛けていた心の扉は固く閉じ、凍った扉のその奥で、火が付いた。 「『貴族だから当然だ』って? 『皆を危険に晒すくらいなら、役に立たない駒は率先して捨てる』と? いくら貴族だからって、私の身の振り方を勝手に決めていい根拠にはならないわ」 ドロテアは、泣き出しそうになる自分を押し殺した。 …同じだ。五年前、学級を移ると決めた時と。 「私は、自分の意志でこの軍に参加して、ここに居るのよ。あなたが、勝手に決めないで!!」 「そんなことを言っているんじゃない。僕は、仲間として君を心配して…」 ――『私は、君のことを心配して言っているのだよ』 いちいち重なる。つい先日討ち果たしたフェルディナントと。 「無理をするな。君自身、戦える状態じゃないことは分かっているだろう?」 ――『無理をすることはない。君の気持ちは、君自身が一番よく分かっているだろう?』 ローレンツは、フェルディナントとよく似ている。 物言いが、価値観が、言葉までもが。 優しく諭すようでいて、ドロテアには鋭く――時に、とても痛い。 「仲間…? 言葉って便利ね」 ドロテアは笑った。先ほどとは違う、渇いた笑いだ。 彼女は、つい荒くなってしまった語気を落ち着けた。 二、三回呼吸をすると、この身を焼く感情の炎が鎮まり、冷えていく。 「フェルくんのことなら、今更なんとも思ってないわ。 心配しなくても、次の戦闘まで引きずったりしないから大丈夫よ」 ドロテアはふわりと踵を返した。…すると。 「そいつは助かる」 飄々とした声と共に、若き盟主が戸口に立っている。 「クロードくん」 「クロード!」 笑顔で、じっとこちらを見ていた。 クロードは扉の枠に片手を添え、自身の体でドロテアの退路をさりげなく塞いだ。 「何しろ、同盟軍は寄せ集めの上に人手不足でね…ドロテア。お前にも、 抜けられたらどうしようかと気が気じゃなかったのさ」 「じゃあ、次も…」 「ああ、よろしく頼むよ。実はもう、きっちり布陣に組み込んであるんだ」 「ふふっ…頑張るわ。任せておいて」ドロテアは、思わず濡らした目元をさりげなく拭った。 「話し込んでて、ごめんなさいね。クロードくん、ローレンツくんに何か用事があったんじゃないの?」 と、ローレンツの方は振り返らず、クロードに尋ねる。 邪魔をしては悪いから、と理由をつけて退散するつもりだったが、クロードは通してくれなかった。 相変わらずの笑顔で、「ドロテアに用があったんだ」と言う。 「まあ…私に? 何かしら。今晩のデートのお誘いなら、嬉しいわね」 「さすがは歌姫、絶妙な返し。…ゴホン。ドロテア姫。 今宵、このわたくしのために歌ってはくださらないでしょうか?」 芝居がかったクロードの言葉と身振りに、ローレンツがイラついて溜め息を漏らした。 ドロテアが吹き出すと、クロードは通常の話し方に戻り、こう言う。 「今夜、宴をしようと思ってね」 「な…宴だと!? 寝言は寝てからにしろ、クロード!」 クロードは、ローレンツの異論は無視した。そのまま、どちらにともなく話しかける。 「俺たちは、ついにミルディン大橋を落とした! その祝勝会だ。 それと、今後の戦勝祈願のために…是非とも宴の席に、お前の歌で華を添えてくれないか?」 「! こ…今夜?」 随分と突然の依頼だ。しかし、クロードはにっ、と笑った。「ああ、今夜だ」 「…いいわ」 「ドロテアさん!」 慌てるローレンツには目もくれず、ドロテアは二つ返事で承諾した。 帝都の歌劇団に居た頃、全く同じ台詞で言い寄ってきた男が居たものだ。 不埒な欲求を丸出しにしたそいつも、貴族だった。 が、クロードは違う。 盟主という地位に在りながら、どこかあけすけで型破りな――明るさと朗らかさには、好感が持てた。 今までドロテアが見てきた、どの貴族とも違う。 学生時代、転属したばかりの時こそ馴染めていない気がして悩んだものだが、 今となっては、金鹿学級に――ひいては、この同盟軍に入って良かったと思った。 この盟主に――そして、あの先生に付いてきて、本当に良かった、と。 クロードは言った。 「選曲は任せる。歌いたいものを、思いっきり歌ってくれ。 まあ…聞いてるみんなの士気が上がるような歌だと嬉しいが」 「わかったわ」 ドロテアは頷いた。 用が済むと、クロードは扉の前から退いてドロテアを出してくれる。 「頼んだぜ」 ひらひらと手を振って歌姫を送り出したクロードに、ローレンツは、どこか恨みがましい目を向けた。 「そっとしておけと言っただろう!」 「そっとしておいたら、何も変わらなかったかもな。気を遣うだけ、無駄なこともある。 正論で説得しても、反発されて終わりだ」 「くっ…」 ローレンツは歯噛みする。…心を尽くした言葉で正しいことを説いているのに、 どうして自分の言葉は届かないのだろう? みんな、クロードの言葉には、すんなり頷くくせに。 プライドをちくちくと刺激され、こめかみに指を当てて唸るローレンツに、 クロードは言った。開いた扉の向こうを見つめて。 「ああいう奴は、同情や憐憫よりも『仕事』を貰った方が奮い立つのさ。プロの意地ってやつだ」
「マヌエラ先輩、居ます?」 ドロテアが医務室を覗くと、旧知の女医が振り向いた。 「あら、ドロテア。どうしたの? どこか具合でも悪いの?」 泣きぼくろのある顔が、気遣わしげな表情になる。 この人もまた、士官学校時代の恩師である。 ドロテアが金鹿学級に転属する前に居た黒鷲学級の担任で、医師も兼ねていた。 マヌエラは、戦争がいよいよ激化すると祖国を離れ、騎士団と共に 行方不明の大司教の捜索をしていたらしい。 士官学校はセイロス教の名の下に設立されたものであり、彼女はそこに属していたからだ。 「いいえ、その…先輩、楽譜を何冊か持ってましたよね?見せていただきたくて」 つい「先生」でなく「先輩」と呼んでしまうのは、歌劇団に所属していた頃の名残だ。 マヌエラは、歌劇団でドロテアの前に歌姫を務めていた。 孤児だったドロテアに才能を見いだし、歌劇団に誘って、帝都の裏通りから連れ出してくれた。 彼女が現れなかったら、今の自分は居ない。 ドロテアにとって、マヌエラは恩師であると同時に――人生の大恩人なのである。 士官学校に入学後、学級担任だと分かった時にはどれだけ喜んだか。 「楽譜? 歌いたくなったのね。気晴らしなら、あたくしも後で付き合うけれど」 今日の医務室、ベッドは珍しく空だ。しかし、このところ戦続きで負傷者も多かったからか―― それとも先日のミルディン大橋の一件を小耳に挟んだからなのか、 マヌエラは余計に心配してくれているらしかった。 ドロテアは笑った。 「いいえ、仕事です。クロードくんから頼まれたんですよ。今夜の祝勝会で歌ってくれって」 「まあ」 マヌエラは、驚いて目をぱちぱちさせた。 「それで、何かいい曲が無いかと思って。私が今持ってるのは、帝国で流行っていたものばかりだから。 それだと、ちょっと都合が悪いでしょ?」 「そう…」 悪戯っぽく笑うドロテアに、マヌエラは切なそうに頷いた。 「楽譜ならその棚に入ってるから、好きに持っていってくれて構わないわ。 …でも、その前に少し、休んだら?」 「えっ?」 「あなた、顔色があまり良くないわ。…眠れていないんじゃなくて?」 それは図星だった。…マヌエラは、男運は無いが、人を見る目はある。 そして、さすがは医師というべきか…こういう観察眼はさすがと言える。 彼女は言った。 「ね、ここのベッドを使って、小一時間でいいからお休みなさいな。 アドラステアの歌姫が、そんな顔色で歌うなんていけないわ。 舞台には、いつも最高のコンディションで上がらなくては…お客さまに失礼よ」 歌劇団時代、厳しくも優しく指導してくれた、憧れの先輩の言葉。 「……。その通りです。先輩には敵いませんね」 ドロテアは苦笑し、素直に救護ベッドに横になった。 マヌエラが、頭を優しく撫でてくれる。昔、熱を出した時のように。 「ほんとうに…あなたはいつも独りで……もう少し誰かを頼ってもいいのに……」 昔と同じく独りごちたマヌエラの声を聞き、ドロテアはそっと返す。 「この戦争が終わったら、誰かいい人を見つけて頼りますよ。 だから先輩も、生きて幸せになってくださいよ?」 「あら。いつの間にやら言うようになったわね」 おとなしく寝なさい、と、マヌエラはドロテアのおでこを小突く。 その仕草には、疑いようもない愛情が滲んでいた。 …マヌエラの側では、素の自分で居られた。 ――この人は、自分に対して嘘偽りなく親愛の情を向けてくれていると分かるから、とても安心する。 「じゃあ、あたくしはちょっと出てくるわね。鍵を掛けておくから、安心してお休みなさい。 …あまり無理をしてはだめよ?」 はい、と返事をして、布団から出した手を引っ込める。 扉に鍵が掛かる音を聞き届けたドロテアは、ふう、と息をついて医務室の天井を見つめた。 多少の無理は仕方ない。無理だと思って諦めていたら、明るい未来は拓けない。 昔から、そう思って生きてきた。…だから今があるのだ。 ここでは表立ってあまり口に出来ないが、 ドロテアはセイロス教の女神の存在をあまり信じることが出来ない。 子供の頃は、不平等な世の中を作った女神を恨みもした。 貴族と平民――貧しかった母は、ドロテアが物心つく前に病死した。 母が、とある貴族付きの侍女だったと分かったのは、確か歌劇団に入団してからだ。 噂と真実が玉石混淆する帝都の芸能界で、母と自分を捨てたらしい男の存在を知った。 その後、父かもしれない男と再会した。その男が言ったのだ。 「手を出した侍女に子供を産ませたが、その子が紋章持ちではなかったから、母娘まとめて捨てた」ことを。 その男がドロテアの素性を知らずに口説いてきた時には、憎さを通り越して唖然としたものだ。 ドロテアを崇め寄ってくる男は、だいたいがこんな感じの貴族で、 ドロテアに言わせれば『うわべばかり飾って繕ったごみ屑』だった。 貴族の多くは、その血に女神の祝福である『紋章』を宿している。 それゆえ魔道をはじめとする特別な才能に恵まれ、世間的に特権を持ってこのフォドラを支配する。 『紋章持ち=優れている』という常識が、今の不平等な世界を作り上げていた。 権力を振りかざし、当たり前のように『自分は優れているのだ』と胸を張る貴族が、 ドロテアは大嫌いだった。美貌やら歌声やら――自分の表面ばかり見て寄ってくる貴族が。 (本当の姿を知ったら、汚らわしいものを見る目をして捨てるくせに…) だったらせいぜい、この人生で綺麗な歌姫を演じきってやろうと思った。 いけすかない連中をやりこめて、陰で笑ってやるんだ、と。だが…。 ――『無理をするな』 ドロテアは、はっとした。
「…。ちょっと、ローレンツ!焦げてるよ!」 食堂に併設された厨房で、ローレンツは我に返った。慌てて鉄のフライパンを火から外す。 「すまない、レオニーさん。ちょっと考え事をしていてね」 「…まったく。この食糧だって、あんたの親父さんが融通してくれた物資の一部なんだろ? 無駄になんかしてみろ、申し訳ない上にもったいない」 レオニーは、ローレンツの父が治めるグロスタール領内の小さな村の出身だ。 彼女も、もともと士官学校の生徒で、ローレンツの級友だった。 聞けば、入学に必要な教会への寄進や学費は、村全体で工面してくれたのだという。だが それはつまるところ借金で、彼女は今もその返済をしている。そんなわけで苦学生だった彼女は、 昔も今も、大変な倹約家だった。 グロスタール家の潤沢な財を後ろ盾に持つローレンツとは、生まれも育ちも全く違う。 学生時代こそ、貴族の自分が彼女のような平民と一緒に雑用をこなすことに 疑問を抱いていたローレンツだが――長く学校生活を共にするうちに、少しずつ考えが変わってきた。 彼女は友であり、今この同盟軍においては、対等な仲間なのだ。 また戦時下というこの非常時、助け合わねば生きてゆけぬ。 馬の世話も食事の支度も、身分に関係なく請け負うのが筋であろう。 「まーた貴族の責務がどうとか? それとも、さっきの軍議のことか?」 レオニーは、鍋の具合を見ながら言った。煮えやすい葉物野菜を、手早く刻んで鍋に足す。 「……」 ローレンツは無言の肯定を示した。認めたくはないが、どちらも正解だ。 クロードは今節末に帝国領への本格的な進軍を決めた。 自分たちが次に帝国軍と激突するとしたら、それはグロンダーズ平原だ。 学生時代に一番大規模な催しとして行われた模擬戦――懐かしき『鷲獅子戦』の舞台である。 旧王国軍と思しき軍勢も帝国領に入ったという。 おそらく次は、この前よりも大きな戦闘になる――そして、 士官学校時代の学友と戦う可能性は、もっと高くなる。 「戦火は、また広がるのだろうな…罪の無い平民が、大勢巻き添えを食う」 グロンダーズ平原は、肥沃な穀倉地帯だ。 『鷲獅子戦』で訪れた時は、見渡す限りの麦畑に素晴らしい実りがあった。 そろそろ種蒔きも始まる頃だろうか…もし、あの畑が全て燃えるようなことがあったら、 翌年の困窮は目に見えている。 「それを最小限に止めるのが、わたしたちの仕事だろ?」 レオニーは、先の戦闘で大勢死人が出たことに対して「まだ慣れない」と表情を曇らせていた。が、 今の彼女には迷いが見えない。 「君は強いな」 「そうかな」 「辛くはないか?とうとう僕たちは、昔の仲間まで相手にせねばならなくなったんだ」 「そりゃ辛いよ。でも、覚悟決めたんだ。みんなだって同じだろ?」 「ああ、そうだな」 「あの先生に、わたしも負けてらんないしね!」 女神の加護を受けたという不思議な青年教師を、レオニーは未だにライバル視する傾向がある。 彼が、レオニーが『師匠』と呼び慕っていた男の息子だからだ。 一方でレオニーだけが、父親を亡くした彼――先生の哀しみを、誰よりも 一番近くで共有しているように見えた。 凄腕の傭兵だった男の、息子と弟子。 二人が折に触れて響き合うのは、ある意味自然なことなのかもしれない。 「…君たちが少し羨ましいよ」 ぽつりと呟いたローレンツに、 「は? 」レオニーはきょとんと目を見張り、首を傾げた。 「どうした今日は?やっぱりなんか変だよ。他人のことより、ローレンツ。あんたは大丈夫なのか?」 「?ははは。心配ありがとう、レオニーさん。だが大丈夫さ。そこは僕だからね!」 「あー…はいはい。愚問だったよ」 いつも通り自信たっぷりに言い切ったローレンツに対し、レオニーはやれやれと肩を竦めた。 「貴族たるもの、ここで挫けているわけにはいかないのだよ」 ローレンツは焦がしてしまった肉を、他とは別に取り分けた。…これは自分の分。 自分の失敗は、自分で引き受けるのが当然だろう。 ところがレオニーは、ローレンツが焦がした肉を細かく刻んだ。 そのまま、揚げた玉ねぎのスライスと共に、さっさとサラダにトッピングしてしまう。 唖然としたローレンツに、レオニーは問うた。 「そうなのか?」 「うん? ああ、そうだ。僕が理想とする貴族は、決して挫けたりしない」 言い切ったローレンツだが、レオニーはなおも首を傾げる。 「貴族だから、挫けてるわけにはいかないのか? 平民だったら挫けても許されるのか? 挫けたり、悲しいのは…貴族も平民も一緒だと思うけどな」 思わずはっとしたローレンツの前で、考え考え、彼女は言った。そして、 「腹が減るのも、できるだけ美味いものが食いたいのも、おんなじだ。だろ?」と、振り返る。 「待ってくれ。なんの話をしているんだ、レオニーさん」 ローレンツは困惑した。だが、レオニーは悪びれもせずに続ける。 「『理想の貴族』か…相変わらずブレないねぇ。あんたのそういうところ、わたしは嫌いじゃないよ。 でも、平民だから、貴族だからって決めつけないでほしい。この前も、そう言っただろ?」 「ああ…」 ローレンツは思い出した。確かに、そんな話をしたことを。 「職業に貴賎なし。料理にも貴賤なし!ってね。…はい、これ。持っていってよ」 鍋から煮上がった女王魚を取りだして豪快に盛り付けたレオニーは、その大皿をローレンツに手渡した。 香辛料は使っていないが臭みは消えていて、いかにも美味しそうな良い匂いが立ち上る。 空腹が鳴ってしまって、ローレンツは顔を赤くした。 「…失礼」
その晩、ガルグ=マク大修道院の食堂で、 元・金鹿学級のメンバーが中心になって企画した宴が始まった。 基本的に自由参加、入退場も自由だ。 同盟軍の同志をはじめ、セイロス聖教会に属する人々… そして、大修道院の地下『アビス』に暮らす訳ありの人々までも、続々と集まってきていた。 「はいはーい、皆さーん!お静かにぃ」 飲み物入りのグラスやゴブレットが全員に行き渡ったのを確認すると、 ローレンツの隣に座ったヒルダが溌剌とした声を掛ける。 ひょこんとストロベリーブロンドの結い髪を揺らした。 「それじゃ、我らが級長、クロード君!一言ご挨拶をお願いしまーす♪」 「堅苦しい挨拶は得意じゃないんだが…あー…オホン」 金鹿学級の元級長クロードは、わざとらしく咳払いをすると、居住まいを正すのだった。 話し声が静まる。 クロードは皆の視線を集めると、明るい笑顔を見せた。 「みんな、今回もよくやってくれた。 いろんな意味でやりにくい戦いだったと思うが、俺たちはミルディン大橋を制圧することができた」 ぱちぱちぱち、と拍手が起こる。 クロードは翠緑の瞳で、集まった仲間たちを見渡す。そこには、穏やかに微笑む恩師の青年も居た。 「この戦いを勝利で飾れたのは、みんなが頑張ってくれたおかげだ。 労いと感謝の気持ちを込めて、今日はこの通り…ささやかではあるが、宴うたげの席を用意した」 「用意したのも、わたしたち全員だけどねー」 レオニーが茶々を入れ、そこに笑いが起こる。同意の声や、空腹を訴える声も。 クロードは微笑み、盃を高く持ち上げた。 「次はいよいよ本格的に帝国領に進軍する。 今宵は存分に食って飲んで、歌い踊り笑ってくれ!乾杯!!」 乾杯の唱和があり、わいわいと賑やかな食事が始まった。 「よっしゃあ!肉食うぞ、肉!」 「オデも食うぞぉ!…ほら、ベルナデッタさんも食え!みんなで食う飯は最高だぞ!」 「ぴゃっ!? こ、こんなに食べられませ~ん!!」 ドロテアの斜め前で、カスパルがラファエルと早食い競争を始め、寮の部屋から ラファエルに無理矢理連れ出されたらしいベルナデッタが、目を白黒させて困っている。 「あーあ、また始まっちゃったぁ」 ヒルダが楽しそうにそれを眺め、隣でマリアンヌがサラダを慎ましく口に運ぶ。 「ほら、ベルナデッタ!この小皿を使いなよ」 見かねたレオニーが、テーブルの向かいから世話を焼く。イグナーツが笑った。 「ラファエル君もカスパル君も、相変わらず凄い勢いですねぇ。 …あっ、レオニーさん!このままじゃ、お肉ぜんぶ平らげられちゃいますよ!」 「…っ!こら、あんたたち! ちょっとは遠慮しろっての!!」 呆れ顔なのはリシテアだ。 「まったく、いつまで経ってもみんな子どもっぽいんですから」 ローレンツも同意した。一度ナイフとフォークを置くと、自前の白いナプキンで上品に口元を拭う。 「カスパル君、ラファエル君!少しは落ち着いて食べたまえ。…体に悪い」 彼は顔をしかめたが、以前は決まり文句だった「品性に欠ける」という非難を口にしない。 代わりに出てきたのは、相手を気遣う言葉だった。 ドロテアの隣で幸せそうに食事をしていたイングリットもまた (彼女もドロテアたちと同じ学級移動組だが、ファーガス神聖王国の出身だ)窘めた。 「二人とも、いい加減にしてください! 明日への貴重な糧なのです。もっと味わって食べようという気にはならないのですか?」 「まあまあ、せっかくの宴なんだからいいじゃないか。堅いことは言いっこなしさ」 「じ、ジュディットさん」 気づけば、その女傑っぷりで有名なダフネル家の当主までもが、 若者に混じって肩を組み、酒を飲んでいる。 パルミラ出身の、元は下働きの少年だったツィリルが、金鹿学級同窓生の輪の中に誘われて 困りながらもちょっと嬉しそうな顔をしている。 (なにこれ) ドロテアはふと我に返り、周りを見て、思わず瞬きを繰り返した。 気づけば座席の配置などもう関係なくなっていて、人々はお互いのテーブルを行ったり来たりしていた。 食堂に居る全員が、不思議と温かく明るい雰囲気で纏まっている。 年齢も性別も――趣向も得意なことも、出身地も身分も違う人々が、一緒になって 楽しそうに大騒ぎしているのだ。 ちらりと横目で見ると、その中心には二人の青年が居た。 元・金鹿学級の担任教師と、級長だったクロードである。 「……」 ドロテアは胸が熱くなるのを感じた。夢みたいな景色だ。 思えば、五年前の星辰の節――冬。 自分がどうしても学級を移りたいと希望したのは、ベルナデッタやカスパルの移動だけが理由じゃない。 先生とクロードが居たからだった。 あの二人と一緒に居れば、自分も変われるんじゃないかと思ったのだ。 フェルディナントへの嫌悪感も、マヌエラへの申し訳なさも、全部捨てて――ドロテアは 黒鷲学級を飛び出した。それで、やっと新しい自分になれる気がした。 ――温かな居場所。それをみんなと共に作り上げているクロードや先生には、 『常識』や『制限』の枠を感じなかった。 社会の縮図――がちがちの枠で括られた大修道院内に在りながら、 二人は伸びやかで自由に見えたのだ。 二人だけではない。いざドロテアが金鹿学級の中に入ってみると、 みんなの印象は外から見た時と違った。 吹けば飛ぶような言葉を並べて女性を口説くローレンツが意外と真面目だったり、 怠け者でちゃっかりしているように見えたヒルダは、思ったより気配り上手で面倒見がいい。 おどおどしている印象が強かったイグナーツは、こうと決めると強く、はっきり意見を述べる。 そして一見バラバラだが、彼らはお互いを尊重し合っているように見えた。 「懐かしいなぁ。…何だか、鷲獅子戦の後みたいですね」 しみじみ言ったイグナーツを、「おいっ」とレオニーが小声で制した。 「あっ、ごめんなさい…」 思わずシンと静まった宴うたげの場で、ドロテアは椅子から立ち上がった。 「クロードくん。それじゃ、そろそろ始めてもいいかしら?」 「ああ」 彼女は、椅子の背に畳んで掛けてあったショールを纏った。 普段使いのショールに急遽縫い付けたとっておきの輝石が、きらきらと光る。 お酒を勧められてもじっと我慢していたマヌエラが、いそいそとドロテアの元にやってきて並んだ。 「さあ、フォドラが誇る二大歌姫の共演だ。こんな豪華な演目はなかなか無いぞ。 とくとお聞きあれ!」 「クロード君、それじゃ旅芸人の一座みたいよー」と、ヒルダ。 再び笑い声が満たしたその場で、ドロテアは、マヌエラと共にもったいぶったお辞儀をした。 心得のあるものたちが楽器を持ち出して曲を奏で――歌が始まる。 アドラステア帝国の歌劇から引っ張ってきた曲以外に、 ファーガス神聖王国の祈りの歌や騎士物語を題材にした歌、 そして、レスター地方の村々でよく歌われているという民謡まで。 食堂に集まった人々は興味津々で聞き入り、あるいは一緒に歌った。 パルミラの舞踊曲が元だという民謡が流れはじめると、 ヒルダがイグナーツを、クロードがマリアンヌを連れ出して踊り始める。 手拍子と足拍子、口笛に笑い声。 気分が乗ってきたマヌエラが本領を発揮する。 ドロテアも負けじと歌声を響かせた。 やがて、拍手喝采。宴もたけなわ、そろそろお開きか、と誰もが思ったが……ドロテアは言った。 「最後にもう一曲だけ、聞いてください」 マヌエラは、そっとドロテアの背を押した。自身は受け取ったグラスワインで喉を湿し、ほっとひと息つく。 …目線の先で、ローレンツがうっとりとしてドロテアを見ていた。 が、曲が始まると同時に、マヌエラとローレンツは仰天した。 (えっ、これは…!?) (僕の詩だ!!) それは、ローレンツが誰にも内緒で書きためていた詩の一編だった。 いつぞや、ローレンツが落とした手帳をマヌエラが拾い見た。 怒ったローレンツだったが、作詞者を公にしないという条件で、マヌエラが曲を付けることを許可したのだ。 顔を真っ赤にローレンツが思わず睨むと、 マヌエラは顔の前で慌てて手をぶんぶん振り「あたくしが教えたんじゃないわよ」と口パクで訴えた。 ――まさか、ドロテアがあの楽譜を見つけて選び取るなんて…! 二人が慌てているなど露知らずドロテアは歌い続け、曲が終盤に差し掛かる。 彼女はマヌエラ以上に朗々と、情感たっぷりに歌い上げた。 『…♪ 誰にも気づかれぬ焦燥を 生ぬるい翠雨が冷ましてゆく この手で枷を外はずせぬ弱さに 失望で時が淀みゆく そして疼く思いを抱えたまま 角弓の風が夏の終わりを告げる …♪』 盛り上がっていた宴の場が、再び静まり返ってしまった。 ドロテアがミルディン大橋で旧友フェルディナントを討ったと知る者は、痛ましい目を向けた。 あるいは、帝国出身者の恨み言――同盟軍への当てつけか、と囁く者も居る。 それらを見聞きしたクロードは、歌い終わったドロテアの元に進み出て、こう尋ねた。 「短調、か。祝勝会を締めくくるにしては、意外な選曲だな。 随分と季節外れだし…孤独で、敗北感のある歌詞だ」 「ええ…今ここに居る大半の人が、そう感じたでしょうね」 ドロテアは、悲観とも諦観ともつかぬ寂しげな微笑みを浮かべ…しかし、クロードを真っ直ぐに見つめる。 「…でも、私は――この歌詞に、試練を乗り越えて進もうとする強さと前向きさを感じたの。だから歌った」 「なるほど」 「私は――私たちは、この先何があっても前に進まなきゃならないわ。 挫けそうになって、時に自分の弱さに嫌気が差すこともある…。けど、歩みを止めるわけにはいかない。 そうでしょう?」 困惑や憶測の声が一転、どよめきから歓声になる。そうだ、そうだ!と賛同があった。 「私も、みんなと前を向いて歩きたい。それを、この歌を歌うことで示したかったの」 「…そうか。ありがとう。その覚悟、確かに受け取った」 クロードは、ぽんとドロテアの肩に手を置いた。その手は力強く、温かだった。 「別に、お礼を言われるようなことじゃないわよ」 と、ドロテアは笑った。 一方ローレンツは、呆然とドロテアを見ていた。 ローレンツが書いた、あの詩。 それは、理想の貴族の姿を追い求め、より強く、より良く在ろうとする、自身の葛藤と決意だった。 高い理想を実現するには、相応の試練を乗り越える必要がある。 時に自分の不甲斐なさを知って悲観したくもなるが、それでも…諦めるわけにはいかないのだ。 詩に込めた決意と覚悟。そして、誰にも見せたくない弱さ。 ドロテアは、それらを全て汲み取っていたというのか。――言葉が出なかった。 ――その後、同盟軍は予定通り進軍した。 ついに帝都にまで手が届いた日、クロードが宣言した。 「この際だから、みんなに伝えておきたい。 俺は帝国を倒したあと、フォドラの中と外を分かつ高い壁を、ぶっ壊すつもりだ」 驚き戸惑う仲間たちに、彼は語る。 人も物も、自由に出入りさせて、外の世界への偏見を一掃したいのだと。 それは非現実的な『夢想』ではなく、実現可能な『理想』として皆の目の前に提示された。
帝都攻略は難しいと思われたが、戦が始まると決着は早かった。 市街地を制圧し宮城に攻め込んだ同盟軍が皇帝エーデルガルトを討ち取ると、 それまで敵対していた帝国貴族たちが降伏する。 あっという間に掌を返して、同盟軍にすり寄ってくるのだった。 「ったく、どいつもこいつも勝手だよな」 「そんなものよー。『勝てば官軍』とは良く言ったものよね」 レオニーとヒルダが話している。 ドロテアの隣では頬に軽く火傷したカスパルが、珍しく黙って立ち尽くしていた。 彼は、帝国の軍務卿の次男坊なのだ。 市街戦で大将を務めていた軍務卿が『帝国の全将兵の責を問わない』という約束の元に 自分の首を差し出したと聞いて、ドロテアは思わず涙ぐんでしまった。 ――それを悟られないよう、慌てて拭う。 「カスパル君、見せて」 言うが早いか、ドロテアは〈ライブ〉の白魔法でカスパルの火傷を癒やした。 「…っ。ああ…ありがとな」 「ううん」 二人して微笑んだが、哀しみを堪えたせいか、何かに困っているような笑顔になった。 ぱっと踵きびすを返すと、ドロテアは近くに居た他の仲間に向かって言った。 「あの。…私、ちょっと歌劇場の様子を見てくるわね」 この五年間で疎開した劇団員も居たが、帝都の歌劇場には、今もドロテアの顔なじみがたくさん居る。 別部隊のマヌエラが先に様子を見に行っているはずだが、 自分も劇団員の無事を確かめにいきたかった。 「待ってください。ひとりじゃ危ないですよ」 「そうだよ」 「僕が付き添おう」すっと進み出たのは、ローレンツだった。 「構わないね? ドロテアさん」 ドロテアは一瞬躊躇ったが、頷いた。 「ええ。お願いするわ」 ミッテルフランク歌劇団の劇場は、帝都アンヴァルの北西にあった。 駆けつけたドロテアを見て、劇団員たちが歓声を上げる。 先に来ていたマヌエラが、ドロテアを抱き締めた。 そうして、無事再会できた喜びを分かち合う。 ひとしきり涙の対面が済むと、ドロテアは連れのローレンツを紹介した。 劇団員たちは口々に礼を言った。 「私の仲間で、劇場に戦火が及ばないように尽力してくれた将の一人よ」と、 ドロテアが言い添えたからである。 しかし手放しで歓迎されているわけではないことは、皆の表情からも察しがついた。 帝国の人々にとって、ローレンツは敵軍の将なのである。 ドロテアやマヌエラのように、帝都にゆかりは無い。 見かねたマヌエラが、「ここは、あたくしに任せて。あなたたちはもう戻りなさい」と声を掛けてくれた。 その気遣いに感謝して、ローレンツはドロテアと共に歌劇場を出る。 戦場となった帝都の市街地からは、いくつもの煙が上がっていた。 あちこちに同盟軍の仲間たちが居るが、帝都に住む人間が出てくる気配は無い。 今は建物の中に閉じ籠もり、じっと成り行きを見守っているのが分かった。 かつての賑わいを思い出しながら、ドロテアは歌劇場の周辺を歩いた。 「離れていたのは六年くらいだけど…懐かしいわ」 「そうか。君は、この帝都の出身だったな。 実は僕も幼い頃、歌劇を見に何度か連れてきてもらった記憶がある。 …だが、意外と覚えていないものだな」 言葉通り、ローレンツの記憶の中にある帝都の街並みは、もう朧気だった。 「美しいよ」 ローレンツは、ふいに街並みを眺めていた藤色の瞳をドロテアに向け、呟く。 「あら、それは街のこと?それとも私のこと?」 ドロテアは言葉にちょっぴり棘を出したつもりだったのだが、 彼はそれを知ってか知らずか悠然と受け止めた。 「どちらも、だ」と、目を細める。 ドロテアは、視線をそらした。 「大通りに面した表側は、確かに綺麗なものよ。…だけど、裏通りは――どうかしらね。 貧しくて、その日その日を生きるので手一杯な人間が、たくさん居る……」 「ならば、早くこの戦争を終わらせて、僕たちの手で安心して暮らせる世の中を作らねばなるまいな」 ローレンツは、当たり前のように言った。 ドロテアはふと落ち着かなくなって、体の前で組んだ両手を動かす。 「ローレンツ君」と、話しかけた。 「この前はごめんなさい。私、勝手に誤解して、貴方に腹を立てていました」 「この前? …ああ、気にすることはない。だが、もし良ければ、腹を立てた理由を聞かせてくれるかな?」 「私、貴方に『役に立たないから出ていけ』って言われたんだと思って…」 「なんだと!? 僕がそんなことを言うわけがないじゃないか!」 ドロテアは頷いた。 「ええ…そうよね。貴方は、フェルくんのことで落ち込んでた私を心配してくれていただけ…… なのに私は、貴方が『貴族』だというだけで、また貴方のことを嫌いそうになったわ…。 貴方自身は、すごく真摯で優しい人なのに」 気づけば、マヌエラとローレンツがドロテアに投げかけてくれたのは、同じ言葉だった。 だが、敬愛するマヌエラ先輩と 貴族としての姿勢を貫くローレンツ―― ドロテアは、無意識に受け取り方を変えてしまったのだ。ローレンツが『貴族』だから。 「貴族だ、平民だ、って…勝手に枠を嵌めて決めつけていたのは、私の方。 色眼鏡で見て、貴方の本質を見ようとしなかったの」 謝罪しながら、ドロテアは思う。これでは私も、私の容姿や歌声ばかり褒めそやした貴族たちと ちっとも変わらない、と。 すると、ローレンツが言った。 「それは僕も同じだ。貴族と平民は『かくあるもの』と頭から決めて、例外は認めようともしなかった。 それに僕は、自分の信念を貫きたいがために、相手に対する配慮を欠いていた…… 高慢だったと思う。理想と正義を盾に…結果的に、浅はかな言動で君を傷つけてしまった」 すまない、と頭を下げられると、ドロテアは苦笑した。 「お互い様ってわけね。…じゃあ、私と仲直りしてくれる?」 「ああ、喜んで。元より、僕は君に対して怒っていたつもりはないが」 「…! ありがとう」 お互いに握手する。ミルディン大橋の戦い以来 落ち着いて話が出来ていなかったから、やっときちんと和解できた気がした。 そのまま再び歌劇場の前の道を歩き出した二人だったが、ふいにローレンツが足を止める。 「…おや? こっちの道は…」 「どうかした?」 首を傾げたドロテアに、彼は言った。 「ドロテアさん。すまないが…このまま少し、散策に付き合ってくれないか」
帝都の中央広場を後にして、狭い路地に入る。こちらは平民たちの暮らす区画だ。 小さな井戸端に差し掛かると、ローレンツは歩調を速めた。 今までは、自分の歩く速さに合わせてくれていたのか、と…ドロテアは今更ながら気づく。 「ああ…あった」 ローレンツは言った。折り目正しい貴族の顔が、珍しく喜怒哀楽の『喜』を全面に表す。 「噴水…?」 ドロテアは小首を傾げた。噴水ならば、中央広場に美しい彫刻を施されたものが在るのに。 あちらの壮麗な噴水よりも、小さなこちらを見つけて嬉しそうにした彼が、とても意外だった。 確かに古そうだが、歴史的に――あるいは美術的に見て、何か貴重なものなのだろうか? 「小さな竜の像が付いた噴水――確かに。フェルディナント君が言っていた通りだ」 「フェルくん?」 不意にその名前を聞き、ドロテアはどきりとする。 ローレンツは、哀しそうな…しかしどこか嬉しそうな顔をして、「そうだよ」と言った。 「彼は昔、好奇心に駆られて、歌劇場の裏から平民が暮らす街に入ったんだそうだ。 『そこで美しい水の精を見た』と聞いてね」 「…み、水の精…?」 「もちろん、話を聞いた時は僕も信じなかった。フェルディナント君本人も、きっと夢だと笑っていたよ。 その日見る予定だった歌劇を楽しみにしすぎて、幻を見たんだと。…彼はその日、 滞在していた宿を抜け出して――ここへ来たらしい」 「………」 「夏の日の朝だ。どういうわけか、通りには誰も居なかったという。…だが」 ローレンツの瞳は、ドロテアを見つめながらも思い出の中のフェルディナントに焦点を合わせている。 ドロテアは石でも飲んだようになって、その場を動けなかった。 「美しい歌声が聞こえたんだ、と彼は言った。 角を曲がって通りを抜けた時、麗しき水の精が目の前に現れた… 可憐な笑顔が今も胸に焼き付いている、と…あのフェルディナント君が、 恋の熱にでも浮かされたような顔をしていたよ」 「!!」 「僕はそれを聞いて、『水の精など居るだろうか?冒険好きな君を叱るために、 女神でも現れたんじゃないか』と笑ったものだ」 ドロテアは堪らず胸を押さえた。動悸がする。 ――そうだ、暑い夏だった。 マヌエラの推薦を受けて歌劇団の皆の前で歌ったドロテアは、 一足飛びで『歌姫』になることが決まった。 …その知らせを受け取った日の朝、ドロテアは浮かれていた。 この自分が、歌劇団の歌姫として華々しい舞台に立つ。 ――夢でも見ているようで、でも本当だと信じたくて、何度も頬をつねった。 しかし、夢ではなかった…。きっと素晴らしい未来が拓けるに違いない! 暗い路地裏で貴族に施しを乞うたり、残飯を漁っていた自分が、 今までとはまったく違う世界に足を踏み入れるのだ。 みすぼらしい乞食の小娘が、それこそ魔法でも掛けられて美しい姫になるように。 まだ見ぬ明日に期待を膨らませていたドロテアだったが、ふと気づく。 自分の顔や体が酷く汚れていることに。 ……すると、急に恥ずかしくなってきた。他人の目まで気になり出す。 …そういえば、マヌエラがドロテアを歌劇場に連れていった時も、 鼻を摘まんで嫌な顔をしたり、こちらを見てひそひそ話す人間を見た。 大恩人であるマヌエラに迷惑は掛けたくない。…それに、これから『姫』になるのだから、 少しでも綺麗にしておかなくては。 ドロテアは思い立ち、平民街にある小さな噴水にやってきた。少しでも汚れを落としておきたくて。 確か、今日は週に一度の礼拝日だ。みんな教会で祈りを捧げている時間だから、 通りには誰も居ない。――今のうちだ。 ドロテアは噴水に入り、こっそり水浴びをした。 人目からは隠れていたかったのだが、嬉しくて嬉しくて、歌が自然と口を突いて出る。 昨日も歌劇団のみんなの前で披露した…それは、いつだったか帝都で流行っていた歌だった。 歌おうとすると、声が――高く、低く――自在に付いてくる。 ドロテアは、なおも歌い続けた。 はしゃぎまわって足下に溜まった水にわざと波を立て、噴水を手に受けては跳ね散らかす。 虹の欠片が出来て、キラキラと散った。 明るい太陽は、まるで自分を祝福してくれているようだった。 …と。 ドロテアは視線を感じ、止まった。――見ると、 そこに居たのは、赤みがかった金茶色の瞳をした少年。 「!」 貴族であることは一目瞭然だった。 柔らかく波打つ髪は綺麗に整えられていて、光沢のある白シャツにも継ぎ接ぎひとつない。 視線がぶつかると、少年はじっとドロテアを睨んでから、すぐに走り去った。 ドロテアは呆然とそれを見送ったが、次の瞬間ふと我に返って真っ赤になった。 そして、急いで噴水を出て服を着直し、駆け出した。 (見られた。見られたんだわ) 少女としての恥じらいもあったが、きちんとした身なりのあの少年に、 みすぼらしい自分の姿を見られたことの方が、ドロテアには衝撃的だった。 自分を睨んだ、あの目。汚くて卑しい姿に――あの少年は、嫌悪感を抱いたに違いない。 (もういや――!) 消えてしまいたい。なんだってそんな目で見るの?私を蔑んでいるの? 「…っ」 戸惑いから生まれた悲しみは、憎しみに。羞恥心は、劣等感に変わった。 ――あの日。 「――僕は、彼が自分で言う通り、夢でも見たんだろうと思っていた。…だが もし本当なら、場所くらいは見ておきたいと思ってね…なに、ちょっとした興味だよ」 ローレンツは噴水を一通り眺め終えると、独りごちた。 「…ふむ。なかなかの年代物だな。だが、やはり夢は夢か……」 「…夢……」 「ドロテアさん?」 「本当にフェルくんが? ここで、水の精に会ったって…そう言ったの?」 「ああ。あまりの美しさに、思わず言葉を失って見とれたと。 ただ、フェルディナント君は、無性に恥ずかしくなって逃げ出してしまったんだそうだ。 ――意を決してここに戻ってきた時には、もう誰も居なかったと言っていた」 「…。うそ。そんな……」 信じられない。 士官学校へ入学した時、フェルディナントの顔を見て――ドロテアには、はっきりと分かった。 彼が、あの時の少年だと。 成長してはいても、面影は変わっていなかった。 嫌悪感を抑えきれないドロテアに、フェルディナントは笑顔で話しかけてきた。 昔、帝都の噴水で対面した時とは別人のような笑顔で。 ドロテアを睨みつけた時のことは、どうも覚えていないらしかった。 あるいはわざと、忘れたふりをしているのかもしれない。それだけでも腹立たしくて仕方がないのに、 彼は、歌姫時代を経て顕著になっていたドロテアの『貴族嫌い』に、更に拍車を掛けた。 事あるごとに『貴族たるもの』と繰り返し、自分は優れているのだと言って憚からない。 ――権威と権力を強調して、これ見よがしに善意の旗を掲げる。 彼女がよく知る『貴族』と同じに見えた。 (貴方が忘れてしまっても、私は覚えてるわ) ドロテアは思った。よくも、いけしゃあしゃあと――私があの時の女の子だと知ったら、きっと たちまち掌を返して遠ざけるくせに。 彼が向けてくる笑顔はただの飾りのように見えたし、 優しい言葉をかけられたらかけられたで、平民である自分に哀れみの目を向けているのだと思った。 ミルディン大橋で再会したフェルディナントは、エーデルガルトに付き従う忠実な部下だった。 エーデルガルトを『好敵手』などと言って張り合っていたが、 結局彼女にすり寄ったのか……と思った。他の貴族どもと同じように。 大嫌いだった。――それなのに。 「なによ…。やっぱり酷いひと。どうして今更……」 ずるい、とドロテアは吐き捨てる。 フェルディナントは、逝ってしまってなおドロテアの心を過去に縛る。 彼自身はドロテアに何も言わなかった。何一つ言い訳をしなかったくせに、今――今! 友であるローレンツの口を借りて、こんなことを明かす。 「酷いわ…」 ――いや、逆か。酷いのは自分の方なのか。 ドロテアは彼が話しかける気配を見せると、つんとそっぽを向いて離れたことが何度もあった。 話せば話したで、どうしても口調に棘が出る。 学級移動を迷っていた時も、そうだ。 ――『あと三節足らずで卒業だと言うのに、今から学級を移るとは…その… 出過ぎた助言だとは思わないでもないが、やめたほうが良くはないか?』 貴方に言われる筋合いはない、と、ドロテアは彼をはねつけた。 すると、フェルディナントは言った。 ――『私は、君のことを心配して言っているのだよ』 その後やはり金鹿学級への移動を決めたものの、 担任だったマヌエラに言い出せなくて困っていると、今度は背中を押した。 ――『無理をすることはない。君の気持ちは、君自身が一番よく分かっているだろう?』 独善的だと思った。なんだかんだで自分を追い出したいのだろう、とすら考えた。 でも…もしフェルディナントが、心から自分のことを思って言ってくれていたのだとしたら。 そして、もし自分が彼の言葉を素直に聞けていたなら。 ――違う未来が、あったのだろうか。 「ドロテアさん…?」 「見とれていた、ですって? そんなの…そんなの、教えてくれなきゃ分からないじゃない…!!」 嫌われたと思っていたのだ。見下されているに違いないと思っていたのだ。 フェルくん、と呟いた声が嗚咽になってこぼれ落ちる。 「フェルくん…っ、フェルくん…!」 もっと話せばよかった。 もっと理解しようと努めれば良かった。 あのひとが投げかけてくれる好意に気づいて、素直に受け取れば良かった。 後悔が大波になって押し寄せてきて、ドロテアを呑みこむ。――とうとう、涙が出た。 戸惑いながらも静かに見守っていたローレンツが、そっと尋ねた。 「君は…フェルディナント君のことを?」 「嫌いよ…大っ嫌い…!!」 だからせめて自分の手で、と悲壮なまでに思い込んでいた。 敵将としてフェルディナントが現れた時、ドロテアは即座に決意したのだ。…けれど。 ふと、かつて演じた歌劇の一節が頭の中に甦る。 ――『他の誰かの手に渡るくらいなら、いっそ私の手で…♪』 想い人を目の前にして、思い余った女主人公が歌うのだ。 あれほど憎かったのは、愛情の裏返し。 悲しかったのは、彼の愛をどうやっても得られないと思っていたから。 (ああ――私は) 愚かだった、と…そう思う。 そしてドロテアは、とうとう気づいた――気づいて、しまった。 「…ごめん、なさい…」 ――ドロテアが少し落ち着くのを見計らって、ローレンツは、そっと絹のハンカチを差し出した。 「…使いたまえ。涙にくれる君も美しいが、そんな顔で戻ったのでは、皆が心配する」 「ありがとう…」 受け取ったドロテアが、何故だか今度はクスッと笑う。 目に溜めていた涙の最後のひとしずくが、白い頬を伝って流れていった。 「ドロテアさん」 ローレンツはドロテアの目を見て言った。一瞬迷ったが、 今、彼女に伝えるのが最善と判断したからだ。 涙の理由は、ひとまず横に置く。 「フェルディナント君は素晴らしい貴族だった。 平民の君からしてみれば、理解できず苦しんだこともあっただろう――だが、 彼は昔、僕に言ったのだよ。『貴族と平民の垣根を払うことを考えている』と。 お互いを理解し合うことが平和への一番の近道だと、彼は悟っていたんだと思う。 ――少し癪だが、今朝のクロードの言葉を聞いて思い出したよ」 戦塵の帝都が、夕暮れの色に染まってゆく。 「フェルディナント君の言っていた『垣根』には、君とのことも含まれているに違いない。 それだけは、はっきりと言える。彼と君の間に何があったのかは知らないが、彼の誠意は本物だ―― 僕は彼の友人として、君に弁明する。覚えておいてもらいたい」 ――遠征の復路、同盟軍は再びミルディン大橋を渡った。 フェルディナントを倒した場所にまで辿り着いたドロテアは、 道中で手折った白いカーネーションを一輪、手向ける。 帝都の入口に、グロンダーズ平原に…無言で献花をした先生や仲間たちと同じように。 盛りを過ぎてしまった白い花は、だいぶ色褪せていた。 ローレンツは、祈りを捧げたドロテアを見つめながら、胸の内で彼女に問いかけた。 偶然か、それともあえて選んだ花なのか。 (その花に込められた意味を、君は知っているのかい?) 白いカーネーションの花言葉は複数ある。 「尊敬」「純粋な愛」「私の愛は生きている」――そして「愛の拒絶」 相反する意味を持つ花に、ローレンツは皮肉を感じた。 今の彼女がフェルディナントに手向けるならば、どの意味になるのだろう。
帝都攻略は同盟軍の勝利に終わったが、一方で同盟軍の戦いは未だ終わらなかった。 戦死した帝国の参謀ヒューベルトが、このフォドラに暗躍する謎の組織 『闇に蠢く者たち』の本拠地を明らかにし、クロードに後事を託したからである。 今振り返ってみると、『闇に蠢く者たち』はフォドラ各地でたびたび事件を起こし、 その度に悲劇が生まれていた。 金鹿学級の先生の――父親が殺されたのも、彼らの陰謀の結果だ。 ヒューベルトの遺言に催促されるまでもなく、同盟軍の方針は決まった。 ――敵の本拠地を叩きにいく。『闇に蠢く者たち』を倒さねば、フォドラに平和は訪れない。 出撃を二週間後に控えたある日の午後、大修道院内でも 人がまばらな一角で、ドロテアはそっと溜め息をついた。 「戦い続きで嫌になるわねえ」 「ん? ドロテアさんじゃないか」 「まあ、ローレンツくん。どうしてこちらへ?」 訊くと、ローレンツは見回りに来たと返した。 「君のほうは? ここで何を?」 「別に何もしてません。戦い続きで疲れたから、束の間の休息を」 「そうか。平民の君にまで負担をかけ、貴族として面目ない」 ローレンツは大まじめに頭を下げた。 ドロテアは思った。彼の言葉や態度には、思い返した限り――嘘が無い。 最初はただの高慢ちきに見えたが、見方を変えれば、それは彼なりの誠実さの顕れだった。 彼は自分で理想の貴族像を掲げて『より良く在ろう』と努力しているし、 そんな自分に心から自信を持っている。 それが分かると、出会った頃あれほど毛嫌いしていたローレンツが、 不思議なことに好ましく映るようになった。 彼は、見栄を張ってうわべだけ立派に見せようとする男とは違う。 先日の反省があっても、『平民』が、『貴族』が、と明言してしまうところは相変わらずだけれど。 「いいのよ」と、ドロテアは微笑んだ。「それよりローレンツくん、結婚相手は見つかったかしら?」 「なぜその話を今? 捜すどころの状況ではないが……」 唐突な話題の転換に、ローレンツは面食らった。 確かに以前、同盟や家のためになる理想の結婚をしたいと話したことはあるが。 「実は……」切なげに長い睫を瞬いたドロテアは、意を決したように切り出した。 「ねえ、ローレンツくん、突然だけど、伝えたいことがあるの」
伝えたいことがあった、と、ドロテアは舞台上で迸るように歌った。 ――覇道の果てに散った、アドラステア皇帝の役を演じて。 このフォドラにおける戦乱が終結して、更に五年が経っていた。 戦による傷跡がようやく消え始めた今、 ミッテルフランク歌劇団が史実を元に新しい演目を上演しはじめたのだ。 記憶が鮮明なうちに、このフォドラであった戦争を歌劇として残しておきたい。 …初めにそう言ったのは、演出家と脚本家だった。 歌劇『フォドラの夜明け』――初演。 「『だが この気持ちを 今どうして言葉にできようか…♪』」 歌姫として復帰したドロテアが、観客の前で皇帝エーデルガルトになりきって歌う。 役柄上とはいえ、あの時と逆の立場で物事を見るのは不思議な感覚だった。 (先生…。クロードくん) 二人の役を演ずる名優が、ドロテアと舞台上で対峙する。 やがて彼らの隣に、ドロテアが次期歌姫と目している後輩のエミリが出てきた。 彼女は、恩師と結婚した級友レオニーの役だ(役名は、実名と少し変えてある)。 『皇帝よ 気高き花よ…♪』 『我らと 手を取り合う道は無いのか…♪』 『きっと わかり合えるはず…♪』 畳みかけるような三重唱が調和すると、歌劇はいよいよクライマックスだ。 同盟軍を目の前にした皇帝は、三人の説得を振り切って、高らかに宣言する。 『来るがいい 女神の尖兵よ 私は立ち止まらぬ 理想を実現するために…!…♪』 この劇でも一番の難曲、その難所。 ドロテアは喉をめいっぱい開き、旋律の最高到達点を目指す。 「!」 観客が息を呑んだ。 凛と美しい高音が響いた。 例えるなら、冬の早朝――澄みきった空気のようだ。 対峙していた三人が、ドロテアの凄みに気圧されたのが分かる。 (だめよ) ドロテアは自身の歌声を以もって、彼らに訴えかけた。 (真剣勝負なんだから。さあ、掛かっていらっしゃい!) 読み合わせと役作りの段階で、彼女は三人に「遠慮は無用」と言ってあった。 ――剣の一閃。 ドロテアは膝をつき、舞台の天井を仰ぐ。か細いが良く通るその声で、師、と呟いた。 片手を上げ、指先まで神経を行き届かせて、ピンと伸ばす。 ――『ここでこうして戦うのは、貴方の選択の結果。ならば、私もそれに応え、全力で貴方を討つわ!』 同盟軍が追い詰めた宮城で、最後まで自分の理想を信じ向かってきた、気高き女帝。 ――『君にはわからないさ。私やエーデルガルトが背負っているものは』 そう言って戦いを挑んできたフェルディナント。 思い出しながら…そうね、とドロテアは思う。 ちっとも分からなかった。自分は、彼らが背負うものの重さを、知ろうともしなかった。 (でも、今――私は貴方たちの気持ちに、少しでも近づけてるのかしら?) 彼らの答えは、もう聞こえない。 ――実際のエーデルガルトの死は覚えている限り静かなものだったが、 ドロテアは演出家の指示通りに、その美声で絶叫した。 音楽が盛り上げる。歌劇なりの演出だ。 彼らが本当は何を思っていたのか、本当のところは知る由もない――けれど。 (彼らの遺志を汲んで、みんなに伝えられるのは、きっと私だけ…) ドロテアは想像を巡らせた。 そして自分なりに行き着いた答えを、この舞台にぶつけたのだった。 二階席で観劇していたローレンツは、はっとした。――涙が一筋、頬を伝っていた。 「……」 即座に拭う。 隣に並んだ同窓の仲間を見たが、全員が舞台の迫力に呑まれたようだった。 と、会場に割れんばかりの拍手が起こる。立ち尽くしている演者たち三人も驚いた様子だったが、 そのまま芝居は続いた。 終幕後は、文句なしのスタンディングオベーションだった。
ドロテアが出した歌劇初演の招待状のおかげで、 先生と金鹿学級の同窓生たちは、久しぶりに水入らずの時間を過ごしていた。 先生は女神の力を継ぐ者として、なんとフォドラ統一国家の初代国王になってしまった。 元・金鹿学級の皆も、さまざまな形で先生に力を貸している。 戦後五年、なんとか落ち着いてきたが、まだまだやることは多い。 特にレオニーは妻として先生を献身的に支えていたが、 王妃という立場になってしまったのは誤算だった、と溢していた。 とにもかくにも、今日は彼ら全員にとって、やっと得られた息抜きの時間なのである。 「鬼気迫るというか…凄い表現力でしたね!ドロテアさん」 「よくわかんねぇけど…オデ、感動したぞ」 「ええ、さすがです。プロですね」 イグナーツ、ラファエル、リシテアが、三者三様の感想を述べる。 「レオニーちゃんも、可愛かったわよ♪」 「可愛いのは、わたしの役をやってるあの子だろ?名前も変えてあるし。 第一わたしは、あんな高い声で喋らないよ!」 「照れない、照れない。ねー、先生?」 頷く先生の隣で真っ赤になっているレオニーを、ヒルダが楽しそうにからかう。 ――ローレンツはそれを見てから、ふと傍らのマリアンヌに話しかけた。 「そういえば。ガラテア領のイングリットさんはともかく、クロードの奴、本当に現れなかったな」 「ええ」マリアンヌは微笑む。「義父宛に届いた東方からの荷に混じって、手紙が届きましたよ。 『みんなによろしく言っておいてくれ』って」 「…まったく。あいつは何をやっているんだ」 クロードは、仲間たちに後事を託すと、ふらりとどこかへ行ってしまった。 現在リーガン領の統治は、クロードが全幅の信頼を置いている先生の名で行っている。 だがその実――動いているのは、リーガン家の心ある重臣とダフネル家のジュディット、 そしてグロスタール家当主の座を継いだローレンツなのであった。 「みんな、クロードに会うことがあれば言っておいてくれたまえよ。 『どこで何をするにしても、責任はきちんと果たしてからにしろ』と」 「おう!」 「わかった」 「わかったよ」 「「わかりました」」 「そもそも、会えるかどうかも謎ですけどね」 「どこに居るか分からないんじゃねー…あっ、イグナーツ君、そろそろ楽屋にご挨拶に行こう!」 ヒルダが言った。 イグナーツが慌てて荷物を抱え、付き従う。 ヒルダは趣味が高じて装飾品の職人養成学校を設立し、 画家として活動していたイグナーツを講師に招いたという。 芸術を通して仲睦まじくなった二人は商売まで始め、歌劇団に舞台用の衣装や装飾品を卸していた。 「みんなも一緒に来る? ドロテアちゃん、きっと喜ぶよー」 「おー、行くぞ」にこにこ笑うラファエルに、 「久しぶりだもんな」と頷くレオニー。 「仕方ない、わたしも付き合いますか」 リシテアが、いかにも妥協した風を装って加わった。 「マリアンヌちゃんとローレンツ君はー?」 行きます、と進み出たマリアンヌとは逆に、ローレンツは一歩下がった。 「残念だが、僕はこれから行くところがあってね。お先に失礼するよ。 …ドロテアさんに、よろしく伝えておいてくれたまえ」
「今日はありがとう、みんな」 ドロテアは控え室で微笑んだ。 カスパルはどこを旅しているのか分からないし、 ベルナデッタは自領の屋敷で引き籠もっているに違いない。 それに、クロードは仕方ないにしても…金鹿学級の仲間たちが招待に応じてくれて、 正直嬉しかったのだった。 「いいえー。じゃ、私たちも衣装の調整しなきゃいけないんで、帰るわね」 「また明日、伺います」 「中心街の宿に居る?」 「そうしたかったんだけどね」と、ヒルダは笑った。 「滞在費が嵩むから別のところにしましょう、って、ボクが言ったんです」 「ま、仕方ないわ。正直、資金もそこまで潤沢にあるわけじゃないから」 ヒルダの言葉に苦笑したイグナーツが、 宿の場所と名前を書いた紙を渡してくれる。絵入りで分かりやすかった。 「団長さんにも伝えてありますが――何かあれば、ここへお願いします」 「わかったわ」ドロテアは頷くと、意味ありげな笑顔を作った。 「それにしても、貴方たち二人、すっかり意気投合したのね。…一緒になるつもりはあるの?」 「え…っ」 「やだあ。ドロテアちゃんてば直球すぎー!私たち、まだそんなんじゃないわよ」 「まだ、ねぇ」 ドロテアは嬉しかった。彼らは彼らで、新たな自分の道を歩き始めたのだ。 そして…きっと、ローレンツも。 「じゃあ明日、待ってるわね」 ヒルダとイグナーツを送り出すと、ドロテアは一人静かに化粧台の前に座った。 ローレンツが会いに来ないと分かって、内心は残念がっていた自分が居た。 …けれど、それは仕方のないこと。 ――『実は……ねえ、ローレンツくん、突然だけど、伝えたいことがあるの』 まだ戦争中だった、あの日の夕刻。彼の狼狽えた顔を、ドロテアはまた思い出した――… 「私、貴方のことがずっと好きだったの。でも、もう諦めるわ」 「な!? ……いきなりだな。そして、なぜ諦めるのだ?」 身分違いの道ならぬ恋をしていたと言ったドロテアに 彼は一度は納得して頷いたが、すぐにこう言い募った。 「そんなに簡単に諦めていいのか? 本当に? この戦争を通じて僕の考えも変わったかもしれないし、それに……!」 ドロテアの企みは大成功だった。 いつも生真面目で冷静なローレンツを、慌てさせてみたい。 彼の貴族然とした顔が、感情に突き動かされて崩れるところを見てみたいと―― そう思っていたのだ。これはドロテア流の、ちょっとした意地悪だった。 しかし、今思うとそれだけではなかった。 ドロテアは鎌をかけたのだ――彼の、隠した本心が知りたくて。 「ふふふふっ、そんなに慌てて……冗談よ、ローレンツくん。冗談」 咄嗟に冗談だということにした。 彼が腹を立ててくれればそこまでだ。が、彼はそれを怒るどころか笑いとばし、言ったのだ。 「完敗だよ、ドロテアさん。僕の心は、君の言葉に大きく揺さぶられた。いや、気づかされたと言うべきか。 どうやら、僕は知らず知らずのうちに、君に惹かれていたらしい」 「でも、私とは結婚できないのよね。残念だわ、ローレンツくん」 更にそっと探りを入れたドロテアに、 「ああ……そうだな。今はできない」 彼は頷いた。 ずっと抱いてきた自分の信念に決着をつけていないから、今は無理だ。が、 この戦争が終わるまでには、必ず結論を出してみせると宣言する。 「あら……それまで私が待ってられるかしら」 笑い含みに言ってみせたこれには、いつものローレンツらしく自信満々の返答があった。 「ふっ、それは心配ないさ。僕を超える男が、現れるはずもあるまい!」 …―― (私はあの時、冗談で済ませたんだもの) 万一ローレンツが真面目に取り合ったとしても、ずいぶん前の約束だ、忘れている可能性もある。 (あるいは、もっと…私の他に、いい人が現れたかもしれないわよね) ドロテアもまた、ローレンツに惹かれている自覚はあった。 しかし、自分からそれを告げる気はなかった。 ドロテアは――ローレンツに、亡きフェルディナントの面影を重ねていたからだ。 (こんなの、ローレンツ君に失礼だわ) 気づけば、ドロテアの心の中にはフェルディナントへの想いが色濃く残っていた。 もう居ないのに、取り返しがつかないのに…彼の声、言葉、仕草を思い出す。 ローレンツは、顔も性格も違うものの、やはり心根がフェルディナントに似ている。 だが、似ているからといって――亡くなったフェルディナントの代わりにローレンツを求めるのは、 虫が良すぎるだろう。 (私って、嫌な女なのかもしれないわ…) ドロテアは化粧を落とし始めた。 顔を洗い終えて再び覗き込んだ鏡には、泣きそうな顔をした少女のような自分が映っている…。
――皆と別れたローレンツは、旧エーギル領に向かっていた。 季節は初夏、道中には沢山の花々が咲いていた。 お付きの者を伴い、何日か掛けて旅をする。 目的地に辿り着くと馬車を待たせて、今は公営となった墓地に向かった。 彼は花の香を楽しみ、できるだけゆっくりと歩いた。 薔薇は献花としては相応しくない。しかし、墓地手前の道沿いには見事な薔薇が咲いていた。 「見事なものだ…!」 白、黄、淡いピンクに紫、橙。 中でもローレンツの目を惹いたのは――アドラステアの、赤い薔薇。 フェルディナントも好んでいた品種だった。 エーギル家自体は衰退してしまったが、この薔薇は――誰が世話しているのか、 とても綺麗に咲いていた。 …実はローレンツも、戦後この薔薇の苗を持って自領に戻った。 行商人のアンナに仕入れてもらった、あれだ。 屋敷の庭師に頼み込み、温室に入れて自分で世話をした。 しかし、庭師に手伝ってもらってなお、これほど綺麗に咲かせることはできないで居る。 「まったく及ばないな、僕は。これほどの手仕事には頭が下がる」 ローレンツは独りごちた。 薔薇は強く美しいと思っていたが、薔薇が美しくあるのは庭師が丹精込めて育てているからだ。 強い苗もあるが、手を掛けてやらねば始まらない――そんなことに、今更気づいた。 水やりは欠かさず行う必要があるし、剪定も重要だ。 何より薔薇は香りが良いので、放っておくとあっという間に虫がつく。 毛虫が群がっているのを見つけた時には、このローレンツともあろう者が――思わず悲鳴を上げた。 庭師はそんなローレンツを見て、困ったように笑い、こう言った。 「坊ちゃん。より美しい薔薇をご所望なら、 薔薇の奴隷になったつもりで世話をしなきゃあ、なりません」 花が美しく咲き続けるためには、それを助ける手が必要だ。強い苗にも、きっと弱い部分がある。 ――ローレンツは、ふと薔薇にドロテアのことを重ねる。 親友フェルディナントが、薔薇のごとしと言った彼女の姿を。 ドロテアは今まで、どうやって生きてきたのだろう。 本人や先生、級友――フェルディナントから聞いた限りでは、とても苦労をしてきたようだった。 マヌエラに見いだされ歌姫となってなお努力を続けた彼女は、 独学で知識や教養を身につけて士官学校に入ったのだという。 ドロテアが自分自身で磨いた、強さと美しさ…それがローレンツの心を動かした。 此度の歌劇でも――昔、ローレンツの詩をそれとは知らず歌った時も。 「……」 ローレンツは、そっと墓地に入った。 墓石の間を歩き回り…中でも中心にある、立派な墓に向かった。刻まれている名を確認する。 「久しぶりだな…フェルディナント君」 ローレンツは亡き友に語りかけた。 「自領の復興やら、クロードの尻拭いやらで忙しくてね…来るのが遅くなってしまった」 答えはない。 「今更どの面を下げて、と思うかもしれないが――」 ローレンツは誓う。かつてフェルディナントと語り合った理想の世を、いつか必ず作り上げてみせると。 …それが、勝者の務めだ。 「最近は、先生の手伝いもしているんだ。ただ者ではないとは思っていたが―― あの人が、今やフォドラの統一王だぞ。信じられるかい?」 ざあっ、と風が抜けていった。 「それから、もう一つ報告がある」 彼は、特別に手に入れてきた百合の花を墓前に捧げると、切なげに笑った。そして、 「僕は、どうしようもなく惹かれているんだ…彼女に」と独白する。 やがて――珍しくうつむき加減だったローレンツは、毅然と顔を上げた。 「君の愛した薔薇を手に入れる。――許してくれ」
ローレンツが旧帝都アンヴァルに戻ってみると、 歌劇『フォドラの夜明け』は、評判が評判を呼び、連日満員になっていた。 チケットに高値が付き、転売屋まで現れているほどだ。 ここまで評判を呼んだのは今のミッテルフランク歌劇団の団員の実力が確かなものだからだろう。 しかし、もう一つ違う理由も見えた。 この歌劇は、非常にデリケートなテーマでありながら――このフォドラにおける勝者と敗者 どちらにも寄り添い得る、絶妙なところを突いていたのだ。 まだ記憶に新しい先の戦争において、勝者は同盟軍だ。 当然、平和をもたらした同盟軍は多くの人々にとっての英雄で、劇中でも『良く』描かれている。 そして、有り体に言えば旧帝国=『悪』だった。 しかし、同盟軍側のヒロインを演じるであろうと思われた歌姫ドロテアが アドラステア皇帝の役を演じたことで、前評判とは違ってきた。 本来なら憎まれてしかるべき敵である皇帝が、一転。 観衆の涙を誘い、一部の――とりわけ旧帝国出身者の共感を得たのである。 理想を目指して突き進んだ者同士のぶつかり合いと、哀しくも美しい女帝の葛藤、そして覚悟。 ……これが、ドロテアなりの友の弔い方だろう。 評判の良さは脚本や演出によるところも大きかったが、 一番はやはり、歌姫であるドロテアの卓越した表現力にある。 「ドロテアー!」 「ドロテア!!」 「ドロテアさーん、こっち向いてー」 「エミリちゃんも!」 劇場の外、今日は晴れ。 挨拶に出てきてたくさんのファンに囲まれたドロテアは、女神もかくやという美しさだった。 (良い笑顔だ) ローレンツは思った。 かつて口説いてきた男相手に見せた、棘のある艶やかさはそこにない。 心から賞賛を受け取り、それを贈ってくれた相手に感謝して慈しみ、受け容れる――そんな笑顔だった。 同時に、ローレンツは憤りを感じている自分を発見する。 彼女に群がる人々――とりわけ男どもが、自分の大切にしている薔薇に群がる虫に見えたのである。 (これは何だ) 始めての感情だった。 ――『歌姫だった私に言い寄ってきた貴族たちと、さして変わらないわね。 自分の得になれば、相手の気持ちなんて考えもしないんですから』 昔ローレンツと顔を合わせて少し経った頃に、彼女は嫌悪感を隠そうともせずそう言った。 後で知ったが、彼女に言い寄った貴族というのは――ローレンツの持論によれば―― 『貴族』の肩書きを持ちながら『貴族』とも呼べぬ行動を平気でする輩だったのである。 それは違う、とローレンツは異議を申し立てたくなったほどだ。 彼女の『貴族』に対する認識――ひいてはローレンツ自身に対する認識を改めねばと、 妙な使命感に駆られた。 「きゃ!」 「エミリちゃん!?」 ドロテアが目を掛けているらしい歌手の娘が、ふいに悲鳴を上げた。 群衆の中から飛び出してきた男が、抱きつこうとしたのである。 ローレンツが出ようとした時には、既にドロテアが割って入り、娘を庇っていた。 慌てて下がったので、男は見事に転ぶ。 「あら」ドロテアは牽制しながら、男に言った。「ごめんなさいね。怪我はない?」 「は、はい…」 男が自分で立ち上がるまで待ってから、にっこり微笑む。 言外に「触れるのはお断り」というメッセージをしっかり示し、有無を言わせぬ調子で。 「それじゃ、そろそろ行きましょうか。エミリちゃん」 「はっ、はい!」 エミリと呼ばれた娘が、ドロテアの後を追う。…まだあどけない少女に見えた。 「ふ…」 ローレンツは小さく吹き出した。――さすがは一流の歌姫、こういう時の対応も心得ている。 (しかし…) こういう場を、ドロテアは何度も経験してきたのだろうか。 ローレンツは思った。 寄ってくる虫が、全て害虫だとは限らない。…だが無防備に、全てに対していい顔をしていたら、 美しき薔薇は無残に食い荒らされてボロボロに傷ついてしまう。 だから、薔薇は棘を生はやして身を守る。 だが、それだけでは不十分。――守る者が必要だ。 ローレンツは、歌劇団の控え室側に回った。
「大丈夫だった? 油断しちゃ駄目よ。 中にはああいう輩が必ず居るんだから」 「はい。すみません、ドロテア先輩」 まあ、憧れの人に近づきたくなる気持ちは分かるが。――独白は胸に仕舞って、 ドロテアは後輩を指導する。 「どう、エミリちゃん、これからもやっていけそう?」 エミリは、笑顔で即答した。 「はい!負けません!!」 彼女は、同盟貴族の出だ。 そもそも古い特権階級制度が解体されつつあるから、これから身分はあまり関係なくなるのだが。 エミリの親は娘が役者になることに大反対で、彼女はある日一念発起、 このアンヴァルにまで家出をしてきたのだという。 自分を慕ってくれるエミリに最初は困惑したドロテアだったが、 ひととなりを知ってみれば、エミリはとても良い子だった。 ドロテアは、かつてマヌエラがそうしてくれたように、彼女を自身の家に住まわせ 一緒に暮らすことにした。 貴族だ平民だとこだわらなくなると、今まで見えていた世界がいかに狭かったかが分かった。 出身や育ってきた環境、性別や趣向には関係なく、世の中には良い人間も悪い人間も居る。 良い悪いを決定づけているのは、価値観の違いだった。 道徳心に乏しく本当に迷惑な輩というのは、そこまで多くない。 また…ごくたまにどうしても「合わない」人間というのは居るが、少数だ。 無理に共感しなくても、理解さえできればきっと争いは避けられる。 ――結論を導き出したドロテアは、以前よりずっと他人に心を開けるようになった。 とても身軽になったと思う。 それを教えてくれたのが、先生――そして、金鹿学級の面々だった。 「ドロテアちゃーん?」 その筆頭であるヒルダが、ノックした戸口から顔を出した。 「ヒルダちゃん! どうしたの、今日は? なにか頼んであったかしら」 「うん、ちょっとね。ある人から頼まれものをしてて…お届け物です」 ヒルダは最後だけ、少し畏まった言葉で言った。 小柄で愛らしい彼女は、低い位置からドロテアを意味ありげな上目遣いで見る。 「私に?」 小さな箱を開けてみると、それは赤い薔薇の――見事な髪飾りだった。 「ちょっ…これ、本物?」 「うん。造花じゃないよ。樹脂もガラスも無しにして、花をそのまんま使いたい、って話だったから… 最近開発されたっていう魔道具を駆使して、なんとか完成までこぎ着けたの。ほんっと苦労したんだよー」 想いを綴ったカードも、送り主を示す名前も無い。 だが、贈り主のことは、何よりもこの贈り物が雄弁に語っている。 目を見開いたドロテアの耳元に、ヒルダが背伸びして囁いた。 「…外で待ってるって。早速これ、付けて行ってあげたら?」 ドロテアは慌てて髪飾りをつけた。 「先輩」なんとなく察したエミリが香水を持ってきて、ひと吹きする。 濃厚な薔薇の香りが漂った。 「さっすがエミリちゃん。気が利くー♪…あっ」ヒルダは、ドロテアの前髪をチョイチョイと整えた。 「はい、これで良し」 礼の言葉もそこそこに、ドロテアは控え室を飛び出す。 声を掛けてくる劇団員や関係者に言葉を投げ返して――外に出た。 「ドロテアさん」 「ローレンツくん!」 息をきらしたドロテアを、ローレンツは悠然とした笑顔で迎える。 「…っ…。来ないと、思ってたわ…」 「何故なぜ?この前の舞台初日には、薔薇の花束を贈ったじゃないか」 「ええ。だから、それで終わりかと」 「この僕が、それで終わりにするものか」 ローレンツは間髪入れずに言った。そしてシンプルに強い答えを持ってくるのだった。 ――自身が決着をつけた信念――太陽さながらに輝く、ダイヤモンドの指輪と共に。 「僕は、君を愛している。結婚してほしい」 ドロテアは、堪らずしゃくりあげる。…だって、彼を想っていたのだ。決めていたのだ。 ずるい自分には、彼に愛を告げる資格は無い。だが、もし彼が求婚してくれたなら。 その時は、彼の申し出を受けようと――決めていた。 それでも、あまのじゃくな性格の自分が、言わなくても済むことを持ち出す。 「いいの?家に利のある結婚をしたかったんでしょう?」 「僕は、僕の愛した女性と結婚する。それだけさ」 「私は、財産も紋章も、何も持っていないわ。 いつかは美貌も衰えて…歌も歌えなくなってく。ただの女に戻るのよ?」 「古い枠組みは壊れた。拓けたこの世界で、紋章や財産に何の意味があるだろうか。 …それに、君が培つちかってきた君自身の価値と魅力は、決して消えたりしない」 「お父様が反対なさったら…」 「僕が説得する」 「私が、まだフェルくんのことを愛してたとしても!?」 一番重かった真実を、ドロテアはローレンツに叫んだ。 バケツに入れた泥水を、頭から思いっきりぶちまけるように。 しかし、指輪の小箱を懐ふところに仕舞ってサッと距離を詰めたローレンツは、 駄々っ子のように嫌々をするドロテアの両手首を掴まえた。 藤色の瞳が強い光を宿して、じっと見つめる。 思わず怯ひるんだドロテアに、彼は言った。 「構わない」
「ニュースだ! 大ニュースだよ!!」 新聞屋の少年が、嬉々として号外を配っている。 何事かと駆けつけた人々が、こぞって新聞を求める。 ――そこには、婚姻が発表されていた。 政治家のローレンツ=ヘルマン=グロスタールが、 ミッテルフランク歌劇団の歌姫ドロテアを妻に迎えるというのだ。 社会的弱者に配慮した政策を打ち出し多くの人々の支持を得たローレンツと、 たくさんの人の憧れの的である歌姫ドロテア。 今をときめく人気者のめでたいニュースに、 フォドラ中の人々が祝福ムードに酔いしれることとなった。 大々的に行われた祝宴の席では、恩師や級友――それ以外にも 沢山の人々に囲まれて微笑むドロテアの姿があった。 夫となったローレンツは、祝いに詰めかけた人々に対して、誇らしげにこう言ったそうだ。 自分にとっては彼女こそ、最も気高く美しい――アドラステアの、赤い薔薇だと。 |
|||||||||||||||||||||
 |
 日陰に咲く花へ |
 小説ページへ |
 サイトトップへ |