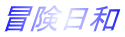
| 風待つ季節 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新生アドラステア帝国が誕生して二年。 戦乱の爪痕は未だ各地に残るが、国は炎の女帝エーデルガルトの手腕により、急速に 復興を遂げていた。そのあまりの速さゆえ、世間ではこの女帝を褒めそやす声と、 「性急すぎる」と不安を表したり、反発する声があった。 それはこのコーデリア領内でも同じだった。 両親に代わって領内の統治に従事していたリシテアは、書面に目を通すと、 そっと安堵の息をついた。なんとかなりそうだ。 コーデリア領は、元々は帝国ではなく、レスター諸侯同盟に属していた。 戦時中、盟主クロードの機転と才気により大きな戦禍は免れたが、戦争の爪痕は皆無ではなかった。 帝国に隣接するこの地で、民は戦々恐々とし、いつしか疲弊していた。 戦争が終結したことで、やっと平和な時代が訪れると安堵したのだが… 水害により、アミッド大河沿岸に広がる街が大打撃を受ける。 被害報告を取り纏めたリシテアが、領民からの嘆願書を受け取って 中央に提出したのが半年前。 復興予算と人手の問題については、宰相となったエーギル公・フェルディナントが 立ち回ってくれた。 ベルグリーズ伯の協力もあり、領民が願ってやまない堤の修復は、近隣諸侯に 引き継ぐ方向で話が進んでいる。 あの大きな戦争から二年。いろいろあったが、やっとここまで来た。 「たった二年で」なのか「二年も掛かって」なのかは、見る者の価値観によるだろう。 リシテアは後者だった。 …性急すぎると言われるエーデルガルトの改革にも、リシテアは進んで手を貸した。 出来るだけ早く国を立て直そうとするエーデルガルトの姿勢が、リシテアには正直ありがたくもある。 「まずは一刻も早く、国の中核を立て直すわ。めざましい復興を、貴女にも見せてあげる」 帝都アンヴァルでの別れ際、彼女が言った事は本当になりつつあった。 執務机の上にあった書面を仕舞い、リシテアは一通の手紙を開封する。 消印は、新生帝国歴の「五月」――エーデルガルトは「女神の眷属」から人の手に自由を取り戻した と宣言し、従来フォドラで使われていたセイロス教の暦を、もっと以前からあった古の形に改めた。 象牙色の封筒には、新生アドラステア帝国の正式な書状であることを示す『炎を纏った鷲』の印が、 黒インクで押されていた。流麗な文字で綴られているのは――皇帝エーデルガルト本人の名。 代筆ではなく、エーデルガルト自ら個人的に宛ててくれた手紙であることが、リシテアには分かった。 そこには、時候の挨拶から始まり、リシテアの体を気遣う言葉、また 自身は元気にしているといった報告が書かれていた。 先日、彼女がついに度重なるフェルディナントの申し出に根負けし、 決闘の末に彼を打ち負かしたことも。 「まあ、当然ですよね」…ふふっ、とリシテアは笑い、手紙の続きに驚いて目を見開く。 「あらまあ……。……。え、ええっ!?」 決闘の末、フェルディナントが口にしたのは完敗と賛美の言葉、だけではなかったらしい。 かつての女帝と鉄血宰相の逸話をそっくりなぞるように、その手に口づけ求婚したというのである。 戦後まもなく公になった宮内卿ヒューベルトと恩師の婚姻にも驚いたものだったが、 これはまた意外なのか予想通りなのか――ともかく驚きの組み合わせだった。 「でも『第一印象が最悪』っていうのは、男女の恋愛物語によくある展開ですからね」 リシテアは一人納得し、続きを読む。恋愛相談でもされるのかと思いきや、 エーデルガルトの手紙には、こうあった。 ――『彼のような人が、私の側には必要なのかもしれない。強い信念を持って、 私に真っ直ぐ異論を唱えられる人が…』 「ええ、そうね。あんたは、もう独りで闘う必要はないのよ、エル」 『あなたとは姉妹も同然になったのだから、こう呼んで欲しい』 …彼女が望んだ愛称を、リシテアはそっと呟いた。 (フェルディナントってば、そんなことして…先生や、あのヒューベルトが 快く首を縦に振るのかどうかは、また別の話ですけど) リシテアは、声を出さずに笑み崩れた。近々、婚礼の式の招待でもあるだろうか。 その手の話だろうと推測して次の一枚を前面に持ってくると、『閑話休題』の文字があった。 そして、『本当に考えを変えるつもりはないのか』との問いと、 『帝都アンヴァルへ来ないか』という誘い文句が連ねてあった。 ――帝都に来れば、自分も側に居てやれる。 リンハルトは、旅先から何か紋章に関する発見があると報告してくれる。 ハンネマン先生も引き続き研究をしているから、リシテアが抱える問題を 解決できるかもしれない、と。 「………」 リシテアの体を巡る血には、二つの紋章が宿っていた。そして、皇帝エーデルガルトの体にも。 それは、『アガルタ』――このフォドラの地の『闇に蠢く者たち』によって成された、 おぞましい人体実験の結果だった。 この実験によってリシテアもエーデルガルトも人智を超える力を手にした。が、 リシテアの体への負担は計り知れなかったのだ。 髪と瞳からは色素が抜けた。――まるで幽霊のようだわ、と震えたのは、うんと幼い頃のこと。 実験を施された後、苦しんで苦しんで――ようやっと目覚めた部屋での恐怖と絶望感が、 今でも冷たく濃いシミとなってリシテアの胸に残る。 帝国の内乱で、コーデリア家が救援要請を受けたのが悲劇の発端だった。 一方的に責任をなすりつけられ、当時レスター諸侯同盟に属していたのに帝国の干渉を受けた。 そこに混じっていたのが、不気味な魔道師たちだった。 コーデリア家の重鎮らは皆、更迭された。 前途ある若者たちがリシテアと同じ血の実験の犠牲になり、命を落とした。 リシテアの両親は精一杯足掻いたが、 結局、娘が屋敷の若者たちと共に実験の現場に連れて行かれるのを、止めることができなかった。 一人実験の成功例となったリシテアは、魔道師たちに短命を宣告された。 『病は気から』というが、疲れやすくなったのもその頃だ。 息は浅くなり、貧血を起こして倒れ、両親に心配されることもしょっちゅうになった。 変貌してしまった自分を変わらず愛し慈しんでくれる両親のために、何かして喜ばせたかった。 たとえ長くは生きられないとしても、苦労を掛けた両親に恩返しがしたい。 だから士官学校に入学した。 入学当初『魔道を操る天才少女』と皆からもてはやされたが、リシテアには忌まわしい二つ名だった。 彼女が操ってみせた闇の魔法には、 血の実験によって強制的に仕込まれた紋章も影響していたからだ。 周囲の人はリシテアの才能を讃えたが、陰でしている努力を見てくれる人は多くはなかった。 帝国は嫌いだったし、憎かった。 その一方で、植えつけられた恐怖は消えず、だから帝国の生徒とも これ以上関わり合いにならないようにしていた。 ――あの先生にさえ会わなければ、リシテアの運命は変わらなかっただろう。 先の戦乱で同盟軍として戦い、かつての仲間と共に命を落としていたと思う。 だが、先生との出会いが、不思議な運命をリシテアにもたらした。 帝国の出身者が集う黒鷲学級を受け持っていた先生は、リシテアにも声を掛けてきた。 最初は警戒していたが、帝国とは関係のない『傭兵』という経歴が、 先生に興味を持つきっかけになった。 異例の抜擢で教師になったという先生には不安の声も多かったが、 先生は生徒に教える傍ら自らも、研修を受けて頑張っていた。 「とりわけ白魔法の上達は、めざましいものがあるわ」と、当時マヌエラ先生が驚いていたっけ。 それでリシテアは、ちょっぴり先生に対する評価を見直し、警戒と疑いを解いた。 (――ふうん、ちゃんと努力ができる人なのね) 今となっては失礼な話だが、指導者としての…そして女性としての先生を、値踏みしていたようにも思う。 そうして気になりだしたら、後は気づくと先生の回りをうろちょろしていた。 先生は、リシテアが声を掛けるときょとんとした顔で振り向く。 その様が時々小動物のようにも思えて可愛らしく、徐々に親しみが湧いた。 顔を合わせて挨拶だけしていた間柄が、いつの間にかリシテアの方から話しかけるようになり―― やがて、黒鷲学級に移る日が来た。 「成績優秀なわたしを勧誘しに来たってところですか? ま、わたしとしては構わないというか……むしろ大歓迎ですけど」 帝国に対する嫌悪感が消えたわけではなかったが、何故か あの時は、先生の元で学べる嬉しさの方が勝ってしまった。 手を引かれて黒鷲の教室に入った日、 皇女だったエーデルガルトとも初めてまじまじと顔を合わせたのだった。 エーデルガルトは色素の薄い髪や瞳と相まって、冷たい印象を受けた。 が、話してみると優しかったりする。 もしかして、と思ったのは、彼女がリシテアの体を気遣い、 書庫の掃除の続きを引き受けてくれた時だ。 エーデルガルトはなかなかはっきりと打ち明けてはくれなかったが、 話すうちに同じように人体実験を受けて苦しい人生を強いられたことは察した。 そして、不思議な連帯感が生まれた。 ――『あんたには、もうわたしたちのような犠牲者が生まれない世界を創ってほしい。 その役に立てるなら、わたしの命を残らず捧げても、後悔なんてしません』 あの時、リシテアが彼女に告げた気持ちは本物だった。…だが。 リシテアは筆を執る。 『お気持ち、有難くいただきました。昔の約束も忘れてはいません。何度も何度も考えました。 ですが、今のわたしは第一に、両親と共に静かに暮らしたいと思っています。 爵位は返上いたします』――
「緑が増えましたよね…」 イグナーツは、食堂のテラス席から見える町並みを眺めながら、旧友に言った。 眼鏡のレンズ越しに、くっきりと瑞々しい樹木の葉が見える。 ここは、とある宿場。 手ずから料理を運んで来てくれた旧友ラファエルは、祖父の営むこの宿を手伝っている。 料理の腕はなかなかのものだという評判を聞いた。 「ああ。焼け出された時は流石にもう駄目かと思ったけどな。 戦争が終わったと思ったら、エーデルガルトさんがあっという間に手を回したって話で」 イグナーツの故郷でもあるこの街は、驚くべきスピードで復興を遂げている。 「エーデルガルト陛下のご尽力はあるでしょうが、 一番頑張ったのは商人組合のみんなでしょう。…ラファエル君も」 「オデは、自分に出来ることをしただけだ」 イグナーツと共に士官学校を卒業したラファエルは、しばらく騎士として地元の領主に仕えていたが、 やがてそれを辞した。祖父の宿を引き継ぎ、今に至っている。 「下手をすれば、君とも戦場で顔を合わせていたかもしれない。 今こうして会えるのを、奇跡みたいに嬉しく思いますよ。…無事で良かった」 とはいえ、黒鷲学級アドラークラッセに転属したことで、 彼自身も決して生易しくはない道を行くことになった。 かつての級友が散っていく様は、今思い出しても…苦いどころの話ではない。 結果論とはいえ、自分はかつての祖国を裏切り、敵方についたのだから。 「後悔しても始まんねぇ。後悔すんなら、まずは飯食って笑え! 食うことは、生きることだ。生きられなかったみんなの分もな」 「ラファエル君…。そうですね」 ドンと卓の上に置かれたサラダは新鮮で、 レタスの緑にパプリカの黄、トマトの赤と、色彩豊かだった。 レタスにフォークを刺し、イグナーツは食べ始める。 「あいかわらず、兎みてえだなー」ラファエルが笑った。「そういや、実家には顔出したか?」 「今朝、挨拶してきました。『画家として身を立てるのはまだか』って突つかれたけど、 それなりに生活もできるようになったんで、納得はしてくれてるみたいで」 「そうかー、よかったなあ!」 一度は画家としての道を諦めたイグナーツが、 黒鷲学級の先生や士官学校の級友と交わる中で考えを変え、 父と兄を説得までして夢を追う決意をしたことを、ラファエルは知っていた。 戦争があって良かったと思ったことは一度も無いが、 イグナーツの人生は、黒鷲学級に転属し、あの戦争に身を投じたことで変わったのかもしれない。 「そういえば、リシテアさんはお元気かな。これからコーデリア領まで 足を伸ばしてみようかと思ってまして」 「あれ? 聞いてねぇのか」 「何を?」 イグナーツは首を傾げた。 「去年か。リシテアさん、爵位を降りたんだ」 「そ、そうなんですか!?」 領地は、周辺諸侯に割譲されたという。 イグナーツは丁度そのタイミングでフォドラを出てしばらく旅をしていたため、 その辺の事情はあまりよく知らなかった。 「それで…リシテアさんは」 「親御さんと一緒にどっか田舎に移ったらしいけど、行先は詳しく知らねえ。 オデは、政治のことも帝都のことも、話に聞くだけだったからな。 あ…でも、リシテアさんから最後に来た手紙に、その田舎のことが少し書いてあったぞ」 「へえ…。どんなところだろう」 「待ってな。持ってくるから」 「え、い、いいですよ!大事な手紙でしょう?許可も無く読むなんて」 「オデが見せたいんだよ。大丈夫、イグナーツならリシテアさんも喜んでくれるさ。 手紙から想像して、どんな景色か描いて見せてくれよ」
フォドラの東端にそびえる雄大な山々は、「フォドラの喉元」と呼ばれている。 かつて遠征で行った「首飾り」と称される砦は、その名に似合わず堅牢さの方が際立ったが、 白っぽい石を積んで作った防御壁は、遠くから見れば陽に光って綺麗だった。 画家として身をたてるべく修行の旅をしていたイグナーツが、この山脈の麓にある いくつかの集落を巡ったのは、旧友ラファエルと会ってからしばらく後のことだ。 初夏の日差しは日に日に強まっていたが、この辺りは平野に比べればとても涼しい。 山道を歩くのも苦にならなかった。 この辺は、昔取った杵柄と言えよう。 思い返せば士官学校があるガルグ=マクも山の上だったし、厳しい訓練で 高所の行軍をしたこともある。今や、体力にはちょっとした自信があった。 イグナーツは見事な山並みを眺め、足元に咲く可憐な花々に目を留める。 途中、山羊が放牧されているのを見つけた。 そのように目に付いたものを写生して歩くのが、彼の日常だった。 街や村に入るとしばらく宿に滞在し、描きためたスケッチを元に油彩画や水彩画に起こす。 絵を気に入ってくれた人があれば、売って路銀を稼いだ。 それでも不足する時には、日雇いの仕事などを請け負った。 懐具合は時に厳しかったが、それでも好きな絵を描いて生きていられるのが幸せだった。 この日もイグナーツは、景色を楽しみながら歩いた。 やがて小さな村を訪れたのは、日差しが傾き始めた午後だった。 村の入口付近では、子供たちが遊んでいた。 宿を探していると、途中、機はた織り小屋を見つける。機織り機の規則正しいリズムが心地良かった。 窓は開いていて、女性が流れるような手つきで糸を通し、布を織り上げていく。色も鮮やかだった。 目が合ったので、挨拶して窓越しに寄っていき、宿の場所を尋ねる。 元々が商家の次男坊であるイグナーツは、人好きのする笑顔で警戒心を解いてしまうのだった。 「観光ですか」 辿り着いた宿の主人は物珍しそうに尋ねた。 「ええ、まあ」 「観光なんか、できるようになったんですねぇ。 近頃はパルミラとの小競り合いも無くなりましたからね。まったく平和ってのは有難いもんです」 「本当にそうですね」 「でも、こんな何も無い村に来るなんて、物好きですね」 「山が見たかったもので。ボク、絵を描きながら旅をしてるんです」 「ほう、画家さんですか」 「あはは…お恥ずかしいです。まだ修行中の身なんですけど」 「山を描くんなら、よく見える部屋がありますよ」 主人は親切にも、イグナーツに景色の良い部屋をあてがってくれた。 「うわあ、本当によく見えますね!素晴らしいです」 「でしょう。これだけは、うちの自慢なんですよ」 翌日、イグナーツが村の中でスケッチをしていると、子供たちが興味津々、見にきた。 但し「都会から来た眼鏡の画家さん」に気後れしているようで、木の陰から遠巻きに覗いている。 ひそひそ声は内緒話のつもりなのだろうが、よく聞こえた。 イグナーツは笑み崩れ、子供たちに「おいで」と声をかけた。 おどおどしながらも、子供たちは話しかけてくる。 「おじちゃん、絵描きさんだよね」 「そうだよ。よく分かったね」 「お父ちゃんが言ってた」 「何描いてるの?」 「見せて見せて!」 「あっ、俺にもー!」 子供たちにせがまれるまま、スケッチブックをめくる。 「綺麗なお花」 「勿忘草っていうんだよ」 「山だ!」 「山羊かわいい」 「父ちゃん!そっくりだ!すげー」 「これ、あたちのお母ちゃん」 「えっ、機はた織りの?」 わいわいと楽しそうな子供たち。 イグナーツがまた一枚、スケッチブックのページをめくった時、一人の女の子が尋ねた。 「これ、だあれ?」 「女神様だよ。…もう、居ないんだけどね」 木炭でデッサンされた人物に、モデルは居なかった。イグナーツが想像で描いた女神だ。 士官学校生だった頃、大聖堂の天井画に魅せられて模写していたのが懐かしい。 あの戦争で、女神の存在自体が夢のように消えてしまったのだけれども。 イグナーツが切ない溜息をついたところで、ふいに、きかん気そうな少年が言う。 「うっそ!俺、見たことあるよ!」 「え?」 村には、セイロス聖教会の名残ある建物があった。 そういった建物はエーデルガルトによってほとんど作り変えられたはずだが、 この辺境の地には、かつての女神の壁画か天井画でも残っているのだろうか? 興味を惹かれて、イグナーツは尋ねる。 「どこで?村はずれの建物かな。連れていってくれる?」 「ううん、待ってればくるよ」 「ときどきだけどね」 「女神さまじゃないよ。妖精さん」 「さいしょね、ユウレイかと思った」 「ゆ、幽霊?」 子供たちが口々に訴える。 彼らがイグナーツを引っ張っていったのは、村にたった一軒の雑貨屋だった。 「ここ…?」 子供たちは、揃って頷く。雑貨屋の女将さんが出てきて、戸惑うイグナーツに言った。 「いらっしゃい」 「こ、こんにちは。あの…」 イグナーツより先に、子供たちが声を上げる。 「おばちゃん、今日は妖精さん、来た?」 「お菓子ある?」 「ああ…それなら、ついさっき置いていったよ」 「お菓子?」 イグナーツが尋ねると、女将さんは小さな紙袋に入った焼き菓子を出してきた。 絞った袋の口に、綺麗なリボンが結んである。 「村外れに住んでるお嬢さんが、時々作って卸してくれるのよ。 そもそも材料が入らない時もあるから、そう頻繁じゃないんだけどね。良かったら、いかが?」 「美味しそうですね」 イグナーツは、入り用なものを見繕い、 最後に籠の中の焼き菓子を一袋取って、カウンターに置いた。 会計を済ませると、焼き菓子の袋をその場で開けて、子供たちに一つずつ分けてやる。 「ああ、ああ…すみませんね、子供たちにまで。…これ!お客さんの分まで食べちゃだめ!」 イグナーツは笑い、自分も一つ口に入れた。――と。 「美味しい?」 にこにこ訊いてくる女の子の目の前で、イグナーツは目を見張った。 時が経って埋もれた記憶の欠片が、途端に鮮やかに蘇ってきたのだ。 ――『この間のお礼です。紅茶には甘いお菓子が一番』 ――『うわ、甘い…物凄く甘いですね、これ』 ――『あんたの好きな、そのお茶になら合いますよ』 ――『あ…本当だ!美味しいです、リシテアさん!』 ――『でしょう』 「おじちゃん?」 ――『自分で作ってみたんです。砂糖が手に入らなくて…今日のは、そこまで甘くないんですけど、 これならイグナーツも好きかなって』 ――『美味しい…ボク、これ好きです』 ――『うっふっふ。決め手は、シナモンをほんのちょっぴり効かせることです』 香りがする。懐かしい、匂い。 「あの。これを作った方は、どちらに?」イグナーツは訊いた。 怪訝そうにした店の女将さんに説明する。 「す、すみません。その人…ボクの、学生時代の友人かもしれなくて」 手元に残された記憶の糸を手繰るように、呟いて。 「教えていただけないでしょうか!?」 慌てて店を出て、イグナーツは走った。 傾斜のきつい坂を大股で登り、息を切らす。 探しているつもりはなかった。 実際にここに来るまで、彼女のことをそこまで考えては居なかった。ただ、 ――『リシテアさん、爵位を降りたんだ』 何があったにせよ、どこかで幸せに暮らしていればいいと思った。 同期生の中では一番年が若くて、いつも一生懸命で、誰よりもしっかりしていた彼女が、 イグナーツは最初、苦手だったかもしれない。――あまりにも隙がなさ過ぎて。 何でもできてしまう天才少女にしてみれば、鈍くさいイグナーツには非常にイライラしたのだろう。 昔は何かというと怒られていたように思う。 指摘は真っ直ぐに事実を突いているのでもっともなのだが、 その率直な物言いは鋭すぎて、傷ついたこともあった。 自分だって頼りになるんだと示したくて、 売り言葉に買い言葉で、つい見栄を張ってしまったこともある。 だが、共に居て気づいたことがある。――彼女も、イグナーツと同じように背伸びをしていたのだ。 お互いに背伸びをして高さを競い、ふらふらよろけていたような具合だった。 今にしてみれば笑い話だ。彼女の場合は周囲からの期待もあったのだろうが。 隙を見せると子供扱いされるから嫌だと言っていた彼女は、 時に無理をしているように見えて、イグナーツはときどき心配になった。 よくよく観察してみると、いつも余裕が無さそうに見える。 戦争が始まると、何かに追い立てられるように、彼女はますます目の前のことに打ち込んだ。 あんな生き方で疲れないのかな、と疑問に思ったこともあった。 今も同じだろうか? それとも、公務から解放されて、少しはゆっくりできているだろうか? ――青い花びらの勿忘草わすれなぐさが風に揺れる。 いつの間にか解けた靴紐を焦って結んでいると、 追いかけてきていた馬車が彼の後ろで止まった気配があった。 「兄ちゃん、上の方に行くのかい。なんだったら、乗っけてってやろうか?」 「あ…」思いっきり走りすぎて酸欠でふらふらしながら、イグナーツは礼を言う。 「ありがとうございます。あの…村外れの青い屋根の家を訪ねたくて」 「へえ。そいつは…なんでまた」 御者は、若干警戒したように見えた。 「そこに住んでいるのが、ボクの古い友人かもしれないんです」 と。次の瞬間、馬車の荷台から慌てて身を乗り出した人が居た。 最初、帽子を深々と被っていたので分からなかったが、 立ち上がった瞬間、珍しい色の綺麗な髪が風に煽られて広がる。 こんな髪の色を、イグナーツは他に見たことがなかった。 吸い寄せられるように見つめた瞳が、同じようにイグナーツを見て 驚くのが分かった――不思議な光を宿す、紅の瞳。 「……。イグナーツ…!」 「リシテアさん!!」 記憶の中から抜け出てきた彼女は、懐かしい声で指摘した。 「靴の紐が…危なっかしいこと。今に転びますよ?」一旦馬車から降りると、 イグナーツの足元に屈んだ。「結んであげます」 「…。あっ、自分でできますから」 「どうせ縦結びにしちゃうでしょ」 彼女は昔と同じように指摘したが、 その声色に以前のような棘は無く、むしろ慈しむように柔らかだった。 丁寧に靴紐を結び、 「……はい、できました」と、立ち上がる。 「ありがとう」 イグナーツは微笑み、礼を言った。 「お久しぶりです。リシテアさん」 白い小さな顔には、呆れたような困ったような笑顔が浮かんでいた。
「懐かしいですね。 引っ越したことはラファエル君から聞きましたけど、まさかこんな形でまた会えるなんて」 「本当に。なんであんた、こんな所に居るんですか?びっくりするじゃない。 …まさか、ラファエルから聞いてここに?」 「いやあ、いつか会えたらいいなとは思ってましたけど、そういうわけでは」 「あら…そう」 「探して欲しかったですか?…だから、あんな謎かけのような手紙を?」 「そんなことしません!あんたの中のわたしは、幾つですか!…って、あんた。 わたしの手紙、勝手に読んだのね!?」 「違いますって!ラファエル君が見せてくれたんですよ…!」 再会したイグナーツとリシテアは、馬車の荷台で話に花を咲かせた。 やがて馬車は止まり、リシテアが心得たように降りようとする。 「ここから先は道が細いので、馬車が通れないの。悪いけど、一緒に歩いてください」 イグナーツはリシテアの荷物も纏めて持ち、先に馬車から降りて彼女に手を貸した。 小柄なリシテアはイグナーツの手を取ると、ぴょんと馬車から飛び降りた。 二人で御者に礼を言い、青い屋根の家を目指して歩き出す。 イグナーツは二人きりになったことを確認して、ぽつりと話を切り出した。 「爵位を返上したって聞きました」 「ああ…そうなんです。戦争が終わってすぐ、 バルタザールが――というより、彼の弟さんが、いろいろお世話してくれまして」 「バルタザールさんが?」 意外な名前を聞いて、目を丸くするイグナーツだ。 「私の両親に『恩がある』とか言って。 まあ、当人はその後、どこをほっつき歩いているのか知れませんけど」 「彼らしいですね」イグナーツは笑った。 「…ところで、そのご両親ですが、大丈夫ですか?ボクがお家にお邪魔して、ご迷惑ではないんですか?」 「わたしが良いいと言ってるんですから、あんたが気にする必要はないの。 それに…父も母も、わたしの友だちが来たって言ったら、むしろ泣いて喜ぶかもしれません」 「え、そんなに?」 「ええ」リシテアは、空を仰いだ。「戦争も大変だったし、その前も、その後も―― あれから本当に、いろいろありましたから…」 「……」 共に黒鷲学級に転属した者同士だからこそ覚える連帯感を、 イグナーツは思い出と共に味わっていた。 リシテアは今、何を思っているのだろうか。
「イグナーツ、あんた運が良いですよ。ちょうど今日、ケーキを焼いたところだったんです」 リシテアは振り向いて笑った。出迎えた父母にただいまを言い、イグナーツを紹介する。 「初めまして」 リシテアの両親はイグナーツを見るなり、本当に大喜びしてくれた。 母親など、目を潤ませて泣き出しそうになっていたくらいだ。 青い屋根の家はこぢんまりしていたが、何とも言えず温かい雰囲気で、居心地の良さを感じた。 リシテアが手製のケーキを切り分ける間、彼女の母が紅茶を入れてくれる。 雑談を始めると、話題は自然と、イグナーツ自身のことや士官学校時代のことになった。 「…ほう。イグナーツ君は画家なのか」 感心したように言うリシテアの父に、イグナーツは頷いた。 「はい。まだ修行中の身なので、お恥ずかしいんですけど…。 ボクは、もともとは親の意向で騎士を目指していたんです。でも結局、夢を捨てきれなくて…」 「そうか。人生一度きり、明日は何が起こるか分からない。 ならば、自分の信じた道を行くのが良いと、私は思うよ」 「ええ…ボクも、そう思います」 「……」お茶を注いでくれた母親が、ふとイグナーツに訊く。 「学生時代のあの子は…リシテアは、どんな印象でした?」 「え?そうですね、リシテアさんは…良い仲間でした。 何に対しても一生懸命で、ボクから見たら何でもできて、尊敬していました。 失敗しているところを見たことがなかったです」 「そう…」 母親は微笑んだが、心底嬉しいというよりはどこか悲しそうで、イグナーツは内心首を傾げた。 …そうか、と思う。 この両親に会った時から違和感を微かに感じていたが、 それは穏やかな笑顔の中に、翳りがあったからだ。 リシテアの父は言う。 「あの子には、うんと幼い頃から苦労を掛けてしまったからね…。 辛いことが沢山あって…それでも屈せず、良い子に育ってくれた。私たちの自慢の娘だよ。 ただ、無理をし過ぎていないか、それだけが心配で――正直、今もね」 「今も?」 リシテアは爵位を返上し、公務から解放され、自由を手にしたのではなかったのか。 両親と三人だけの慎ましくも穏やかな暮らし。今の彼女は、とても幸せそうに見えるのに。 どういうことかと聞き返そうとした時、リシテアが台所から戻ってきた。 両親が口をつぐんだのを見て、イグナーツもそれ以上何か言うのをやめた。 「お待たせしました」 出されたケーキは小麦粉、卵、牛乳、砂糖とバターを混ぜて焼いた、素朴だが贅沢なものだった。 「大奮発です」と言って、リシテアが泡立てたクリームとベリーを添えてくれる。 「さ、召し上がれ」 「いただきます」 彼女が極端な甘党だったことを思い出したイグナーツは思わず躊躇したが、口に入れてみると 甘いのはケーキ生地だけで、クリームは甘さが抑えられていた。 ベリーの酸味がアクセントになり、とても良い。 「美味しい!」 「でしょう」 リシテアが得意げに言う。 「腕を上げましたね、リシテアさん」 「ふふ、もっと褒めてくれてもいいんですよ?何なら代金を払ってくれても」 「まあ、リシテアったら!」 「勘弁してくださいよ。ただでさえ懐が寒いんですから」 「では、出世払いということで。絵一枚で手を打とう」 「あら。父様、良い案ですね」 リシテアは言い、自作のケーキを一口頬ばった。 「ふむぅ」と妙な声で感嘆し、もぐもぐ、ごくん、と飲み込む。 人形のように整った顔が、これでもかというほどに笑み崩れた。 「おいしーい!幸せ!!」 ほっとしたように、彼女の両親が笑う。 和やかなお茶会は続いたが、 彼女の父親が言った言葉が、イグナーツには引っかかったままだった。
「…しまった!もうこんな時間か」 気づくと、もうかなり日が傾いていた。イグナーツは慌てて席を立つ。 「どうもありがとうございました。そろそろお暇します。――リシテアさん、ケーキ、ごちそうさまでした」 「えっ、あ…」 リシテアが躊躇ったのを、彼女の父は見逃さなかった。そこで、目の前の青年に 至極もっともらしく提案する。 「今から帰っても、宿に帰り着く前に暗くなってしまうよ。今夜は泊まっていったらどうだね」 「それがいいわ、イグナーツさん」 母親の方も賛成する。 「えっ、でも、それはさすがに…」 「この辺の山道は、慣れない者が歩くと危ない」 「大丈夫です!剣術の心得もありますから。旅をしてるので、夜の山道は慣れっこですし」 「いや…獣に出くわす心配より、迷う心配が、ね。崖から転落しても困るし」 「確かに」とリシテアが頷いた。「あんた、ぽーっとしてるところがあるから、 万一のことがあったら困るわ。わたしたちの寝覚めが悪くなるじゃない」 「でも…絵の具とか筆とか、宿に一式置いてありますし。 ご依頼の絵を描こうにも、一度戻って取ってこないと」 「下書きのラフなら、そのスケッチブックで十分でしょう。 宿の方には、明日わたしも一緒に行って説明しますから」 「で、ですが、そんなの申し訳ないですし」 「何なら宿代も私が払おう」 「余計申し訳ないですよ!」 「ああー、もう!分からない人ですね。他人の厚意は素直に受け取るものですよ?」 「…。それ、リシテアさんが言います?」 「こちらが困るから、お願いしようとしてるのよ。 昔『何かあったら、試しに頼っていい』って、言ってくれたじゃないですか!」 「お試し期間は、終了しました!」 「何、その宣伝文句みたいな断り方!」 親しい者同士特有のじゃれ合いのような喧嘩が始まってしまった。 早く帰った方が良いのに収拾がつかなくなったな、とイグナーツが困っていると、 「イグナーツさん、わたくしたちを助けると思って」と、リシテアの母が申し出る。 「お風呂を沸かすにも、お料理を作るにも、薪を運んでこなければならないんだけど… この歳になると、どうにも力仕事がね。先に出来る下ごしらえをしておくから、 今日だけでも…この人を手伝って、持ってきてくださらないかしら?」 それは取って付けたような理由だったが、「お願い」と言われてしまうと断れなかった。 切実そうな視線に正面から捕まってしまったイグナーツは、戸惑いながらも承諾した。 そのまま、持ち出そうとした僅かな手荷物をリシテアたちに預け、彼は父親と共に薪を取りに出る。 良いタイミングだ。…これを逃したら、もう聞くことはできないんじゃないかと思って、 イグナーツは尋ねた。 「あの…さっきのお話ですが」 「うん?」 「リシテアさんが、『今も無理をしているんじゃないか』って…どういうことですか? ボクには彼女が、今とても幸せそうに見えるんですけど」 「そう見えるかい。ならば、わたしたちも嬉しいんだが…あの子は、何でも 自分でやろうと頑張ってしまうから」 「ああ…そういうところ、ありますね」と、イグナーツは微笑んだ。 「昔、士官学校で――と言っても、黒鷲遊撃軍として 大修道院を占拠していた頃のことですけど――リシテアさんが話してくれたことがあります。 『誰かを頼るのが本当に苦手だ』って。 でも、だから、彼女が本心から頼ってくれた時は、嬉しかったです。 …あっ、と言っても、『お茶を淹れて』くらいのことだったんですけどね」 「リシテアが、そんなことを…」 「はい。本当に素敵なお嬢さんですね。何事にも一生懸命で、ひたむきで、 ご両親のことも大事にして。…ボクは、父や兄を説得したとはいえ、 自分の夢を優先させてしまったから――彼女の生き方を見て、反省することも多くて。 …後悔は、していませんが」 そして結果論だが、尊敬する恩師についていったことで、祖国も裏切った。 「リシテアさんは、お父様とお母様にも笑顔になってほしいから、頑張ってしまうんだと思います。 だからお父様も、嬉しいとか楽しいとか美味しいとか、 リシテアさんに笑顔を返す――それで十分じゃないんでしょうか」 「…そうだね」 「あっ、すみません!ボクみたいな青臭い奴が、偉そうに」 「いやいや、君の言う通りだよ。リシテアは、士官学校で良い友だちに恵まれたんだね。 …ありがとう。ああ見えて、不器用なところもある子だが――どうか、これからもよろしく頼むよ」 「えっ…」 「こんな辺境だ。なかなか訪ねては来られないだろうが、仲良くしてやってくれ」 「は、はい!」
夕食の時間も和やかに過ぎていった。 食後もイグナーツは、旅先で見た景色や出会った人々の話を、リシテアたちに話して聞かせた。 彼は面白おかしい冗談を言えるような性格ではなかったが、 心から楽しそうに話すので、リシテアも両親も、いつの間にか笑顔になっているのだった。 「しかし、君の絵は珍しいね。あまり見たことのない題材が多い。 人物画と言っても貴人や英雄や神ではなく、村の子供たちや、機織りの職人なんだね」 「父様。昔は女神様ばっかり描いていたんですよ、イグナーツは。 騎士様の絵といっても、凜々しくて美しい女性の絵だったし」 「まあ、面食いなの?」 クスクスと笑うリシテアの母だ。 「えっ、そんなことは…まいったなぁ。リシテアさん、勘弁してくださいよ」イグナーツは頭を掻き掻き 言い訳したが、「まあ、そういうこともあったかも…」と認めた。 「うーん…価値観が変わったんだと思います。 昔は、ボクは自分が美しいと思うものを、自分の想像上で描いていました。 でも、今になって思うんです。どんなことも、事実という土台があるからこそ、 説得力を持って輝いてみえるんだって」 「ほう」 「たとえば、泥んこ遊びをした子供を『汚い』って怒る親御さんが居ますけど、 その泥んこがあるから、花が綺麗に咲きます。 毛嫌いされることが多い虫たちやミミズも、居てくれるから土が肥えて、豊かな実りに繋がる。 人間だけじゃない、花も虫も鳥や獣も、一生懸命生きている。 そういう側面を、忘れちゃいけないと思って」 「その通りね」 「同じように…人が一生懸命生きた証として、今の世界があると思うんです。 焦土になっていた場所が緑に変わっていく。戦争で崩れた街が復興して、綺麗に整っていく」 イグナーツは微笑んで、続けた。 「人の暮らしは、どこに行っても同じでした。汗水垂らして働いて、食べて寝て。 そして、『今日も無事に過ごせたね』って家族や仲間と笑っている……美しいと思いました。 それでボクは、そんな人たちを描きたいと思ったんです。その人たちが暮らす土地の風景も」 「うち捨てられて廃墟になった場所は、どうなんですか?」 と、リシテア。 「ええと――そういう場所では、自然が人間の代わりをしてくれます。植物が朽ちた建物を 包み込んで、風と雨と光が、ゆっくりゆっくり時間を掛けて、風景を作り上げていくんです」 「戦争の絵だってあるじゃない。あんただって、ミルディン大橋が陥落するのを描いた… それも、美しいと思ったから?」 「…それは、ちょっと意義が違ってきますね。 『昔こういうことがあった』と後世に伝えることができたらと思ったからです。 そのようにして残された歴史的絵画も、沢山ある」 「時間は、全部を美化してはくれないわよ」…リシテアは俯いた。 「時間が経てば、真実なんて簡単に埋もれてしまうし」 それを見たリシテアの父が、話題を少し逸らした。 「そういえば…絵というと、私は肖像画や静物画しか見たことが無いが、君は、風景も描くんだね」 「はい。季節毎の移ろいが、土地によって違って、でもどれも甲乙つけがたく美しくて…」 たまたまスケッチブックにあった自作の風景画のラフを見せて、イグナーツは言う。 「ブリギットは――ペトラさんの故郷ですね――空が本当に青くて、地平線が遠くにあって… 見ていると、自分のちっぽけな悩みなんか、どこかに行ってしまいました」 「そう…。わたしも本物を見たら、そんな風に思えるかしら」 ぽつりと言ってしまったリシテアは、しまったと思った。 両親が、なんとも言えない顔をしてこちらを見ていたからだ。 イグナーツもきょとんとしてリシテアを見たが、眼鏡の向こうの優しげな目がぱっと輝き、 続いて嬉しそうに微笑んだ。 「ええ、思えますよ!そうだ。リシテアさん、何ならいつか、一緒に行ってみますか?」 「「!」」 両親は驚いた顔をしていた。 さすがに軽いことを言い過ぎた、と思ったのか、イグナーツは口ごもる。 「その気も無い提案を、軽々しくしないでください。 第一、旅をしてまであんたの面倒を見るなんて、お断りですよ」 「そ、それは…でも、ボクと一緒かどうかはともかく、本当に凄い景色なので、お勧めですよ。 いつか、機会があれば見にいってみてください」 「そうね。『機会があれば』ね。――たぶん、わたしには無理ですけど」 ぽつりと呟いたリシテア。身を乗り出すイグナーツ。 「ど、どうしてですか?」 「どうしても。地図見て言ってごらんなさい。ブリギットなんて、ここから反対側じゃないですか」 「で、でも…ボクでも行って帰ってこられましたから! もう戦争も無いんです。旅行だって安全に――」 「そういう問題じゃないんです!」 「…?どうしてそう、頭ごなしに否定するんですか。どうして無理だと決めてしまうんですか? リシテアさんらしくないです、そんなの」 「わたしらしい?わたしらしいって何です? あんただって、わたしのことを『こんな人間だ』って決めつけてるじゃない。 わたしのこと、よく知りもしないくせに」 「知ってますよ。学生時代から何年一緒に居たと思うんです? リシテアさんは努力家で、何でもできて――」 「出来ないことだってあるのよ!」 言い募るイグナーツを、リシテアはぴしゃりと制した。 「あんたは、いいですね。夢を語れて。どこへでも行けて。時間もあって…」 はあっ、と息をつき、やめる。 「…ごめんなさい。ひがみっぽくなってしまいました。――ごちそうさま。食器、片づけますね」 母親が、彼女の背中をそっと押して、一緒に台所に下がっていった。 「イグナーツ君」リシテアの父は、二人が居なくなると、思い切ったように話しかけた。 「君に、聞いてもらいたい話があるんだ」
(もう!なんなのよ) リシテアは、がさがさと食器を洗った。 ――腹が立つ。久しぶりにひょっこり現れたと思ったら、 一方的な価値観を押しつけたばかりか、純粋無垢な理想をひけらかして。 「リシテア」 「とんだ理想家ですよね、イグナーツって」 「リシテア、おやめなさい」 「母様は気にしないで。ああいう人なんです。だから時々腹が立つだけ…」 母の腕が、背中からリシテアを抱き締める。 その腕をリシテアにきつく絡めた母は、ごめんね、と呟いた。 「ごめんね。守ってあげられなくて」 「……っ」 そんなことを言わせたかったわけじゃない。 父も母も、リシテアを精一杯愛して守ってくれている。昔も、今も。 「母様かあさまが謝る必要はありません」 すぐ側で涙を感じ、つられてうっかり泣きそうになる。 忘れられたら良かった。昔の嫌なことを、全て。でも無理だ。 それに、思い知ってしまう。あんな風に笑顔を見せられると、自分には決して手に入らない未来を。 イグナーツが、あんなに楽しそうに笑うから。 (あ…) 未来を手に入れたいなら、自分にだって別の道があった。 もっと足掻けば良かったのか? あの時、エーデルガルトの誘いに応じて帝都に行く選択肢だってあったはずだ。 でも…リシテアは、それをしなかった。 (後悔してるの?わたし) いや、そんなことはないはずだ。わたしは、わたしの道を選んだ。 ――『自分のちっぽけな悩みなんか、どこかに行ってしまいました』 イグナーツも、きちんと自分に向き合ったからこそ、今あんな風に笑えるのだ。 納得いく選択をしたからこそ、脇目も振らず進んでいけるのだ――。 「………」 お互い本当に、いろいろな経験をした。だからこそ選べた道だ。 リシテアは濡れた手を拭き、振り向いて母を抱き返した。 「わたしは今、幸せです。だから、泣かないでください。母様」
イグナーツは、借りた寝室の床に、ひとり放心状態で座り込んでいた。 星は多いが小さくて、部屋を明るく照らしてはくれない。 (そんな…) リシテアの父がしてくれたのは、思いも寄らぬ…にわかには信じがたい話だった。 人工的に二つ目の紋章を宿され、結果、人の命を縮めるなど。 帝国は――いや、帝国の裏で動いていたというアガルタは、そんな非道なことをしていたのか。 ――『聞けば、皇帝陛下も同じ実験の犠牲者だったと―― それで今も、娘やわたしたちを気に掛けてくれているんだ。ありがたいよ』 彼女が一生懸命、いつも生き急いで見えたのは、先が長くないと知っていたから。 それに、さっきあんなに怒ったのも。 「ああ……」 後悔しても遅いが、本当に悔やまれる。 なんて鈍いんだ、ボクは。事情なんか分からなくても、もっとよく見ていたら、 リシテアさんの抱える悲しさの断片くらいには気づけたかもしれないのに。 「イグナーツ」コンコン、とノックする音が重なって、イグナーツは慌てて顔を上げた。 「まだ起きていますか?」 「り、リシテアさん?」 「よかった。あの、わたし謝りたくて。さっきは、ごめんなさい」 「い、いいんですよ、そんなこと。ボクの方こそ、無神経で。ごめんなさい」 「無神経って?」 「いえ。あの、その…」 くすっと笑う気配がした。肝心な時にはっきりしないんだから、と彼女は言う。しかし、 そこには親しみゆえの柔らかさがあった。 「…よかった。それじゃ」 そばだてた耳に、踵を返す気配と、衣擦れの音がする。イグナーツは、慌てて扉を開けた。 「………!」 「リシテアさん」 「何か訊きたそうな顔ですね。まだ起きているつもりなら…ちょっとお話しませんか?」 リシテアは部屋の中に入ってきた。 灯りの点いた燭台を卓の上に置いて、客人の為に用意された簡素な長椅子に腰掛けると、 「どこまで聞いたのかしら」 と、イグナーツに問う。 イグナーツはベッドの上に畳んであった毛布を持ってきて、膝掛け代わりに広げた。 遠慮しながらもリシテアと並んで座ると、彼女の父親から聞いた事実を、正直に話す。 「そう…」 リシテアはどこでもない遠くを見た。 「わたしね、大嫌いだったんです。わたしをこんな風にした奴らも、 そんな奴らと手を組んでいた帝国も、日和見で助けてくれようともしなかった祖国の貴族たちも。 あの両親が居なかったら、もっと世界を憎んで、人の道を外れていたかもしれない」 「リシテアさん…」 「女神もね、あまり好きではありませんでした。 そこに居るというのなら助けてくれればいいのに、そんな奇跡は無かった。…ただの一度も」 「………」 「だからね、あんたみたいに手放しで女神様に憧れてキラキラしてるのを見ると、 『夢見てるんじゃないわよ』っていうか…腹立っちゃって」 「そうでしたか…」イグナーツは苦笑した。「でも、かつての女神はもう居ません。 大司教は…実のところ『女神の眷属』と呼ばれていたそうですが――人ならざる『白きもの』でした」 「ええ…。結局、最後に信じられるのは自分だけ。わたしもそう思いました。 エーデルガルトは、それを地で行く人で…わたしも彼女に賛同して、付いていこうと思った…」 「エーデルガルトさんを憎いと思ったことは無かったんですか?」 「そりゃ、ありましたよ。実験は帝国の監視下でされていましたからね。 …でも、彼女が同じ苦しみを味わっていたと知って…それは、 私の人生を決定づける上で大きかったです。知らなかったら、今も憎んでいたかもしれない…」 「そうですね。でも結果的に、君とエーデルガルトさんは、とても信頼しあえる間柄になった。 それは、幸運なことだったかもしれません。――エーデルガルトさんから、お誘いがあったんでしょう? 帝都に行けば、長生きできる方法が見つかるかもしれませんよ?」 「可能性は、あるでしょうね。でも…」 「さっきも言いましたが、諦めるなんてリシテアさんらしくないです。 リシテアさんは、いつも可能性を追い求めて頑張ってたじゃないですか」 「諦めてるわけじゃないんですよ。ただね、ここまで来てみると、 もう短命とか長命とか、言ってる場合じゃないような気がして。 とにかく今できることをして、わたしを育ててくれた父と母に恩返しがしたい。そう思ったんです」 リシテアは言った。 「だから、今日のあれは、分かってて言った単なる意地悪です。あんたが あんまり能天気に楽しい話をするから、ちょっと噛みついてやりたくなっちゃったの。 我ながら子供っぽくて嫌だと思ったけど、わたし、背伸びするのはやめたので」 「あはは…ボクもです。そういえば昔、そんな話もしましたね」 「エーデルガルトとは、今でも手紙のやりとりをしてるんです」 と、リシテアは話題を少し変えた。この家はバルタザールと彼の弟さんが世話してくれたものだが、 一方でエーデルガルトも、落ち着くまで何かと面倒を見てくれたのだという。 「体調も気に掛けてくれて、よく効くというお薬を送ってくれたこともある。ありがたいことです」 「じゃあ…帝都に行かなかったのは、どうして?」 イグナーツの問いかけに、リシテアはほんのりと苦笑した。 「気に掛けてくれるのは嬉しいけれど…正直、重かったり。 何もかも水に流して仲良くするには、いろんなことがありすぎて」 「………」 それは、そうかもしれない。 幼少期に、耐えがたい苦痛を味わったリシテア。 領内から川を挟んで見えるのは、敵だったはずの帝国の街だ。 そして、橋の向こうからやってきた帝国軍と、恐ろしい魔道師たちの影――否応なく思い出したのは、 一度や二度ではないだろう。 安易に同情の言葉など告げたらまた傷つけてしまいそうで、イグナーツは迷った。すると、 「ごめんなさい…嘘です」押し殺した声がする。 「え?」 「わたし、本当は…たぶん、今でも憎いんだと思います。 帝国も、エーデルガルトも。帝都になんか行ったら、堪らなくなる。だから嫌なんです」 「……」 「お母様と同じ色だった髪もお父様譲りの目も…こんな、お化けにみたいになってしまって。 昔は、お化けの話を聞く度に怖かった。正直、今も苦手です。…思い出したように夢を見るんです」 イグナーツは思い出した。士官学校に入学したての頃「お化けが出るぞ」と級長や仲間たちが からかう度に、リシテアが怒って「怖くなんかないですから!」と否定していたのを。 それこそ怖がっているのが見え見えで、あの時は年相応の愛らしさを微笑ましく思ったものだったが。 実際はこんなに苦しんだ背景があったのかと思うと、今更ながらに胸が痛む。 「『お前も仲間だから』って――お化けが、あの実験で死んでいった人たちを引き連れて、 わたしを迎えにくるんです。引っ越してきたばかりの時ね、村の子供たちが、幽霊の噂をしていたの。 何て恐ろしいんだろう、と怯えていたら――それは、わたし自身のことでした。笑っちゃうでしょ」 胸にしまっていたことを話し出すと全部吐き出してしまいたくなったのか、 堰を切ったように、リシテアは畳みかけた。 「わたし、嘘だらけなの。…父と母には、幸せな余生を送ってもらいたい。それは本心のはずなのに、 あんたを見てたら思ってしまったの。ここを出て自由に生きられたらどんなにいいかって…。 羨ましいんです。だってわたしは、もういつ居なくなってもおかしくない。 あんたみたいに未来を切り開く力も時間も、もう残されていないんですから」 「リシテアさん」 「生きることを諦めないって、エルとも約束しました。 諦めたつもりなんか無かった。だけど、これ以上どうしたらいいか」 「リシテアさん」 「怖いんです。夜眠ろうとして床に就くと、このままもう目覚められないんじゃないかって… 父と母を置いて、わたし一人、誰にも会えずに――!」 「リシテアさん!」 イグナーツの呼びかけが、リシテアを現実に引き戻した。 穏やかで温かな雰囲気を湛えた茶色の瞳が、強い意志を持ってリシテアを見つめてくる。 「リシテアさん…頑張りましたね」 イグナーツは言った。 「もう、いいんです。ひとりでそんなに頑張らなくても、いいんですよ」 「イグナーツ…」 不覚にも、目の前が滲んだ。 「頼ってください。そう言ったでしょう?昔『何かあったら頼って欲しい』って」 「わたし…苦手なんです、誰かを頼るの」 「知ってます」 「甘えるのも…苦手なんです。嫌っていうか…子供っぽい気がして」 「それも知ってます」 「お試し期間は終了したんじゃないんですか?」 「はい。ですから、それを踏まえて、これからも…お気に召したなら、頼ってください。 それとも――ボクじゃ役者不足ですか?」 彼女がこの小さな肩に背負ってきた物を思えば、自分では不足かもしれない。 イグナーツの従来の自信のなさが、こんな時に限って顔を覗かせる。 だが、 「――」 リシテアは、イグナーツの袖をきゅっと掴んだ。彼からは見えないように、顔を伏せる。 「リシテアさ…」 華奢な体を寄せた。小さな頭をコツンと預ける。 「ありがとう。これからも、頼りにさせてもらいます。――いま少し、こうしていても良いですか?」 「…はい。もちろんです」
それからしばらくの間、 他所から来た『眼鏡の画家さん』が、村外れの家のお嬢さんと一緒に行ったり来たりするのを、 村の住人たちは見ていた。 とはいえ、宿の部屋はそのまま借り続けていたが。 「おはようございます」 「おんや、リシテアお嬢さん。画家さんなら今日も籠もってるよ」 イグナーツは、リシテアの父から依頼された『家族の肖像』を誠心誠意込めて仕上げた。 肖像の中のコーデリア一家は幸せそうに微笑み、 リシテアの髪や瞳は色が抜けた今のままだったが、嫌な感じはしなかった。 リシテアの容姿を描くのは難しいようで、イグナーツが苦心していたのを思い出す。 「この髪。切って、差し上げましょうか」と申し出ると、彼は慌てて断った。 「いっ、いいです! あ、いや、だめです! もったいない!!」 完成した絵を見た父母は「良い絵ができた」と嬉しそうに笑った。 ――両親がこんな風に笑うのを見たのは、何年ぶりだろうか。 作者本人も満足そうだった。 「君の、この髪。やっと納得いく色合いになりました」 そう言って笑った。側で完成した絵とリシテアを見比べていた彼は、 リシテアの伸びた髪の先っぽをそっと摘まんでから、我に返って慌てるのだった。 「すっ、すみません!」 「いいですよ。もう気になりません。イグナーツなら」 「そ、そうじゃなくて…」 「? やっぱり、はっきりしない人ですねぇ」 彼と居ると笑顔になる自分や両親が居て、 家に太陽のような明るさと暖かさが満ちてくるのだった。 その後すぐにまた村を発つのかと思ったが、 イグナーツは「急ぎの用事もありませんし」と、暫く村に滞在することを決めた。 仲良くなった村人たちをモデルに、彼は次々とデッサンを仕上げていく。 元・伯爵家の令嬢だったリシテアには地味だと思える題材も多かったが、 イグナーツの絵には不思議な魅力があった。 「この色、そのまま写し取れたらなぁ。絵の具にして持って帰りたい」 ある時リシテアが案内した場所で、空を見上げたイグナーツはうっとりと呟く。 「青を塗れば良いんじゃないんですか?」 「自然の色っていうのは難しいんですよ。空の青も海の青も、季節や時間帯によって変わるでしょう? 昼間の空は、言葉で言うなら『青』だけど――青にもいろいろあります。 たとえばこの、勿忘草の青とは違うでしょう。 …あ、今日のリシテアさんの洋服とは似てますね。ボク、この花好きなんですよ」 「ふうん…確か、騎士物語が名前の由来になっていましたね」 「ああ、そうです。恋人に花を摘んで捧げようとした騎士が、 川に落ちて『私を忘れないでほしい』と言い残して亡くなったっていう…。 恋人は騎士の墓前にその花を手向け、それが名前の由来になったんだそうです」 「迂闊な騎士ですね。恋人は、花なんかより騎士が帰ってくるのを待ち望んでいたでしょうに」 「でも、ちょっと素敵だと思いませんか?」 「あんた、ロマンチストですもんね」 イグナーツは、ある程度スケッチを描き溜めてはキャンバスに起こして絵を仕上げる、 といった作業を繰り返していたが。 「じゃあ、また次の『竪琴の節』――じゃなかった、『五月』に」 ある程度の枚数絵を完成させると、あっさり出ていったのだった。 村人ともすっかり馴染みになった彼は、 『リシテアお嬢さんをお嫁に貰うんだろう』と噂が立っていたが、その予想は空振りしたようだ。 村の雑貨屋や宿には、彼の残した絵が飾られた。 無論、リシテアの家にもだ。 どの絵にもイグナーツの素直で温かい人柄が表れている。 彼は美しいものを捉えて描写するのが得意だった。 クパーラの里があるという方面を描いた山並みは壮麗で、 彼が持って帰れないかと言っていた空の青も、本物に勝るとも劣らぬほど美しく仕上がっていた。 「これ…完成したんですね…」 「ああ…そうそう。見事なもんだよねえ!」 宿の主人はリシテアに言い、顔を見て思い出したようにもう一枚絵を出してきた。 「お嬢さん。これ、あんたでしょ」 リシテアは目を見張った。 それは小さな水彩画だったが、描かれているのはリシテアが案内した場所の一つだった。 見渡す限りの勿忘草の花畑の中に、虹色の羽を持つ妖精が佇んでいる。 「……!!」 ざあっ、と風が抜けた。…いや、正しくは、そんな気がしただけだ。 イグナーツの残していった絵画は、彼の的確な審美眼と繊細な筆使いも相まって、 えもいわれぬ美しさを実現していた。 ――『景色はどんな機械で写し取るよりも、人間の目で見るのが一番綺麗なんだそうですよ』 彼の目が捉えた美しいものを、リシテアは今、共有することができたのだった。 何という才能だろう。自分が何一つ見出せなかった――長いこと見逃していたものを、 イグナーツは、すくい上げて見せてくれたのだ。 空の青。 山を渡る風の爽やかさ。 花の色、草木の緑の匂い。 陽の光の明るさと、暖かさ。 水の涼やかな音、口に含んだ時の甘さ。 見た人にさえそれを呼び起こさせる再現度に、リシテアは感動した。 そして。 ――『綺麗ですね』 リシテアと一緒に同じ景色を見て感動したイグナーツが、こう言ったのを思い出す。 もう何度も見てるじゃないですか、よく飽きないわね。…振り向いたリシテアに、微笑んだ彼。 風に揺れたリシテアの――長い髪を、朝焼けの色だと称した。 身の毛もよだつ実験で、お化けのようになってしまったとリシテアが悲観し嘆いていた、この白い髪を。 「妖精のおねえちゃん!」 宿を出て村を歩いていると、小さな女の子が、そう声を掛けてくる。 ――『綺麗ですね』 あの言葉が紛れもなく自分に向けられていたのだということを、今知った。 優しかった、笑顔。 「おねえちゃん?」 「………」 この気持ちを、どうしたらいいんだろう。――顔が、熱い。
最初のうち一年は何て長いんだろうとすら思ったが、 日々の暮らしに真面目に向き合っていれば、季節は足早に過ぎていった。 途中、熱を出して寝込むこともあれば、貧血で動けない日もあった。 それでも、リシテアは何とか生きていた。 次の『五月』に再会しようという、イグナーツの言葉に励まされて。 日も沈んだ夕刻。 「彼は、どうしているかね」 ふと、父親がリシテアに言った。 「そういえば、去年の今頃でしたわね…そろそろ来てくれるかしら」 「わたしに訊かないでください。わかりません」 実際にはぴったり一年ではなく、もうひと月遅れだ――旧セイロス歴で言えば、『花冠の節』 …頼ってください、と言った割に、イグナーツからは音沙汰も無い。 木々が水を蓄えて伸び伸びと育つ気持ちの良い時季。 心地よい風とは逆に、リシテアは浮かない顔をしていた。 あの時の会話は、きっと一時の気の迷いだったんだわ、と諦めている。 「……」 不覚だった。弱い自分を、あんな風に見せてしまうなんて。 リシテアが自己嫌悪に陥った時…トントン、と玄関の戸を叩く音がした。 リシテアたちは揃って顔をそちらに向ける。 「あなた」 「噂をすれば、だったりして…な」 「父様。そんなわけないでしょう」 言いながらも、リシテアは胸の動機を抑えることができなかった。 返事をして扉を開けると、そこには、郵便配達人が居た。 「お届けものです」 配達人は、息を切らしている。 スケッチブックと同じ大きさと厚さの小包に、手紙が挟んであった――差出人の名は、 イグナーツ=ヴィクター。 「リシテア」 慌てて封を開ける。母親が引き受けて開けた小包は、肖像画だった。 「………!」 「まあ」 勿忘草わすれなぐさを手に微笑む、リシテア本人の肖像だ。 一年前、冗談半分でリクエストしたのを、リシテアは思い出した。 リシテアは百合が好きなので、描くなら百合をモチーフにしてくれと頼んだのだが。 ――『リシテアさんは色白だから、こういうのも似合いますよ』 趣味全開でそんな返答をもらったのだった。 添えられていた手紙には、今近くまで来ていること、数日中にはこちらへ着けるだろうとの 連絡があった。会ったら、伝えたいことがある、とも。 そして、勿忘草を押し花にした、可憐な栞が挟んであった。 「…そろそろ、こちらへ着くそうです」リシテアは、父母に報告した。 「手紙の消印が隣村だから…今日じゃないのなら、明日には来るのかしら」 ところが。配達人は、ゼエゼエしながらこう言った。 「昨日、土砂崩れがあったろう? あの前後に、近くで眼鏡の兄さんを見たって人があって…もしかしたら」 「なんだって!?」 リシテアは真っ青になった。 「――そんな…」 信じられない。これじゃ、『私を忘れないでくれ』と言い残して死んでいったという騎士の物語を、 そっくりそのままなぞるようなものじゃないか! 「リシテア、だいじょうぶよ、気を確かに持って」 「ちょっと、行ってくる!」 「父様! わたしも行きます」 郵便配達人に連れられ慌てて走り出た父娘の元に、坂の下からまたしても人影が現れる。 こんな時に、なんて千客万来な――苛立ちを隠しきれないリシテアは、抗議してやろうとした。 …だが。 人影が、こちらを見つけて走ってやって来るのが、足音で分かった。 灯りを翳すと、何かがきらりと反射する。 「こんばんは!」 何とも人好きのする笑顔を浮かべてやってきたのは――あれほど待ちわびたイグナーツだった。 「…っ」リシテアは半泣きで詰め寄り、「あんたって人は!」と怒る。 「わわっ!」 「紛らわしいこと、しないでください! 心臓が止まるかと思ったでしょう!?」 「す、すみません…。え?」 「…良かった、無事だったか」と、リシテアの父が笑った。 えぐえぐと泣き始めたリシテアに、イグナーツは困って頭を掻く。 「イグナーツのばか! なんて鈍くさいんですか、あんたは! タイミング最悪です!」 「さ、最悪…?一体何が」 「土砂崩れがあってね。君が巻き込まれたんじゃないかと、みんなで心配していたんだよ」 「えっ、ああ――その話ですか。心配掛けてごめんなさい。 丁度道が塞がっちゃったって聞いたものですから、 地元の猟師さんと一緒に、別の道を辿ってきたんです。 回り道になるかと思ったけど、距離はそっちの方が短かったみたいで」 「そうか。ともかく、よかった。家にお入り」 「ありがとうございます。あ、あのう…」 「ん?」 「今日は、リシテアさんと…お父様とお母様にもお話があって参りました」 イグナーツは、おどおどと言った。 その後、劇的――なのかどうなのか分からないが、 お決まりのやりとりがあって二人の結婚が決まったのは、言うまでもない。 リシテアとその両親の「良いのか」という問いに対して、 イグナーツは、はっきりと頷き言い切ったのだった。 「はい。時間の長さは関係ありません」 恩師について行くと決めた、その時のように。
「酷いですよ」 リシテアはむくれた。 一年前と同じように、二人は長椅子で語り合っていた。だが、今日は月明かりがある。 「本当にすみませんでした、心配かけて」 「それも、ですけど…父と母に言う前に、わたしに直接言ってほしかったです。 しかも挨拶に持参したのが絵?もっとこう…他にあるでしょ」 「あ…」イグナーツは慌てて、懐をまさぐった。 「そうでした。朝を待たずにお邪魔したかったのは、一刻も早くこれを渡したかったからで」 「えっ」 「でもこういうのは…どうせなら、ロマンチックに演出したいですから。 ――同窓会でもあって、女神の塔に行けたら良かったんですけどね」 彼が出したのは、綺麗な細工の、小さな箱だった。――リシテアは呆気に取られた。 ぱかりと開けて出てきたのは、素朴な指輪。 だが、白いプラチナに、青色の宝石で花をあしらった飾りが付いている。 これを手に入れるには、お金も時間も掛かったに違いない。 「あんた、どこで…どうやってこんなものを」 「絵を描いて、売って…あちこち回っていたので、ちょっと時間が掛かっちゃいました。 待たせてごめんなさい」照れくさそうに、イグナーツは笑った。 「ボクが居ること、『忘れないでください』。ボクにできることは、多くはないかもしれませんけど…… これからも、もっと頼ってくれたら嬉しいです。一緒に、綺麗な景色を沢山見ましょう」 イグナーツは言い、リシテアの前に片膝をついて、おずおずとプロポーズの言葉を口にした。 親の意向で騎士になるはずだった青年は、美しい景色と温かな人々の暮らしを絵筆で写し取る。 素直な心で誠実に美を追い求めた彼が、いつしかリシテアを救ってくれたのだった。 「もう…」リシテアは、困ったように笑った。「一生、頼りにしますからね?」 「はい!よろしくお願いします」 やがて、慎ましくも幸せな結婚式が開かれた。 リシテアは真っ白なハンカチに大好きな白百合の花を刺繍して、嫁入り道具として持参した。 新郎には勿忘草じゃないのかと言われたが、 リシテアは、わたしはこの花が好きなの、と主張する。 理由は他にもあった。 ドレスもそうだが、花嫁の身につける白は「あなたの色に染まります」というメッセージを含んでいる。 頭には花冠ではなく、新郎が見立てた髪飾りと、村の職人が織り上げたヴェールを着けた。 女神は居なくなってしまったが、人の心に神は宿る。――挙式を取り仕切った村長の そんな話が、人々の心に残った。 そして、風や光すら写し取ると言われた青年画家が、 美しき『花嫁の肖像』を発表するのはもう少し後だ。 また、彼の代表作『女神の肖像』が完成するのは、更に先のことである。 薄幸の才媛と言われたリシテアが、 後にアドラステア帝国の皇帝エーデルガルトに送った手紙には、こうあったそうだ。 ――『わたしは、生きることを諦めたわけではないのです。 ただこの命を、美しい色と情景を追い求める彼に捧げたいと思ったのです』 イグナーツは後に『色彩の旅人』と称されることとなる。 その彼が、愛する妻といつまで添い遂げたのかは、定かではない。―― 「…。行こうか」 「ええ。でも、どちらまで?」 「約束した場所。どこまでも続く地平を、見せてあげるよ」 朝焼けの色を映した長い髪が、風にふわりと揺れた。 |
||||||||||||||||
 |
 日陰に咲く花へ |
 小説ページへ |
 サイトトップへ |