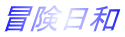
| 第1巻:風の呼び声 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光の四戦士 | |||||||||||||
|
「うわあぁぁぁ!!」 天と地をひっくり返すかと思われる悲鳴が四人分、暗闇に響き渡った。 堅い岩盤がそれを方々で跳ね返して、奇妙な余韻を残す。 「…。…う~、痛ててて…」 少年は、何が起こったのか判らぬまま、周囲を見回した。薄暗い。 ぱちりと開けたエメラルド色の瞳に映るのは、闇ばかり。 短い髪は埃だらけで、いつもより更にぼさぼさだ。 痺れた頭に、どうにか考えを巡らしてみる。 村の守り神だと聞かされてきた『風のクリスタル』──それを探しに来たんだ。 …ところが、山腹にあったクリスタルの祭壇は、崩れるどころか ほぼ影も形も見当たらない有りさま。 代わりにあったのが、下層にぽっかりと口をあけた洞窟の入口だった。 丁度、祭壇の真下だ。位置的にも、クリスタルが埋もれているとしたら、この中だろう。 「『祭壇の扉まで』だったよな!」 「これ以上は危険だ」と反対する兄と弟を半ば強引に引っ張る形で、 また、末の妹は口車に乗せてそそのかし、彼はそこへ入ったのだった。そして… いよいよ意識がはっきりしてくると、少年は自分の怪我を確かめた。 腕はちゃんと曲げられる。手も、足も、肝心要の頭も…傷ひとつ無いことが判ると、 我ながら感嘆してしまった。 ナイフも薬の入った袋も、ちゃんと腰のベルトに括りつけてある。 探険には無くてはならないものだ。 火熾しの道具、ランプ、切れ味の良さそうな長剣、果ては祖父が大切に保管している いかにも貴重そうな瓶詰め… 四人で手分けして、わざわざ大人の目を盗み、見つかるか否かギリギリの危険まで冒して 拝借してきたのに、無くしてしまっては元も子もない。 見ると、少年から少し離れた場所に、あと三人…彼の兄妹も、ちゃんと居た。 「落っこっちゃった…」 弱虫な弟は、途方に暮れていた。 まさか落とし穴があるなんて。いや、地震で足下が脆くなっていたんだ。 一方、兄は天井を仰ぎ見て、情けなく笑った。 「やれやれ、今のはちょっと効いた。…まいったな」 見れば、兄の腕には派手な擦り傷があった。利き手でなかったのが不幸中の幸いだ。 白いシャツの袖は破けて、血が滲んでいる。 「キャンディ」――少年は、まず兄に声を掛けた。 「ムーン。大丈夫か?怪我は…」 「俺は、何ともない。とりあえず上手いこと…っていうのかな、落ちたからさ。 ポポとアリスは?」 「大惨事よ!どうしてくれるのよ!」 妹のアリスは、泥だらけになったエプロンドレスを気にしながら怒鳴った。 心身共にかなりの衝撃だった筈だが、既にしゃんと両足で立っている。 こちらは怪我の心配はなさそうだ。 彼女は洞窟内を検分し、ぱたぱたと足音も忙しく歩き回る。 少年――ムーンは、その後を追った。 「おいおい。大丈夫かよ、こんなとこまで来ちまって」 これを聞いた妹は、いよいよ本気で怒った。 「何言ってんのよ。言い出しっぺは、あんたでしょ! あんたがあれ以上進まなければ、 穴に落っこちることだってなかったのよ。今頃、村に帰ってたわ!」 「なっ…」ムーンは、つい『売り言葉に買い言葉』で応じてしまった。 「お前らが一緒に落ちなきゃ良かったんだ。 何も、『底まで一緒についてきてくれ』なんて俺は頼んでないね!」 些細な一言がきっかけで始まってしまった言い争いは、止める間もあらばこそ。 あれよあれよと、熱を帯びていく。 「僕だって止めたよ。嫌だって言ったのに。ムーンが聞いてくれないから」 弟のポポも、そうキャンディに溢した。 晴れた夜空にも似た群青色の瞳が、潤んで今にも泣き出しそうになり、 後ろで束ねた短いしっぽ髪も、心なしかしゅんと萎れている。 聞き逃せば良かったのに、ムーンはこれにも拳を固めた。 「ならお前、もっとしっかり止めろよな。何かにつけて、ぐずぐずしやがって。 言いたいことあるならハッキリしろ、ハッキリ」 「…っ言ったら、ちゃんと聞くの!?」 「ほらやだ、すぐ力で解決しようとするの」 「お前は少し黙っとけ!…ポポ、文句があるなら言ってみろよ」 「ぼ、僕…!」 一方、長兄キャンディはくっと奥歯を噛み、内心頭を抱えた。 腹の底に押し込んだ苛立ちが募り、渦を巻く。 「おい…」 やめよう、と彼は静かに声を絞り出した。 ――今ここで喧嘩をしても、何も解決しない。 「お前ら、いつも鈍いんだよ。 誰か一人でも無事なら、助けを呼んでくることだってできたはずだろ?」 「鈍くて悪かったわね!お馬鹿の誰かさんよりマシよ!」 「誰のことだよっ」 「自分の胸に手ぇ当てて、よぉーく考えてごらんなさい。 ここまで言って分かんないようじゃ、もうダメよね」 「…っこの野郎…!」 ――気持ちは分かる。いきなりこんな処に落ちて痛い思いをして。 「あんたの馬鹿力で殴られたらどうなると思ってんの?」 「知ったこっちゃないね! てか、『馬鹿』は余計だ、余計!」 「あ~ら、そうかしら?」 ――みんな同じだ。誰かのせいにしなきゃ、やってられない。 冷たい不安に押し潰されそうになる──暗闇は、人を無条件で不安にするから。 「…何よ、やる気?」 「面白れぇ、受けて立つぜ」 ――気持ちは分かるよ。だけど! 「やめーーっ!!」 場を揺るがす大音声。叫んだのは誰あろう、キャンディだ。 思わずびくっと肩を震わせて、あとの三人が振り返った。 「喧嘩してる暇があったら、出口を探せ!」 凛々しい声はしかし怒気をめいっぱい含んで、周囲の岩がそれを増強させる。 ムーンとアリスはぴたりと止まり、慌てて口を噤んだ。 それまで静かに成り行きを見守っていたはずの──決してそれだけではなかったが── 長兄は、無言で弟たちの間に割って入った。 いつも雲間に射す陽光のごとく細められる黄金色の瞳が、 今は刃のように鋭くなっている。 普段穏やかな兄が怒声を張り上げたとあって、これは即座に効いた。 訪れた静寂の中、すん、とポポが鼻をすすった。 「ムーン、松明はあるか?」 「おう、こっちに」 火打ち石と木屑、油を染みこませた布を使い、 キャンディとムーンが協力して火を熾した。 周囲を温かな光が満たすと、誰もが抱えていただろう不安が薄れてゆくから不思議だ。 安心した途端に、ぐぐう、とムーンのお腹の虫が鳴いた。 「まったく、緊張感のカケラもないのねぇ」とアリス。 「仕方ねーだろ」空腹を抱えた当の本人は、最もらしい顔つきで答えた。 「人間、腹が減るときゃ減るんだよ」 ――…ぐるるるる……。 呼応するかのように、再び音がした。 「ほら、また!」 アリスが「そら見ろ」とばかりにムーンを振り返る。 だが、ムーンは「今度は俺じゃないぞ」と首を横に振る。 視線が集まると、キャンディは慌てて首を横に振った。 自然、二人の視線が自分の方へ向けられたので、ポポも慌てて否定する。 「ちっ、違うよ!」 だいたい今のは、お腹の音にしては変だ。 どちらかと言えば、獣の唸り声に近いような── 「…あ……」 突然ポポの表情が変わったのを見て、ムーンとアリスは、きょとんとした。 大きな瞳は驚愕にめいっぱい見開かれ、「どうしたの?」と訊ねる間にも、 じりじり後ずさりを始めている。 二人の方を示した人差し指が小刻みに震え、一カ所に定まらない。 「―――」思わず振り向くと、その先には。 「!」 身も凍る、無数の黄色っぽい光が点っていた。 …いや違う。これはただの光なんかじゃない。何かの、目──! 「──ゴブリン!?」 「うわああ!!」 その悲鳴が、魔物たちの突撃の合図になってしまったようだ。 キャンディが剣を抜き前に出るのと、角のある小鬼が飛びかかってくるのがほぼ同時。 ポポに突き立てられようとしたナイフは、間一髪、兄の長剣が代わりに迎え撃つ。 一方、ムーンは咄嗟に妹を背後に庇い、手にした灯火を盾代わりに振りかざした。 運良く炎が敵の顔面を掠め、そいつが怯む。…今だ! この機を逃さず、空いたもう片方の手でナイフを抜き、構える。 敵が持っているのも、同じような小ぶりのナイフだ。 どこからこんなものを、と思う間にも、炎を照り返した敵の刃が、橙色の弧を描く。 ──ナイフ同士のぶつかり合う音。 金属音は剣のそれに比べれば軽いが、敵の繰り出す刃は一撃一撃がずっしり重く、 全く容赦がない。受けとめると、腕が、身体が、ぎしぎし軋んだ。 全身でしっかり踏ん張らないと、弾き飛ばされてしまいそうだ。 もっと姿勢を正して。そうだ、もっと踏み込め。…村での稽古を思い出す。 だが、これは稽古とは違う。こいつらは、ほんとの本気で俺たちを殺そうとしている。 当たり前だ、これは実戦なのだから…! ムーンの心を察知して、ありがたくないことに身体がそれに従った。 ひやりとしたものが背を伝う。何とも嫌な感じが全身を駆ける。 ──一瞬、あってはならない隙が生まれた。 敵のどちらかといえば猫に近い瞳が、獲物を狩る喜びにギラリと輝くのが分かった。 ──やられる! 「きゃあああ!!」 突如、背後で甲高い悲鳴が上がった。 …すると。その直後、両手ほどの大きさもある石くれが…何と、目前の敵の顔面に 命中しているではないか! アリスがたまたまそこら辺に転がっていたのを拾って、渾身の力で投げつけたのだ。 見事に一発命中、ストライクだ。 打ち所が悪かったのか、威力があまりに凄まじかったのか。 あわれ小鬼は、そのまま卒倒する。 大事な頭の一角が欠けなかったのがせめてもの救いだろう。 「ナーイス。やるじゃん」 「…え、嘘。当たっちゃった?きゃ~、やったあ♪」 ぴょんぴょん跳ねる妹は実に嬉しそうだ。 ムーンは、感心しながらも正直、愕然としていた。 防衛本能の勝利とでもいうのだろうか…。何にせよ、 女の底力ってやつは、ナメて掛かると怖い。 ちらとそんなことを考えながら、もう一匹に向き直った。
キャンディは二匹のゴブリンを同時に相手しなければならなかった。 こちらも剣術の心得はあるものの、日頃の練習とのギャップに戸惑いを隠せなかった。 何せ魔物は、本能で狩りをする。 時に予測のつかない反応をするから、人間相手を想定した型通りの剣術は、なかなか 上手く通用しない。その上、一度に二匹とあっては…! シャアッ! ──威嚇する猫そっくりに毛を逆立て、声荒く突っかかってくる小鬼たち。 一方の攻撃をかわしたと思った側から、もう一方が仕掛けてくる。 血の臭いにも敏感なのか、傷ついた左腕を狙ってくる。 懸命に受け流しながら反撃の機会を窺うキャンディだったが、俊敏な相手の動きに ペースを乱され始めていた。 無意識に自分の息づかいを聞きながら、彼は思う。 ──そうか。ここはもう、彼らの領域なんだ、と。 この前の地震。それが間違いなく『何かを引き起こした』 いや、逆か…地震があったから、『何かが起こった』? どちらにしても、今まで干渉し合わなかった人間と魔物、 双方の境界線が曖昧になった。──そう感じる。 これまで、魔物という存在は人々の間で認知されていたが、それは英雄譚と共に、 伝承やおとぎ話の中だけの存在だった。それが今こうして目の前に居る。 彼らは日増しに凶暴になっていると聞く。 実際に、最近では人里に現れては畑を荒らし、家畜を屠り、物を奪っていく。 四人が暮らすウルの村でさえ、例外ではない。 (世界は滅びようとしているのか) 地震、村の騒動、魔物、大人たちの心配顔。 祖父の険しい声、忙しげな足音、使者、手紙。 祭壇、クリスタル──世界を支える四つの柱が、地下に沈んだ。 様々なことが一陣の風の如く胸を通り過ぎていき、最後に冷たい予感が石となって、 キャンディの胸の中、ことり、と落ちる。 まさか…まさか!でも、大人たちの話が本当だとしたら。 世界はこれから、どうなってしまうんだろう? 「──く、…はっ…」 熱い痛みが走った。敵に左肩をやられたのだ。しかし、それを気にしている暇はない。 どうにか切り抜けなければ…そして、無事に戻って報告をするのだ。 キャンディは、手にした剣を振るった。 「帰れ……!」――元居た処へ。 彼は正面の敵と打ち合うように見せかけ、くるりと反転、背後に来ていた奴をなぎ払う。 そのまま動きの反動を利用して、壁を背に体勢を立て直す。 「…」息も荒いまま、剣を構え直した。その間にも、敵はじりじりと間合いを詰めてくる。 傷が痛む。しなやかな銀髪が、既に汗を含んで乱れていた。しかし彼の双眸は、ひたと 敵を見据えている。 ここは駄目だ。『風』の祭壇は。あれを壊したら── 「ただじゃおかない!!」 ──キャンディは、一直線に剣を突き出した。
ポポは震えていた。岩の影に隠れたまま。 「助けなきゃ」と思うのに、動くことができない。 魔物は四匹、こちらも四人。数では互角だが、獲物を狩ることを歓びとする魔物と、 実戦経験は皆無の自分たちだ。 みんな必死で戦っているけれど、不利なのは目に見えて明らかだった。 これでは勝機はあり得ない。あるはずがない! 妹の悲鳴が聞こえた。その途端、ポポの心に、じっとりと恐怖が湧き起こってくる。 今まで懸命に抑えつけてきた恐怖が。 やっぱりムーンの誘いになんか乗るんじゃなかった。 自分たちみたいな子供が、大人の代わりにクリスタルの無事を確かめようなんて 無茶だったんだ。 心が後悔でいっぱいになった時、突然ぐいと腕を引かれ、ポポの意識もまた現実に 引き戻された。擦り傷と切り傷でいかにも痛そうな左腕が、必死に彼を引っ張るのだ。 「キャンディ」 大丈夫?と訊ねる暇は無かった。 「逃げるぞ!」 萎(な)えかかった足が、ここから逃れたい一心で呼びかけに応えた。 長兄の声を聞き、ムーンとアリスも走り出す。 と、妹の背に斬りつけようとした一匹に、 「プレゼントだ!」 ムーンが熱い炎を押しつける。 背後でぎゃあっと悲鳴が上がるのを聞きながら、彼もまた、振り向かずに走った。 虚ろに開けた闇の中を、四人は必死に駆けた。 どのくらい走っただろう。 追っ手が来ないと分かると、四人共その場にへたへた座り込んでしまった。 「…。何なんだよ、今のは…」ムーンが、ぜいぜいと言葉を継いだ。 「あんなのが居るなんて…聞いて、ないぞ……」 「『危険なところ』か…はは」キャンディは力無く笑い、ふとその笑顔を消す。 「確かにそうだ。甘かったな…」 「もうやだ、絶対やだ!今度会ったら間違いなくやられちゃうよ」と、ポポ。 「んじゃ、そろそろ帰ろうぜ」 「すんなり帰れたら苦労しないわよ!安全な道も出口も分からないのに…ああ、 あんたのせいよ。あんたのせいだからね!」 アリスは苛立ちを遠慮なしに言葉にして、ぶちまけた。 「痛て、痛ててて!叩くなよ」 「やめ…、…っ」 例によって止めに入ったキャンディが、顔を歪めた。 「キャンディ!」 痛々しい左腕を見て、ポポが声を上げる。アリスは、はっと我に返った。 彼女は、簡素な布製の肩掛け鞄を開け、中から清潔な白布と消毒薬を取り出す。 キャンディは、自分で持ってきた水筒の水で、まずは肩から腕にかけての傷口を洗った。 綺麗になった傷口に消毒薬を塗ってもらうと――滲みる。 ポポが、キャンディと一緒になって痛そうな顔をする。 確かに痛いが、結局痛みを味わうのなら、治りが早い方がいい。 堪えて、上から傷薬を塗り重ねる。 アリスが、今度は包帯を取り出し、しっかりと巻いた。 「きつくない?」 「うん、ありがとう。ポーションもあるかな?」 ポポが慌てて応じる。 取り出した銀色の小瓶は金属製で、中には一服ずつ、煎じた薬草の粉が入っている。 これを口に含み、皮製の水筒に口をつけて水と一緒にぐっと飲み下す。 これを飲んでおくと、怪我をした時や風邪をひいた時の治りが早いのだ。 今度は、ムーンがキャンディの代わりに苦そうな顔をした。 「何だか疲れちゃったね…」と、ポポ。キャンディがそれに同意する。 「そうだな…僕もだよ。少し、このまま休んでいかないか」 誰からともなく溜め息が漏れる。それが皆の、『賛成』の返事代わりだった。
休息を取った四人は、再び歩き出した。 明かりを失ってしまったから、壁づたいに足下を気遣いながら歩かなければ ならなかったが、休憩後の四人の足取りは強く、歩調も速かった。 あんな魔物がここに居ると分かった以上、出来る限り早くここを出たい―― そう誰もが思っていた。 幸い魔物の気配はもう無く、聞こえてくるのは自分たちの足音と、 時折奥から流れてくる、冷たく乾いた風の音だけだ。 ──ここでは、時間さえ止まっているのかもしれない。 ポポは漠然とそんな考えに囚われていた。 ずっと閉ざされた処に居るからだろうか、時間感覚が狂ってしまいそうだ。 …と。 「腹減った…」 再び、ムーンの空きっ腹が鳴った。 「あんた、さっきからそればっかりね」 「きっと、帰ったら夕飯の時間くらいだよね」 と、取りなすようにポポは言う。 「おっ、そりゃ丁度いい!」 「…そう上手く行くかな?きっと、まずはおじいちゃんの説教だよ」 「風のクリスタルを探しに行ったなんて、言わなきゃいいんだ」 「言わなくたって、決まりを破って村の外に出たことは分かるよ。『罰として食事抜き』とか」 …あり得る。 「育ち盛りにはキツイぜ…何だか帰りたくなくなってきた…」 「じゃ、残るか?」 「滅相もない!帰ります」 急に敬語にするムーンである。それにしても、と彼は思った。 祖父のトパパと来たら、いつもムーンの計画をものの見事に見破る。 『壁に耳あり障子に目あり』というが、あれは人智を越えている。 単に勘が鋭いのか、それともお得意の魔法か。 魔法なのだとしたら、遠い昔に名を馳せたどんなに偉大な魔道師も、祖父には敵うまい。 そして…そんな祖父に魔法を教わっているポポも、実は結構侮りがたいのかもしれない。 「ん?」 魔法。そうだ、その手があったじゃないか。 「そういえば、お前ら魔法使えるようになったんじゃなかったっけ?」 ムーンは、ポポとアリスに言った。 「…まだだよ。やっとおじいちゃんから許可が出て、 明日〈魔法珠〉を貰えることになってるんだ」 「一日早かったら良かったのに。そしたらさっきだって、チョチョイと」 「そうすぐに上手くできるか分からないよ。魔法だって、練習しなきゃ上達しないんだから」 ポポは自信無さそうに、うつむいた。 「呪文唱えれば、攻撃も回復も一瞬だろ?」 「これだから素人は困るわ」 言ったのはポポではなく、アリス。 やれやれ、とこれ見よがしに肩を竦めると、彼女はすまして得意そうに右手の人差し指を立てた。 「そんな簡単なものじゃないの。ちゃーんと呪文の意味を理解しないと」 「あ??」 「魔法は安易に使っていいものじゃないんだ。 大きな力を動かす分、もし使い方を間違えると、大変なことになるんだから」 分かったような分からないような理屈だ。 教科書をそのまま読むような二人の言い回しを、ムーンとキャンディは正反対の表情をして聞いた。 祖父トパパが教えてくれている魔法は、目に見えない力を形にして、万物に様々な効果を及ぼす。 ポポの習っている〈黒魔法〉は攻撃性が強く、主に自然界の精霊の力を借りる。 対してアリスの〈白魔法〉は生命に働きかけて回復や治療をする性質のものが多い。 そして、魔法を使う者――魔道師が魔法を使う前にまず必要になるのが〈魔法珠〉だ。 これは傍目にはただの石なのだが、いわば魔法を使う前の契約書のようなものだ。 〈黒の珠〉と〈白の珠〉があり、それぞれ〈黒魔法〉と〈白魔法〉に対応している。 魔法を使う者は、 〈黒魔法〉ならまず「自然界の精霊に働きかける方法」を、 〈白魔法〉なら「生命力を『織り上げる』方法」を理解しなければならない。 その上で、少なくとも一度は〈魔法珠〉を手にして『魔法の源』を手に入れる。 精霊や生命力が特定の配列で流れ込んでくるのを、自分の心身に取り込むのだ。 しかも、面倒なことに、珠は使い切りで、 精霊や生命力の気配が密なところでないと手に入らない。 だからこそ、珠を仕入れてきては売る「魔法屋」が成り立つのだけども。 「魔法堂から、手に入ったって連絡が来たのよ」 「やっと貰えるんだよ」 ポポとアリスは、感無量といった様子だった。 「とりあえず、面倒なことは分かった」 ムーンはさっぱり分かっていないものの、大まじめに頷いた。 腰の小袋から、透明なガラス瓶を取り出してポポに放り投げる。 「わっ」 ポポは慌てて受け取った。瓶を取り落としそうになりつつも、懸命に堪えた。 「とりあえず持っとけ。お前なら使い方、分かるだろ?」 「え」 「あんた、こんな高価なものを!」 アリスが怒る。 ガラスは、滅多にお目にかかれない貴重品だ。 そして、瓶の中に入っている物を見れば、祖父の書斎に保管されていた魔法の品だと分かる。 「…っていうか危ないわよ!何が入ってるか分かってんの?」 「分からない。ポポ、お前に任せた」 「また、そんな…」 勝手な。しかし、キャンディが同意した。 「そうだな。さっきみたいにゴブリンに囲まれたら、守りきれるかわからない。 いざとなったら、それを使うんだ」 こんな非常事態だ。ポポは「わかった」と頷くしかなかった。 ああ、早く帰りたい。本当は日が暮れる前に帰りたい。 早く、安全で明るいところに出たい── 願いの半分は、間もなく叶った。 進んでいくうちに、ごつごつした天然洞窟が人工のそれへと変わったのだ。 比較的平らになった通路には、見覚えがあった。 瓦礫に半ば埋もれた上り階段を見つけたのは、それから少ししてからのことだった。 少しでも上へ、少しでも明るい方へ。無意識に光を求めて、四人は…迷わず登る。 すると今度は、頑丈そうな石の大扉が待ちかまえている。 何故かそれだけ、欠けることも、歪むこともなく。 「あった」 「あった…!」 明るいと思ったのは、扉の白色だった。 隙間から、気のせいかもしれないが、光が漏れている気がする。 ムーンは手でその表面を辿った。 複雑な紋様と、吹きつける風に祈りを捧げる人のレリーフが刻まれている。 ふと気づくと、扉の向こうから冷たい空気がやってきて、ふわりと頬を撫でる。 「冷たい」 今は春先、夕刻に外で風に吹かれた日は寒くて心細いと思うこともあったが、今日は励まされた。 ──風は止んでいない。まだ大丈夫なんだという気がした。 ムーンが止める間もなく進み出た。喜び勇んで…ふと我に返り 「いいよな?」と問う眼差しを向ける。 四人揃って頷き合うと、ムーンは扉を押した。 扉は、ご、ごぉん…と音を立て、重々しく開いた。 まるで勿体ぶっているような開き方だ。 『儀式や祭典の時を除いて、長老あるいは風の守人の許可なくば、決して通ってはならぬ』 いつもそう注意を受けていた大切な扉を、とうとう少年少女は通り抜けた。 ぱあっ、と目の前が開け、眩しい光が一斉に飛び込んできて、弾けた。 「う、わあ…!」 四人の誰もが言葉を失い、ただただ唖然と立ち尽くした。 そこは透明な空間だった。 限りなく澄んだ、清い空間だった。 目に飛び込んでくる光景はあまりに透き通って汚れなく、その場に居る人間が 思わず気後れしてしまうほどに。 記憶にある風の祭壇は、はたしてこれほどだったろうか。 壁を規則的に飾るのは風を象徴した壁画だ。そのいずれも白を基調に彫られている。 『風』の恵みと生命のすばらしさを謳い、長い長い時を在り続けてきたのだ。 床と柱は総大理石、台座も装飾を施されたそれ。 側面にはさり気ない意匠と共に翡翠が飾られている。 そして、台座の中心で淡い輝きを放っている石こそは。 「…風の、クリスタル…!」 キャンディが言葉を紡いだ。…畏怖と歓喜のあまり喉に絡まった声で。 四人の表情が、みるみる喜びに溢れていく。 「…凄い……凄い、すごい、すごーいっ!」 「やったあーっ!!」 手を取り合い、ぴょんぴょん飛び跳ねて喜ぶポポとアリス。 「よっしゃあ!」ムーンは拳を固め、大股で部屋中央の祭壇へ向かっていくのだった。 「俺が一番乗りィ!」 「あっ、ずるーい!」 慌てて祭壇に殺到しようとした弟、妹たちを、 「待て!」 キャンディの鋭い声が制した。 「…感じないか?誰か…何か、そこに居る」 と。クリスタルが放っていたように見えた紫色の光が、信じられない速さでムーンを掠めた。 「うおっ!?」 間一髪、飛び退いた彼だったが、瞬間。怖気が身体を走った。 紫色の光の正体は、発光する霧のようなもの。 クリスタルを取りまいていたそれが、ぎゅわ、ぎゅわ、とひとつに固まり、 徐々に何かの姿を取りはじめる。 「何だこりゃ?……亀か!」 「亀には違いないけど、これじゃお化けガメだよっ」 それを聞き、目の前のものを見ながら、アリスは知らず知らず青ざめていた。 「私、聞いたことがあるわ。昔、ここにクリスタルの力を借りて封印した魔物のこと」 「ランドタートルか」 「やっぱり魔物なの!?もうイヤだって言ったのにーっ」 話す間にも、巨大亀の輪郭がはっきりと現れる。頭が、尾が…そして甲羅が、手足が。 人間の六、七倍はあろうかという怪物。 見るのも恐ろしかったが、釘で打たれたように四人はその場を動くことが出来ず、一時も 目を離せなかった。 巨大な亀の皮膚は岩石と同じ土色だ。 甲羅は紫水晶の紫…だがそれは、宝石に例えるにはあまりにも生々しい。 おぞましいまでに、ぬらぬらと光っているのだ。 前後の脚には叩かれただけでも痛そうなのに、これまた鋭い爪がくっついている。 立ちすくむ四人の前で、怪物は目覚めの喜びにか、大きく一声吼えた。 部屋全体が震えあがる。それはまた、この場の子供たちの気持ちを、ご丁寧にも代弁していた。 大きく開いた怪物の口の中は、熟れすぎた苺の赤に似ていた。 鮮やかすぎる、人間の血の色──四人は、ぞっとした。 「こんなの聞いてねえぞ!」 「…おかあさん……っ!」 「……っ」 「嫌よ、『美人薄命』なんて。まだ十年ちょっとしか生きてないのに!」 言ったところで、もう逃げ場はない。何とか覚悟を決めて、武器を手にした。 怪物の、巨体である割にとても小さな二つの目。それが、 久方ぶりの獲物の到来を歓迎して、にやりと笑ったように見えた。 「来るぞ!」 だあん! 間髪入れず、前足が振り下ろされる。 ムーンは慌てて後ろに飛び退いたが、たった今まで自分が立っていた床は、 ひびが入ってあっという間に砕けてしまった。何という破壊力だろう! 「いくら一対四でも、こりゃ反則じゃねーの?」 冷や汗を垂らしながら言う。怪物が聞いてくれるはずもないが。 前足の第二打をぎりぎりでかわしながら、ムーンはなるべく動きやすい場所を探した。 怪物が自分以外に興味を持たぬよう、奴の目を睨んだまま、わざと他の三人とは反対方向に走る。 「勝手に突っ込むと危ないわよ!」アリスが叫んだ。「もう!」 標的から逸れたキャンディは、土色の皮膚を懸命に攻撃した。 だが、思っていたより怪物の皮膚は分厚くて、掠り傷程度しか付けることが出来ない。 それでも近づき、斬りつけては離れ。何度も攻撃を繰り返す。 ランドタートルに全く堪えた様子はなく、ふいに――長剣でちくちくと刺した箇所が 痒かったのか、奴は鬱陶しそうに尻尾を一振りした。 不意を突かれてあまりに巨大なそれを避けきれず、キャンディが跳ね飛ばされる。 「うわあ!!」 「きゃあっ!」アリスが巻き添えをくって悲鳴を上げる。 「ああ…」 これ以上留まっていても危険だというのに、ポポはそこを動けない。 目の前の怪物を見たくもないのに、視線が強い磁石にでも引っ張られるように、 逐一その動きを追ってしまう。 (どうしよう、どうしよう…どうしたら?) ポポは、目の前の怪物ではなく、己の恐怖と戦っていた。 頭の中は真っ白になり、焦るばかりで物が考えられない。後ずさりした足がまたしても震え始め、 緊張で汗ばんだ手は、いつの間にか道具の入った小袋を強く強く、祈るように握りしめている。 …と。 震えていたポポの手に、小袋の感触が伝わった。こつ、と何か、固いものの入った感触。 「…魔法?」彼は弾かれたように顔を上げ、「そうだ!」大急ぎで袋の中を探った。 取り出したのは、ムーンがくれたガラス瓶だ。 瓶から青白い輝きを放つ結晶を転がして出し、手に取る。 『南極の風』――中級の冷気魔法を閉じこめた品だ。 ちくちくと手を刺す鋭い角のある結晶だったが、 ポポはそれが痛いのも忘れて壊れんばかりに握りしめ、やはり震える唇を必死で宥め、 何事か呟き始めた。 「『…汝、万物を凍結する精霊よ。我が声を聞き届けたまえ…』」 ちかちかと結晶から、光が零れる。もし、夜空の星を手に取ることができたらこんな風だろうか。 ――これこそ魔法が凝縮されている証なのだ。 「『清き吐息よ、冷たき掌よ、魂を永遠に留め置く鎖となれ』」 意を決してすっくと足を踏ん張って立ち、両手を真っ直ぐに上げる。――瞬間、 零れていた輝きが失せた。 が、その直後。 びゅうっっ!! 耳をつんざく鋭い音を発して、冷気が吹き荒れた。 それは空気中に含まれたわずかな水分さえ源にして、雪を作り、氷塊を作り、吹雪を起こす! 冷気に包み込まれたランドタートルは、一瞬だけ冷凍状態になった。 魔法の発現を見届けたポポが、後ろに一歩よろめく。 結晶はまだ手の中に残っていたが、その輝きは少し鈍くなっていた。 これを投げつければ効果はもっと強かったはずだが、そうすると手元にも残らず、 一回きりの攻撃手段になってしまう。 だからポポは、これを魔法珠と杖の代わりにして、自身の黒魔法を土壇場で試したのだった。 「あっ」アリスが指さした。「何だか動きが鈍くなったみたいよ!」 「…そうか、亀だから寒さに弱いんだ」 「所詮は亀ってわけだな!」 「…や、やったの?」 「いや、まだだ…動いてる!」 ──亀の生命力を舐めてはいけない。 ランドタートルは甲羅に暫く閉じこもっていたものの、反撃を再開した。 やはり先程の冷気のせいか、動きが鈍い。 これに手応えを感じた四人は、ばらばらに散って敵を翻弄する作戦に出た。 亀はといえば、この元気のいい獲物に思ったより手を焼いた。 寒くて上手く動けないのに加えて、獲物がちょこまか四方八方逃げまどうものだから、 結局なかなか食事にありつけない。どうしていいかわからなくなって、やみくもに暴れ回るばかり。 「ほら、どうした!そんなんじゃ捕まらないぜ」 亀は重くなった瞼を持ち上げると、目の前でひらひらしている一匹に狙いを絞る。 こうなれば丸飲みにしようと、大きな口を直接持っていった。 「危ない!」 「「ムーン!!」」 気がつけば彼の背後は壁、逃げ場はなかった。もう駄目だ! 兄妹は悲鳴を上げ、目を瞑った。……だが。 「うぉっとっと、…ふう。へへん、どんなもんだいっ!」 彼は、大亀の背でばっちり決めのポーズを取ってみせていた。 ご馳走を食べるべく降りてきた怪物の頭を踏み台にして、すかさず飛び乗ったのだ。 思わずあとの三人から、安堵の溜め息が漏れる。 「このムーン様をエサにしようなんざ、百億年早えんだよッ──うわっと!」 悔しがって頭を振り、手足をばたばたさせる怪物。獲物も必死にしがみつく。 何せ亀は手も足も短いので、こうなってしまうともう、どうしようもなかった。だが、戦闘は続行だ。 「ひゃああ!」 振り下ろされる爪を避けて、ポポは右に左に走り回る。 「魔物め、お前の相手はこっちだ!」 キャンディは果敢に敵の懐に飛び込んで剣を振るうが、息があがっていく。 「くっそーっ」 ムーンはランドタートルの背に懸命にしがみつきながら、歯を食いしばった。 「弱点は分かったのに──うわああっこら、暴れるな馬鹿!」 「もうっ」 ひらりとのたうつ尾を避けて、アリスは独りごちた。 「これじゃ、らちが明かないじゃないの!」 怪物の後ろに回り込んだはいいが、それからどうしたものか。 キャンディの長剣がなかなか通らないところを見ると、護身用に持ってきたナイフは 役に立たないだろう。きっと突き立てた途端ぽっきり折れてしまう。かといって、 このまま見ているだけというわけにもいかないし…それも悔しい。 見れば、キャンディは汗だくで肩で息をしているし、ポポは祖父の秘蔵道具を使ったものの、 自分の力量よりずっと上の魔法を唱えて疲れているようだ。 怪物の上にしがみついているムーンも、いつ振り落とされるかと思うと気が気じゃない。 「このままじゃ、みんなやられちゃう…。ああもう!どうしたらいいのよっ!」 吐き出すようにして、彼女は自問した。しかし、答えが見つかるはずもない。 焦りと苛立ちが募っていく。それから、恐怖も。 「………っ」 彼女は我知らず震えた。 忍び寄る冷たい予感。もし、みんなやられてしまったら。いっそ、その方がいいかもしれない。 だって、誰か一人でも居なくなってしまったら…! 弱気になった彼女に、心の中でもう一人の彼女自身が言う。 あの怪物を何とかして倒して、みんなでここを出よう、と。 でも…でも、どうやって? (祈りなさい) 「えっ?」 突然降って湧いた答えに、彼女は目を丸くした。 …いや、違う。今のは自分で思ったことじゃない。何か…誰か、別の声。 「だっ、誰?誰なの?」 (……。…こ…) 今度こそ声が聞こえたような気がして、アリスは慌てて辺りを見回した。 人影はなく、返事も聞こえない。空耳だろうか?けれど確かに…。 (……巫女…) 「!」 今度はもっと、はっきりと聞こえた。確かに、『巫女』と。 「誰よ?隠れてないで出てきなさい!」 …しかし、気配はない。 「聞こえてるんでしょ?遊んでる場合じゃ、ないの!」 振り向くと、そこには光を放つ宝石があった。 透明な結晶の中に温かな光が宿り、ちらちらと瞬いている。 壁画の中を彩る翡翠の緑は、クリスタルの光そのものだったのだ。 風が纏う森の木々と草花の匂い、その生命の証を示す輝き。 「クリスタル?」 信じがたいが、確かな予感。ここに居るのは、自分とクリスタルだけだ。 今話ができるとしたら、他に誰が居るというのだ! しかし村で声を聞けるのは、今は三人だけだ。風の守人と、 二人の長老── 自分たちを育ててくれたトパパと、いつも見守ってくれているホマクだけ…。 「うああっ…!」 叫び声を聞いて振り向いた視線の先、 キャンディが鋭い爪のある前肢にひっぱたかれ、今度は壁際まで吹っ飛ばされていた。 見事な壁画を縁取る凹凸が、皮肉なことに衝撃を増す手段となった。 「…おねがい、助けて」 いよいよ駄目かもしれない。アリスは縋る思いで言った。 祭壇上の水晶柱を見上げ、畏れ多くも自身の手で触れる。 まぐれでいい。構わない、たった一度だけでいいから。 「みんなを助けて!!」 きらっ、と一筋(ひとすじ)、緑の星屑が零れたように思った。 (『風の巫女』……) 声が聞こえた。 今度こそ本当に、間違いようがない。 直接はっきりと、頭の中に響いてきたのだから。 「……」 アリスには、それがこの上なく力強く温かいものに思えた。 緑の光が、ぼやけた視界に眩しく映る。 (祈りなさい。祈りは私の力となる。清き祈りは光となり、広がりゆく。 巫女、その心を私と共に。私に祈りを…──光を!) 「……っ分かったわ、祈ればいいのね!」 彼女は、知らぬうちに頬に零した涙を袖でぐいっと拭うと、 傍にあった儀式用の魔法陣に飛び込んだ。クリスタルに言われた通り、一心に念じる。 と── その唇から、不可思議な呟きが漏れた。 「『…光よ…命よ……今ここに、我を通じ力を示したまえ。その力をもって、魔を封じたまえ!』」 零れる光の粒子が、クリスタルとアリスを包み、広がっていく。 「くっ…」 ムーンの指に力がこもる。指が、爪が、甲羅に食い込んだ。もう限界だ。 巨大亀の背は思ったよりも安定感が悪い。 おまけに奴は激しく暴れるので、これ以上身動きが取れないのだった。 頼みの綱とみえた祖父の道具は、ポポが使ってくれてこそ有効だ。それなのにあいつときたら、 一回コッキリ呪文を唱えただけで、歯が立たないと見るや逃げてばかり。あれではアテにできない。 結局思いつくことはといえば、あの太い首を切り落とすことだけ、 だがそもそも、それが可能なのかどうか。 キャンディが必死に立ち回っているが、気を抜いた途端やられてしまいそうだ。 せめてポポがもう一回やる気を出してくれたら。 そして自分が、こいつの動きを少しでも止められれば…! そう思った時、何度目かに立ち上がったキャンディが、疲労のあまりとうとう足下をふらつかせる。 「キャンディ!」 「来るな!」 思わず駆け寄ったポポの行動が、魔物に絶好の機会を与えてしまった。 あんぐりと大きく開けた顎がそこにある。 「…っこの野郎!」 ムーンは決死の覚悟で飛び出し、首の皮をナイフで貫こうとした。 無情にも乾いた音がして、小さな刃はあっけなく弾き返される。 「!」彼は勢い余って、ランドタートルの背からもんどり落ちた。「っ…やべえ」 体勢を立て直そうとしたところで、物凄い重圧がそれを阻んだ。 二度、三度と床に叩きつけられる。 腕を動かそうとしたが、衣服の袖が爪で床に留められてしまっている。 片腕に至っては肩から二の腕に掛けて巨大な爪が食い込み、血を流しはじめていた。 足を使って蹴り上げようにも激痛が走り、動けない。 (もう、だめなのか?こんなところで死ぬのか?) 怪物の頭は目前だった。ランドタートルの巨大な口が迫る──! 「うわあああ!!」 ──『止まれ!』 突然、圧倒的な迫力をもって響き渡った声。 怪物も少年たちも、びくりと動きを止めた。 声は、耳を通してでなく、頭に直接届くのだった。 『生命の環(わ)から外れし者よ…戻れ、在るべき流れの中へ…!』 「!」 「アリス?」 「………」 それは、聞き慣れた妹の声でありながら、同時にもっと別の── 逆らうことなど思いも寄らぬ声だった。 『私の光は、お前の命。巡りゆき、また在るべき処へ還ろう』 温かく爽やかな緑の光が漂ってきて、ぱあっと拡散する。 光の粒子は薄いカーテンのように広がって膜を作り、 ランドタートルの巨大な全身をすっぽりと包み込んだ。 ――今だ! 少年三人の呼吸が、ぴたりと重なった。 「「「やあああっ!!」」」 ポポが投げつけた結晶が、きしゃあん、と音高く砕けた。 解放される、冷気の嵐。瞬間的に凍りついた皮膚を、大小二つの刃が突き通す。 凍った怪物の首は、意外に容易(たやす)くそれを許した。 やがて、断末魔の咆哮の代わりに巨体の沈む音がした。 再び広間が揺れる。 次の瞬間、怪物の巨体は音もなくかき消えた…。
「や…った…」 「あ~…危なかった……」 「た、助かったあ……」 安堵のあまり溜め息をつき、力無くその場に座り込んだ三人。 「…治ってる」 ムーンは、傷が完治していることに気づいた。破れた袖はそのままだったが。 消えた傷をぽかんと眺めていた少年たちは、先刻の緑色の光に思い当たった。 「!」 殆ど同時に振り向いて、彼らは妹の姿を見つける。 彼女は神々しい光を放つ水晶柱の側で、途方に暮れていた。 …疲れを押して立ち上がり、駆けつける。 「アリス!」 「アリス、無事か!」 「…大丈夫?怪我ない?」 言われると、彼女ははっとした。たった今、夢から醒めた人のようだった。 「生きてるか?起きてるか?おーい」 「ムーンてば」 「アリス…大丈夫かい?」 アリスは笑顔を見せた。 まだ夢見がちな微笑みだったが、出てきた言葉はしっかりしていた。 「うん、私は平気。みんな無事?」 「うんっ」 「お陰さんで。さんきゅ」 「ありがとう、アリス」 「お礼なら、あたしじゃなくてクリスタルに言って。あたしは、お祈りしただけだもん」 「お祈り」 アリスは頷いた。そして三人を見回してから、改めて目の前の水晶柱を見上げた。 もうずっとそこへありながら、一点の曇りもない宝石を。 「…ねえ、クリスタル。貴方よね?あたしに話しかけたのは…」 (──そうだ) 万物の根元、世界の全てを支える尊い存在──に対し、アリスの言葉は礼儀を欠いたものに 違いなかったが、クリスタルはあくまで優しく答えるのだった。 これに驚いたのは少年達の方だ。 「お…おい、聞いたか?クリスタルが喋ったぜ!」 「う、うん…!今の、空耳じゃなかったよね?本物だよね?」 「信じられない…言葉を聞くことが出来るのは、クリスタルに選ばれた者だけだっていうのに」 (そうだ。お前たちは選ばれた…) クリスタルが言った。 四人は驚きのあまり、きょとんと目を見張り、続いて思わずクリスタルに詰め寄る。 「選ばれた…って何をすればいいの?」 「聖職に就けということですか?」 「そんなの、俺はごめんだぜ!じっちゃんや風守みたいに、一生、村で静かに暮らすなんて。 だいたい、急に話しかけてきて何だよ。やぶからぼうに!」 「ちょっと静かにしてよ!」 (私の中に残った最後の光を…最後の希望を受け取ってくれ。このままでは、この光も消えてしまう。 全てのバランスが崩れることになる…) 「…ひかり…?」 (光を受け取れば、大いなる力を取り出すことが出来よう。それは溢れる闇を打ち砕く力となる) 「闇を」 「打ち砕く…?」 (闇の氾濫を止めるのだ。この世界を消してしまってはならない……) きらきらと瞬いていた光がすうっと消えかけた…と思うと。 「…え?」 「な、何だよ、何なんだよ!?」 「うわーっ!!」 「きゃああ!!」 突然クリスタルが輝きを増し、四人は光に包まれた。 何が起こったのか、考える暇も貰えないまま…気がつくと四人は、白く輝く まばゆい空間に居るのだった。 きょろきょろと辺りを見回したが、あるのは溢れる光だけだ。 辛うじて上下左右の認識はできるものの、床も天井も消えて無くなっている。 だからだろうか、宙に浮いていると感じてしまうのは。──いや、違う。 四人は宙に浮いているのでもなく…そう、言うなれば 自分が空間そのものに融けてしまったのだと感じた。 クリスタルの――『風』の気配を、自分の内に感じることができる。 彼らは今や、完全に光と一体だった。 気づくと四人は『風の祭壇』を眼下に見下ろし…あっという間にそこを通り過ぎた。 四人は風そのものになっていたのだ。 山腹を吹き下ろし、谷を駆け抜け、見知った村を一瞬で見分した。 家の中の蝋燭の火を揺らし――森の木立を揺らして、洞穴を抜け笛さながらの音を立て、 丘で砂を吹き散らした。熱を纏って勢いをつけた風は、また空へと駆け上がる。 鳥と一緒に旅路を渡り、冷たい雲にぶつかると雷光が爆ぜた。驚く間もなく、今度は吹き下ろす。 川の勢いを後押しし、海の水をかき混ぜて泡となり…ようやく止まるか、と思いきや また押し上げられ、景色が変わる。 そこは行ったこともない山だった。四人は――風は、可憐な花に口づけして通り過ぎる。 緑の草地と雪を頂く山頂が、とても美しいと思った。 緩やかになった風は、こんもりと降り積もった腐葉土をほんの少し巻き上げるに止まり、 そこに埋もれた。底の土は、びくともしなかった。 ふと、土の中から徐々に灰色のものが湧き出してくる。…霧か、煙か。 薄墨色のそれは黒へと変じ広がって、次第に色濃く辺りを覆った。四人には、美しい景色が 闇(と皆には認識できるもの)に、じわり、じわりと染まってゆくのが見えた。 そして、とうとうその場に収まりきらなくなった闇が、まるでコップから水が溢れ出るように ──世界中へ、流れ出していく。 流れ出した『闇』は、周囲の『光』を侵食するかに見えて音もなく『光』との衝突を繰り返した。 気がつけばもう、そこには何もない。 『闇』にすっぽり覆われて、明るく美しい景色も、進む先も――全て見えない。 四人は突然、怖くなった。 止まってしまった…終わってしまった。『空っぽ』だ。 そう思った途端、『空っぽ』が大きな口を開けた。土の深淵に行き着くと、そこは闇。 逃れよう逃れようと必死にもがいて…しかし、 追いつかれる、と思った途端、本当にその通りになった。 『空っぽ』が迫ってくる。大きな大きな口を開けて、四人を呑み込もうとする…! (──っ) 叫びたくて──助けを求めて叫びたくて、けれど、声が出ない。 『空っぽ』の波に揉まれ、押し流されて、自分が『からっぽ』になる。消えてしまう! 必死に身を縮め、あるいは振り払おうとしても、意味を成さなかった。 もう、そこに自分が居るのかすら分からない。 自分が無くなる。自分が自分であることも、分からなくなる……。 (……!) もう駄目だと覚悟した瞬間、『光』が戻ってくる。あの優しい輝き。 四人は自分を取り戻す。この上ない安堵感を覚えながら。 風のクリスタルが言った。「旅立つのだ、光の戦士たちよ」と。 「どうして…」 やっと、声が出た。 (お前たちは、希望を持つ者として選ばれたのだ) 「希望?」 「何なんだよ、光の戦士って!」 クリスタルは、これには答えてくれなかった。 四人は、次の言葉を求めてクリスタルの声に耳を傾けた。 しかし、どうしたことだろう。声はとても小さく、弱くなっていく。 繋ぎ止めておこうとする四人の思いとは裏腹に。 (光の戦士たちよ、光と闇を分かつ者たちよ。この世界に再び希望を…) ……。
陽光と小鳥のさえずりに目覚めを告げられ、四人は起き上がった。 「…う……ん、…あ、あ~~…」 「ここは…?クリスタルは…?」 「…行ってしまった…いや。僕らが、ここへ出てきたのか…」 「……。…? ──見て!」 妹の声で、少年たちは我に返る。 「…ここ、村の裏側じゃない」 その通り、四人が目を覚ましたのは、彼らが住む風の村「ウル」の、 綺麗に刈り込まれた林の中だった。 向こうから穏やかな風に乗って、人々の喧噪が聞こえる。 見慣れた風景、生活感漂う場所。…四人は顔を見合わせた。 「帰ってきたんだ!」 ポポが嬉々として叫んだ。かたや、ムーンは欠伸を残す。 「それにしても、クリスタルも気が利かねーよなー… どーせ送り届けてくれるなら、家のベッドの中にしてくれりゃいいのに」 「馬鹿なこと言ってないの! 聞いたでしょう?あの、クリスタルの声」 「…俺たちのこと、『光の戦士』って言ってたな…」 「ああ。『闇が氾濫を起こす』と言っていたけど、まさかこの前の地震と関係あるんだろうか。 魔物たちのことも気になるし」 「夢じゃないよね」 「夢なもんか。俺たち、確かに祭壇へ行って、魔物と戦って、クリスタルに会ったろ?」 ムーンは一言ずつ強調して、大げさに手を振って見せた。 「うん…。痛っ、なにするのさムーン!」 「ほら見ろ」 弟の頬をつねっておいて、彼はさも当然のように頷く。 「痛いってことは、これは現実なんだよ」 「そりゃあ、『今はちゃんと、起きてる』もんっ」 ああでもないこうでもないと議論の末、四人は結局、祭壇での出来事を信じることにした。 四人が四人とも同じような夢を、しかも同時に見るなんて普通は無いと思ったし、 何よりも、あの恐ろしい体験やクリスタルの固い感触には、現実味がありすぎる。 今も、まざまざと思い出すことが出来たからだ。 加えて、破けた袖はそのまま。 更にポポが持っていた〈魔法〉の結晶は、しっかり消失していた。 ここまで揃えば、夢だと疑う方がおかしい。 「とにかく、長老たちに話を聞いてもらおう。何か、ご存知かもしれない」 「でぇーっ、わざわざ怒られにいくようなもんじゃん」 「仕方ないだろう?」 家に戻ろうと歩き始めたところで、慌てて走ってくる人影がある。 もちろん、よく見知った村人だ。 「お前たち?」 彼はあからさまに驚いた様子だった。 「今までどこに…まあ、いい。長老様がお呼びだ。急いで家へ戻りなさい。 ………。まさか、また何かしでかしたんじゃないだろうな?」 汚れた衣服や顔に目を留められ、破れた袖を怪訝そうにねめつけられたので、 四人は慌てて首を横に振った。滅相もない、と口を揃えて弁解する。 こっそり横目を使ってお互いを見やった四人には、いつになく深刻な表情が浮かんでいた。 何やら、ただならぬ事態らしい。 「心当たりは」と聞かれれば、そりゃあもちろん、ありすぎるくらいだった。
「帰って来たな」 四人の顔を見るや、ダーンは心得顔でそう言った。 「奥で長老が待っていますよ」 「ダーン様、風守様…」 応接間の手前に控えていたのは、長老たちの補佐役であるダーン、 それに風のクリスタルの側仕えである『風守』だ。 「え?もしかして…全部バレちゃってるわけ?あっちゃー…」 ムーンは後悔のあまり、額に手を当てた。 「やっぱ、ダーンの薬草棚ひっくり返すのは止めておいた方が良かったか」 「えぇ!?」 「それは知らんかった」鷹揚に頷くダーン。 「ばか…」 アリスがこれ見よがしにため息をつく。 風守は、ははは、と声を立てて笑った。実はね、と続ける。 「ダーンが、あなたたちに起こったことを感じ取ったんです。また夢を見たと」 「わしの霊感は…自分で言うのも何だが、強くてな。肝心なところは察したと思うとるよ」 「でも、薬草棚は見抜けなかったんだから。少しは整頓してください」 「私、お手伝いしましょうか?」とアリス。 「うん?うん…」 ダーンは曖昧な返事をした。 「まあ、さておき」彼はコホンと咳をひとつして、居住まいを正す。そして、静かに扉を開けた。 「さあ、長老の言葉を聞きなさい」 促され応接間に勢いよく飛び込むと、そこには既に村の長老トパパとホマク──それに 四人の義母親ニーナが待っていた。 「じっちゃん!」 「騒がしいぞ、ムーン」 トパパは孫を、軽くたしなめる。 「早急にお話があると聞き、戻って参りました」 キャンディは公式の場での『長老』に対する態度で、祖父との対話に臨んだ。 彼がそっと前へ出たのを見て、ポポとアリスも倣う。 四人が横一列に並ぶと、トパパは孫たちの顔を見渡し、静かに訊ねた。 「何故呼んだか、分かるな」 「はい。ええと…あの…たぶんそうだと思います」と、ポポ。 「よろしい。お前たちの身に何が起こったかは、ダーンが話してくれた。 大まかにだが分かっておるつもりだ」 トパパは言い、続いて厳かに告げた。 「──先程、『風』のクリスタルよりお告げがあった」 「!じゃあ、やっぱり……!」 どよめく四兄妹。 ここでついに、ポポが約束事を破ったことを黙っていられなくなる。 「あの…ごめんなさい、僕たち」 そんな彼の言葉を引き取ったのは、もう一人の長老ホマクだった。 「無断で北の祭壇跡へ行ったことか?その奥で、風のクリスタルを見てきたと」 訳知り顔で頷き、ぱちりと片目を瞑る。やっぱり全てお見通しだった。 ポポがびっくりして目を丸くすると、彼はからからと笑った。 「困ったことよ」 「……」 「しかし今回ばかりは叱れんな、トパパ。 子供たちの好奇心だけがこの事態を招いたのなら、何とでも言えようが… 『風』が絡んでおるもの、のう?」 「全くだ」 トパパは溜め息をひとつつくと、再び厳粛に言った。 「クリスタルが自ら、お前たちを『呼んだ』のだからな」 「じっちゃん!俺たち…」 「わかっておる。まさかお前たちが選ばれるとは考えもしなかった…」 そして、トパパは順繰りに四人の顔を見渡した。名を呼んで。 「ムーン、ポポ、キャンディ、アリス。これは偶然の選択ではないことを、まず知らなければならない。 クリスタルは、その意志でお前たちを選んだのだ」 思い当たるふしが多すぎて、四人は驚くばかりだ。それでも 我が身に起こったことは、全員が正確に把握していた。…様々な感情と共に。 やがて、トパパが訓示を終えると、四人は洞窟での出来事を我先にと話した。 こんな状況でさえなかったら、日常の中の小さな冒険で片付いたろう。 その後、祖父からこってりお叱りがあり、日常が戻ってくる。 だが、今回は違った。 「祭壇には、封印されたという魔物が居ました。昔語りで聞いた姿そのままに」 二人の長老は合点がいって頷いた。 「クリスタルの――『光』の力が弱まった証拠だろうな。 だからこそ、『光』はお前たちを手元へ引き寄せた」 「クリスタルの本質は『光』じゃ。 それが弱まったということは、対極にある『闇』が強まったことを意味する」 「そういや、クリスタルは俺たちのこと、『光の戦士』って呼んだんだ」 と、ムーン。 「クリスタルは僕らに言いました。『闇の氾濫をくい止めろ』と。 それは、世界に何か──」 キャンディは言い淀んだ。そして何とか先を続けた…ように、ポポとアリスには見えた。 「…何か、悪いことが起こる。いえ、既に起こっている……そう考えるべきでしょうか」 「おいおい!縁起でもねえな」 「お前だって言ったじゃないか。心当たりがあるだろう?」 キャンディは険しい表情で言う。そのまま、長老たちの方を見て話した。 「最近、世界中で異変が起きていると聞きます。 長老が、外と連絡を取っているのはそのせいでしょう? 村のみんな、普通を装ってるけど、本当は不安なんだ。…違いますか?」 「………」 「魔物は、地震の後から人里に現れはじめた。 …祭壇の洞窟で、僕らは小鬼にも会いました。 あの山には以前、魔物なんか決して棲んでいなかったのに」 あとの三人が頷く。 「これも…関係が、あるのでしょうか」 彼の言葉の締めくくりは、絞り出したような声になった。 世界の危機、クリスタルの啓示…肯定して欲しくはなかった。 何故ならそれは、自分たちがあまりにも重大な使命を背負ってしまったことを意味するから。 ──しかし、長老たちは言った。 「おそらくは、な。間違いなかろう。異変についても聞いての通り、この村の被害など小さいものだ。 全ての原因はあの地震、そして」トパパは子供たちを見やった。 「世界の命運を託すべく、クリスタルは戦士を選んだ」 「それが…僕たちだということですね?」 「さよう。…村を出なさい。世界を旅して異変の元を探り、それを断つのだ」 「それが、最終的には『闇』の力を封じることにもなるかの」 どことなく重い空気の中、相変わらずどこか、とぼけた口調のホマク。 「……。あのさぁ」 ムーンも口を開いた。全く緊張感の無い様子で。 「俺たち『光の戦士』にされちゃって…そんで、『今から世界を救いに行け~』って、俺 そう聞こえるんだけど、合ってる?」 まったく身も蓋もない言い方だが、要点は上手く捉えているらしい。 「平たく言えばそういうことになる」トパパはいささか苦い顔で頷いた。 母ニーナはといえば、先程から、ただ黙って話を聞いている。 何かを言いたそうに、だが何とも言えない顔をして、四人を見つめていた。 「その力を…お前たちの心に宿る『光』を無駄にしてはならない。――さあ、旅立つのだ」
「もっといい武器ないのかよ、師範!」 「馬鹿言え!これは我が家に伝わる由緒正しきヌンチャクだぞ! だいたい、その剣は何なんじゃ。両方持って魔物と戦うつもりか? そもそも格闘家が武器に頼ろうなんぞ、たるんどる!素手で充分じゃ素手で!」 「へーんだ、頑固ジジイ。俺は武器の扱いに関しちゃ天才的なんだぜ。素手でも充分強いけど、武器が あれば強さは倍になる!いい武器なら尚更だ。そこんとこ、解ってほしいよなあ……」 「たわけ!口ばっかり達者になりおってからに」 「痛ってぇ~~~!!」 大きな道場の分厚い扉を隔ててなお聞こえてくる怒鳴り声に、キャンディは苦笑した。 かれこれ一時間近くもあの調子だ。 これから魔物の出没する中を旅していこうというのだから、 保身のために武器は必要だけれども…選び始めたら、きりがなくなってしまったらしい。 思うに、使い慣れた物が一番だと思うのだけれども。 ムーンは、剣術を習う傍ら、老師に付いて格闘技も齧っていた。 もともと体を動かすのは好きで、何にしても「格好いいから」と形から入るタイプなのだが、 やってみると思いのほか筋がいい。 魔法理論はからっきしでも、身体能力は抜群なのだった。 ただ、あの通りの性格だから、老師と一緒に居るとなかなかに騒がしかったりする。 …いや、老師に限ったことでもないか。 家の裏手から帰宅し、台所を覗くと母親ニーナが居た。 「母さん」 「あらキャンディ、お帰り。あと少しで夕飯よ」 いい匂いのするシチューの鍋をかき混ぜていた母は、振り向き、微笑んだ。 「もうそんな時間か。手伝うよ」 「みんなは?」 「ムーンはまだ道場だよ。ポポとアリスは、おじいちゃんの所じゃないかな」 「準備は、もういいの?」 「うん、粗方(あらかた)。 必要なものは揃ったし、後はみんな…各自で持っていくものがあれば、それで終わり」 キャンディがテーブルを拭き棚から食器を出して並べていると、 ふと背中の向こうで、そっと母が溜め息をつくのが聞こえた。 「…何?」 「いえね、不思議だなあと思って」 母はしみじみと言った。何となく分かる気がした。 「僕たちのこと?」 「それもあるけど…いろいろよ。 巡り合わせって不思議ね。どこまでが必然で、どこまでが偶然なのか、判らない」 「…確かにね。時期が少しずつずれてるとはいえ、みなしごが四人も拾われるなんて、 ちょっと驚きだ。おじいちゃんは、ああ見えて、よっぽど子供が好きだったのかな」 冗談めかして言うと、母は目をぱちぱちさせた。 「あら。それは、あながち外れてないわ。あれで、おじいちゃんは貴方たちのこと、 可愛くて仕方ないのよ」 「でも母さんは、世話しなきゃいけない子供が増えて大変だったでしょう」 「そりゃあ、大変は大変だったけどね。後で振り返ると子育てって、やっぱり嬉しいものよ」 「……。ありがとう、母さん」 ぽつりと言うと、母は笑う。 「やあね、何改まってるの」 母の口調には、心なしか明るさが足りなかった。いつも笑顔で、そこに居る── 決して泣いたりしないひとだったけど。 「キャンディ」 「…ん?」 母の姿は、何だかとても小さく見えた。 彼女は息子を見上げ、その目を見て静かに言う。 「気をつけて、行ってらっしゃい。みんなをよろしくね」 安心させたくて咄嗟に出てきた言葉は、ひどく簡潔なものだった。 「うん…大丈夫だよ」
いつもと同じように過ごした翌日の早朝、村の出入口に旅装束で子供たちは立った。 村のことを考えた結果、子供たちはひっそりと村を出ることになった。 だから見送りも、母ニーナと祖父のトパパ、長老の補佐役ダーン、『風』の守人などに限られた。 村のみんなに話が伝えられるとしたら、四人が遠くに行った後だろう。 ムーンが「世界を救いに行く」なんて隣のおばちゃんに宣言したが、いつもがいつもなだけに、 冗談で片付けられた。 「何で信じないかなぁ」ムーンは不満そうだったが、これはこれで幸いした。 いざ見送りの時になると、ポポはみんなの顔を見回した。そして、母親に目を留める。 その顔を見てしまうと、我慢していたものが込み上げてきた。それを抑えようとして、必死で堪える。 …駄目だ、絶対。ここで泣いたりしたら、きっとまた心配をかける。 それに、きっと旅になんか行けなくなる。だから、精一杯の笑顔を作ろうとした。 「……。おかあさん…!」 「ポポ」 肩を震わせる息子を優しく抱きしめてやりながら、ニーナは言った。 「ほら、しっかり。男の子でしょ?」 「うん…うん……。行ってくる」 「行って参ります」 折り目正しく言ったのはキャンディ、長老トパパも頷く。 「うむ、しっかりな」 一方ムーンは、場の雰囲気が何だか重くて、あまりに落ち着かない。 それで、咄嗟に明るい声を出すのだった。 「じっちゃん、暗い!大丈夫だって。俺が居るんだぜ?」 「あんたが一番不安なのよ」アリスが言った。 くってかかろうとする兄を横目でちらりと見やり、いささか大げさに溜め息をつく。 「ご心配なく。『お兄ちゃんたち』は私が、ちゃあんと見てますから」 「あのなあっ」と怒るムーンの横で、 「信用無いなあ、僕ら」キャンディが笑った。 「うおーい」 長老ホマクは、いそいそとやってくると、手にしていた帽子をポポの頭に被せた。 ──鍔の広い、とんがり帽子だ。 「ホマクおじいちゃん、これ…」 「餞別じゃ、持ってけ」 ためらうポポを後目に、さらりと言う。 「昔っから、黒魔道師はこれと決まっておる」 「! ありがとう…」 「なあに、気負うことはない。物見遊山にでも行くつもりで、楽しんでこい。 何せ、世界中回るんじゃからの」 「まあ、ホマク様ったら」 ニーナが笑う。 「行ってらっしゃい。くれぐれも、病気や怪我には気をつけるのよ。お土産、楽しみにしてるわ?」 と、茶目っ気たっぷりに瞬き、こんな風に付け加えた。 「君たちの行く先に、良い風が吹かんことを。風はいつも君たちと共にある」 風の守人は、いつも旅人を送り出す時するのと同じように、言った。 まさか彼らを送り出すことになろうとは、これまで思ってもいなかったが。 子供たちは、揃って頷いた。 「行ってきます!」 「見とけよーっ!バッチリ世界を救ってやるからな!」 「みんな、元気でねえ!」 「またね、お母さん!おじいちゃまーっ!」 歩き出す四人の背中を、風が後押しした。 北から吹きつける風は、まだ少し冷たかったが、軟風。彼らを導くかのようだった。
|
|||||||||||||
 |
 第2巻:駆け抜けた異変へ |
 小説ページへ |
 サイトトップへ |