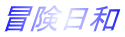
| 第6巻:三大魔道師 Fan Fiction novel written by HIJIRI. Fan art by Shoo. Do not reupload. Do not use for AI training. 無断使用禁止。SNSへの再投稿やAI学習禁止 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魔道師 | ||||||||
|
千年の昔に生きた古代人が、超技術の粋を集め空に至らしめた『浮遊大陸』―― その、更に東の海の向こうに、『風の秘境』と呼ばれる場所がある。 『風の秘境』――ダルグ大陸。 陸地面積の九割を急峻な山々が占めるここで、 唯一 奥深くへの上陸を許してくれそうなのが、南に突き出した『十字岬』だ。 しかし実際のところ、この岬から少しでも内側に足を踏み入れようとすると、強風が来訪者を拒む。 切り立った山脈から深い谷に向かって絶えず吹き下ろす風は狭まった谷底を北から南へ抜けるうちに勢いを増して、 世界でも他に類を見ないほどの暴風となって岬に到達するのである。 古代の遺産である飛空艇をもってしても、おいそれとは立ち入らせてくれぬ この場所を、いつしか人々は『秘境』と呼ぶようになった。 が、もしその奥地まで辿り着ける者が居たならば、きっと驚くことだろう。 樹木でさえも山肌にへばりつき真横に曲がって伸びるこの土地に、大きな館が建っているのだから。 館は、険しい谷の一番奥深く――何故かそこだけ周囲を森に護られ、ぽつんと建っていた。 …微動だにしない。 色褪せて見える白い外壁も黒い屋根も――派手さは皆無だが、不思議と 厳かな印象を受ける佇まいだ。 館に付随する三つの塔が、強風の中に在ってなお真っ直ぐ天を突く。 大きい二つの塔は館を門番のように挟んで建ち、残りの小さな一つは東の端で、油断なく辺りを見張っているようであった。 ごうごうと唸る風の中、森に隠れ物言わずに佇むその様は、さながら俗世を離れた隠者のよう。 そして――ここに住む者も、世間的に言えば隠者だった。住まいもまた、住まう人間に似てくるのかもしれない。 「ドーガ様」 館の主は書斎に居た。自分を呼んだ声にごく短く返事をして、再び窓の外に目をやる。 屋内に居るにもかかわらず目深に被ったフードの中から、鮮やかに青い瞳が覗いている。 生気に満ちて澄んだ瞳とは裏腹に、深く刻み込まれた目尻の皺は、彼自身が かなりの高齢であることを物語っている。 その顔には、年齢と共に幾多の経験を重ねてきた人間ならではの落ち着きと、独特の翳りがあった。 目を伏せると皺が一層目立ち、どこか苦いものでも噛みしめているような表情になる。 木枠の付いた硝子窓はカタカタ鳴るだけで、いつもと特に変わらなかった。 「ドーガ様」 書斎からなかなか出てこない主にしびれを切らしたのか、彼の『使い魔』が再び呼ばわった。 ――そう。彼は人間に違いないが――その中でも『魔道師』と呼ばれる類の人間なのだった。 朱で染められたローブは、彼が最高位の魔道師である証。 手元に引き寄せた杖は単なる歩行補助具ではなく、魔法を使うための道具だ。 魔道師ドーガは、席を立った。『使い魔』が呼ぶ理由が分かったからだ。――侵入者だ。 (ザンデ、か…?) この大陸特有の風の守りを突き抜け、防衛のため空に放っている『翼ある者たち』 (これも、彼に従う『使い魔』だ)の包囲網をかいくぐってやってきた、何者か。 もしザンデの手の者ならば、黙って見過ごすわけにはゆくまい。 (今度こそ…) 今度こそ。ドーガは杖を手に、大きく腕を広げて声を発した。 ――「誰じゃ! ここを魔道師ドーガの館と知ってのことか!」 警戒感を露わにしたその声が、魔法でもって館の玄関まで届く。 朗々と響き渡り、今やすっかり戦慣れした『光の四戦士』すら怯ませるに足りた。 「……!?」 『光の四戦士』の一人――ムーンは、鍵が開いているからと安易に この館に足を踏み入れたことを、たちまち後悔した。 彼の三人の仲間であり、兄妹――弟のポポも、兄のキャンディも、そして妹アリスも、驚いて我を忘れている。 そうとも。ここに住んでいるのは、ただの人じゃない。 ありとあらゆる魔法に精通し、何者をも超越した存在になり得たために、 今や『超魔道師』とさえ呼ばれている、あのノアの弟子なのだ! ――「ものども!! かかれ!!」 「ニャー!!」 四人の前に現れたのは、猫のぬいぐるみを彷彿とさせる二足歩行の生き物だ。 全身をふわふわの真っ白な毛に覆われ、背中には濃いめのピンク色をした蝙蝠の翼を生やしている。 体の大きさは、人間の幼子くらい。――可愛らしくも、変な奴らだ。 この白いぬいぐるみめいた者たちは、あれよあれよとムーンたち四人を取り囲むと、黒くてまん丸な目で睨んできた。 ――これには『恐怖』というよりも『困惑』が先立つ四人だ。緊張に強ばっていた顔が、思わずぽかんとしてしまう。 そんな彼らが何か言うより先に、未だ姿を見せてくれぬ声の主が唸った。 「もしや、そなたたち…??」 変で可愛い蝙蝠猫は、揃って奥を振り返ると、サーッと引っ込んでいった。 入れ違いで四人組の前に出てきたのは、朱色のローブを纏った人物だ。 玄関奥の長い廊下は仄暗く、その人物も目深にフードを被っていたから、 遠目で見た最初は表情が分からない。 しかし、やがて相手が自分たちの目の前までやってくると、海のように青い瞳が確認できた。 皺の寄った顔に、白い眉毛と髭。 ムーンが想像していた通りの、いかにも「魔道師です」という風体の老爺だ。 猫背をしゃんと正したところで、ムーンよりは背が高いのだと分かる。 朱色のローブを着た老爺は、青い目を見張ると、二度「ムムッ」と唸った。 「そなたたち、『光の戦士』じゃな」と、こちらが名乗る前に言い当てる。 この人が先ほどの声の主――つまり、魔道師ドーガ本人なのだろう。 はい、と四人が頷くその前に、ドーガは勝手に納得した。 「そうか。クリスタルは人間に、その力を委ねたのじゃな…」 先ほどの張りつめた声の調子はどこへやら、あっさり警戒を解く。 「ならば、話さねばならぬことがある…」 そして、言うが早いか『奥へ入れ』と目と手で促して踵を返すのである。 ドーガの態度はもとより、話も急展開しすぎて呆気に取られっぱなしの四人だったが、 ムーンは我に返って朱色のローブの背中に言葉を投げた。 「俺たちも、あんたに訊きたいことがいっぱいあるんだ!」 大魔道師ドーガが立ち止まる。 「なあ! 俺たち、あっちこっち回り道して、やっとこさここまで来たんだぜ!? あんたなら何か知ってるんじゃないかって」 ポポも思いきって顔を上げ、言った。 「お願いです。どうか、本当の事を教えてください! 僕たち、たくさんの話をいっぺんに聞きすぎて混乱してるんです。 あの…っ!『闇の氾濫』って、結局何なんですか? そもそもの原因は…? 知りたいんです。何がどうして、こうなったのか。それに、今何が起こってるのか――起ころうとしてるのか」 キャンディとアリスが続く。 「正直、具体的なことが掴めないまま、僕たちはここまで旅を続けてきました。いや…大方の予想はついた。 けれど、ここから先は……是非とも貴方にお話を伺って、僕たちがどうすべきなのかをはっきりさせたい。お願いします!」 「あたしたちが『光』を受け取れば、クリスタルは大丈夫なんでしょうか? …でも、土のクリスタルは……。どうしたらいいの? 教えてください!」 ドーガは黙りっぱなしだ。四人は、つい焦って矢継ぎ早に言葉を重ねた。 何故かといえば――話は、少しばかり前に遡る。
――大国サロニアのゴタゴタを解決したムーンたち四人組は、王位継承したアルスの計らいで、 長いこと城に仕えているという二人の老魔道師に会った。 四人が一連の出来事を通して辿り着いた『超魔道師ノア』の名を口に出すと、彼らは言ったのだ。 「クリスタルに宿る『光』の減衰に、世界規模の大地震。魔物の出現と凶暴化…。 これだけの禍を引き起こす力を持っているのは、おそらくダルグ大陸の三人の魔道師だけじゃ」 「三人の…」 「魔道師?」 「今は『大魔道師』と呼ばれる、ノアの弟子たちじゃ」 「超魔道師と、大魔道師……!」 その存在に思いを馳せ、頬を上気させるポポである。 一方、ムーンは唸った。 「まあ順当だわな。『超魔道師』って呼ばれてる時点で、すげーのは何となく判るよ。 しっかし…そんな奴の弟子が、三人も居るのかよ」 世界的危機と自分たちの旅の根幹に、やっと近づけた気がする。 しかも――驚いたことに、サロニア城の老魔道師たちの話は、ここで終わらなかった。 ムーンたちの想像と期待を、易々と超えてきたのである。 「超魔道師ノアは息を引き取る前、ザンデ、ドーガ、ウネの三人に、その力を分け与えたという」 「「「!」」」 「ザンデだって!?」 その名前には聞き覚えがあった。 これまで四人の前に『敵』として立ち塞がった者たちの中に「ザンデの命令を受けて来た」と宣言する輩が居たからだ。 ――それに加えて、音に聞こえたノアの弟子の一人――『魔道師ドーガ』だと名乗った人物が――今、確かに目の前に居る。 「頼むよ!」 「ドーガ様。お願いします!」 「お願いします!」 「お願い!」 声を上げる四人とは対照的に、あくまで静かに視線を送って寄こしたドーガは、奥の部屋へと続く扉を開いた。
鼠穴の向こうには、摩訶不思議な空間が広がっていた。 じめじめした暗闇が支配しているその場所を、ドーガは少しも迷いなく進む。 ドーガが歩くと、道が現れる――四人は、はぐれないように付いていくので精一杯だ。 「この世界には、闇の世界に通ずる場所が幾つかあってな。ここも、その一つじゃ。 『光』と『闇』……二つの世界の間に、今は針の穴ほどの小さな異次元空間を作り、一時的に両方を繋いでおる」 「魔法で、そんなことができるんですか」 キャンディが感嘆した。いくら『魔法は万能ではない』と聞かされていても、 ドーガほどの大魔道師ともなれば話は別――殆全知全能のようにさえ思えてくる。 ドーガがこうなのだから、ドーガに魔力を与えたという師匠のノアも、さぞ凄かったに違いない。 何せ、竜王バハムートに認められたくらいだ。 一方、ムーンたち四人は、クリスタルの力を借りて幻術師になっても、 せいぜい『冥界の精霊』を二体ずつしか召喚できない。…ポポは溜め息をついた。 「僕の〈ヒートラ〉の珠(たま)も、貸してあげられれば良かったのにね……。 ひとり一体じゃなくて、全員で四精霊に会いにいけば良かったのかなぁ」 「でも、それじゃ時間が足りなかったじゃない。手分けして正解よ」 「だよねぇ…急いでたもんね」 四人が、ここに来るまでに習得した〈召喚魔法〉。 練習用の〈エスケプ〉は既に全員使えるようになっていたが、 それより上位の〈魔法〉は、四人等しく同じものを使えるようになったわけではなかった。 限られた時間で、手分けして『冥界の精霊』に会いに行ったために。 今使える〈召喚魔法〉は、 ムーンが、女王シヴァの持つ氷の力を発現させる〈アイスン〉 ポポが、炎の精霊イフリートを呼び出す〈ヒートラ〉 キャンディが、大地の巨人タイタンの力を借りる〈ハイパ〉 そしてアリスが、雷神ラムウに助力を得る〈スパルク〉である。 〈召喚魔法〉の修得を志す者は、まず最初に『冥界の精霊』と接触する。 次に、彼ら『冥界の精霊』の望む『対価』を差し出して認めてもらう。 そうやって契約して初めて幻術師となり、〈召喚魔法〉が使えるようになるわけである。 …更に、初回の召喚に限り、契約の履行を願う長い呪文を唱える必要があった。 「一体ずつでも契約できたんだから、良しとしましょうよ。それより、問題は効果の方じゃない? 〈白召喚〉と〈黒召喚〉」 今度はアリスが溜め息をついた。 「出てくる効果が極端すぎるのよね。それに、いざ使ってみるまで〈白〉〈黒〉どっちに転ぶか予測ができないんだもの…。 あれじゃ毎回、大博打だわ」 「仕方ないよ、僕たち半人前だもん」 「…いや。半人前だろーが一人前だろーが、そもそも『幻術師』ってそういうもんらしいぜ」と、ムーンが 二人の会話に割り込む。 「強い精霊を呼ぶんなら、『魔界幻士』を目指して〈合体召喚〉ってのを出来るようになれって話じゃん」 「…待ってよ。じゃあ、一人前になっても『幻術師』は『幻術師』じゃない」 どこか落胆の色が濃いアリスに対し、 「あ…そっか」ポポは一人納得する。「じゃあ、強い『幻術師』って、実は博打の天才なのかもね」 他の三人が、きょとんとした。 「なんで?」 「〈黒召喚〉と〈白召喚〉を、出したいタイミングで狙って引き当てるとか…出来たら凄くない? ――そういうのが、強い『幻術師』」 何気なく耳を傾けていたキャンディが、笑って同意した。 「違いない」 「それは確かに『凄い人』みたいに聞こえるわね。でも、きっと結婚相手には不向きだわ」 唐突な話題の跳び具合が、実にアリスらしい。…ポポが言う。 「そう? もしそういう人と結婚したら、アリスも一緒に幸せになれちゃうかもしれないよ?」 「『悪運持ち』の場合もあるじゃない。…ううん、ギャンブラーって時点で、対象外ね。 あたしは堅実な結婚がしたいの」 「堅実さは大事だ」と、笑いながらも生真面目に頷くキャンディ。 「まだまだ先の話だろ。まずは相手が現れるか、心配しとけよ」と、ムーン。 「なんですって?」 「おっと」さっと頭を下げてアリスの攻撃をかわしたムーンは、相も変わらず寡黙な魔道師に尋ねた。 この人は四人の会話を聞いているのか、いないのか。 「ところで、ドーガ。魔法陣ってのは、まだまだ奥の方にあるのか?」 四人は暢気な会話をしてはいたが、一方でモーグリたちの言った通り 魔物がウジャウジャ出てきて、その度(たび)に撃退していた。 「さっきから魔物だらけじゃん。ここがもう『闇の世界』か?」 「いや。ここはまだ『光』の領域――儂らの属する、こちら側の世界じゃ。 …しかし、ここに魔物が現れるのは『闇』が力を増している証拠」 ドーガは言葉を途切れさせて、はっと顔を上げる。そのドーガを守るべく、四戦士は動いた。 「〈エアロガ〉!!」 「〈ファイガ〉!!」 アリスとポポの連携攻撃が、敵であるメイジフライヤーの魔法を凌駕する。 「出来たわ! 〈白魔法〉!」 「これが高程六の……? 凄い威力だ。ドーガ様、ありがとうございます!」 元通りに〈魔法〉を使えるようになった二人が喜びと驚きを露わにすると、ドーガもまた微かに笑うのだった。 「さっき伝授した魔法、上手く使いこなせているようだな」 「「はいっ!」」 …と、ドーガの背中に斬りつけようとした黒騎士の剣を、 「〈ハイパ〉!!」 キャンディの召喚した『大地の巨人』タイタンが、素手で受け止める。 続けてタイタンの振るった拳は、ズドンと音を立ててめり込んだ。 「…っ」ムーンはその場から飛び退いた。「また敵かよ…!」 味方の形勢不利を感じ取って、やっと〈召喚魔法〉を使ってみる気になる。 同時に『冥界の精霊』と契約を交わした時のことを思い出したら、要らぬ疲れまで蘇ってきて、げんなりした。 (あいつが出てくるんだよなぁ…) 幻術師たちが暮らすレプリトの里では、 〈召喚魔法〉の珠を手に入れることこそ容易かったが、それ以降がまた大変だった。 余所者である自分たちが本格的な〈召喚魔法〉を使えるようになるには、里の中にある『幻生塚』に 行って『冥界の精霊』と対面し、まず自己紹介をしなくてはいけなかったからだ。 そうして顔を覚えてもらい、その上で『対価』を差し出して―― 即ち、彼ら『冥界の精霊』が望む贈り物をして、仲良くなる必要があった。 言葉としては分かるが、これがまた一筋縄ではいかなかった。 何しろ、対面した『冥界の精霊』は曲者で、召喚の契約を成立させるために渡す『対価』も、 非常に漠然としていたのである。 例えば、ムーンが対面した『氷の女王』シヴァは、こんな具合だった。 ――『この世に存在する「美しいもの」を持ってまいれ』 ――美しいもの。なんとも個人の主観に頼った、曖昧な『対価』だ。 ムーンは咄嗟に河原で拾った小石を取り出したけれども、女王はお気に召さなかったと見えた。 そこで今度は目の前に生えていた可憐な野の花を示したが、これも 「おぬし、今わらわのことを面倒な奴じゃと思ったな?」と言い当てられた。 『対価』としては当然、不合格である。 困り果てて頭を掻きむしったムーンに、シヴァは言った。 ムーンが身につけ、襟の中にそっと隠していた首飾りを、目ざとく示して。 ――『その、クリスタルのかけらをおくれ。それならば申し分ない』 ムーンは驚き、慌てて断った。これは大事なもので、渡すわけにいかないと。 するとシヴァは、おぬしの目玉でも良いぞ、などという。 ――『やれるわけがねーだろ!』 こんな問答だけを延々と繰り返して、結局ムーンがよく分からないうちに、シヴァは勝手に納得した。 ――『まあ、良いじゃろう。特別大サービスじゃ。 おぬしの、実に人間らしいその心根に免じて、力を貸してやろうではないか』 (「人間らしい」って何だよ。わっかんねーよなぁ…) ムーンだけでなく、他の三人も苦労したようだ。 …後で話を聞いたところによると、ポポは炎と熱気を纏うイフリート相手に必死で言葉を重ね、 「どうか力を貸してください」と頭を下げたらしい。 アワアワしながら話しているうちに「合格」を言い渡されたそうだ。 「よくわかんないけど、仲良くなれたみたいだ」とは、本人の言(げん)である。 (そもそも、なんで認めてくれたんだろ) 『冥界の精霊』が望む『対価』を示せたかどうかも、今ひとつ釈然としないが―― 契約成立したのだから、こちらを気に入ってくれたことだけは確かか。 「んじゃ、やるだけやってみっか!」 ムーンは苦手意識をひとまず心の片隅に置き、独りごちる。 そうして彼は、契約だけはしたものの一度も召喚したことのなかったシヴァに、初めて呼びかけたのだった。 「『冥界に在りし精霊よ、我が声に応えて来たれ』…えー…」 ムーンは脳をフル回転させた。 たどたどしく呪文を唱える彼の視線の先で、キャンディの―― 一度消えたタイタンが再び現れて、 文字通り敵を一蹴する。 一拍置いて、ポポの〈サンダガ〉が轟いた。 「続けなさい。――『我は汝に、汝は我に』」 思わず冷や汗をかいていたムーンに、ドーガが呪文の続きを教えてくれる。 励まされつつ、彼はドーガの言葉をそっくりそのまま繰り返した。 「『我は汝に、汝は我に』」 この洞窟は見た目通りではないのだろう。 それが証拠に、みんながどれだけ強力な〈魔法〉をぶっ放しても、岩が崩落してくることがない。 (思いっきりやっていいってことだよな) ムーンは声を大きくして、必死に呪文の詠唱を続けた。 やっと呪文の締めくくりまで近づくと、足下に光り輝く紋様が現れて、周囲の暗闇を照らし出す。 額から後頭部に掛けてが、電気を通してでもいるようにチリチリした。 内心おっかなびっくりしていたが、やがてムーンは満を持して叫んだ。 「出(い)でよ『氷の女王』シヴァ! エル・ディ〈アイスン〉!!」 ヒュ、と吹きつけたのは凍てつく風だった。 最初、風花(かざばな)が散る。それは儚く消えると思った。 ところが、風花は消えるどころか白い雪片となり、ムーンを取り巻いた。旋風に乗って冷たさを増す。 「……!」 やがて集まった無数の雪と氷の粒は、きらきら輝きながら――すらりとした、 人間の女性のような姿を取った。 無垢な雪そのものの白い肌に、時折ちらつく氷河の青。 薄衣を纏った美しいその姿には、きっぱりと見覚えがある――正真正銘、 以前に契約を交わした『冥界の精霊』だ。 『氷の女王』シヴァは宙を漂って、ほっそりした手指でムーンの顎を撫でる。 びっくりした彼をよそに、ふわりと方向転換した。 そして、最後に残った敵――乗り手を失い一直線に突っ込んでくる、通称「悪魔の馬」を一瞥する。 馬の瞳に宿る眠りの魔力よりも、シヴァの視線の方が強力だったらしい。 悪魔の馬は氷の彫像と化した。シヴァが消えると同時にピシリとヒビが入り、それは砕け散る。 思わず脱力して後ろにふらついたムーンの背を、ドーガが静かに支えた。 「よくやった」 「…。ど、どーも」 褒めてくれると思わなかったから、くすぐったかった。 「やったじゃないか!」 「い、今の、ムーンが召喚したの?」 「嘘みたい」 集まってくる兄妹。ムーンは疲れていたが、口先ばかりは威勢良く言った。 「俺だって、やりゃあ出来るんだよ! 見たか!!」
幻なのか、実在するのか。やがて現れた扉を、ドーガは開いた。 暗闇に沈む足下に、緑色の光の線で描かれた魔法陣が浮かび上がる。 「着いたか……」ドーガは、人ひとり立てば埋まる小さな魔法陣を見やった。 「早くしなければ…。儂(わし)の命も、もうそんなに長くはないようじゃ」 それを聞いて愕然(がくぜん)とするムーンたち『光の四戦士』に構わず、彼は言う。 「さあ、まずお前たちの乗ってきた飛空艇ノーチラスに魔法をかけ、海の底に行けるようにしよう…」 ――ゼハピド ムウー カイネ! 朗々と響くドーガの声は、四人が聞いたこともない呪文を唱える。 暗闇に、不思議な光が、ぴかぴかっと瞬いた。ドーガから魔力の波動が放たれたのだ。 彼は独り魔法陣の内側に足を踏み入れると、四戦士にこう指示した。 「サロニアの南…『二本角岬』の海底に眠る『時の神殿』に行くのじゃ……。 そこには、ノアのリュートがあるはず…」 「えっ」 「ちょっ…待てよ、ドーガ! 俺たちはここまでなのか!?」 「どういうつもりよ、ドーガ!」 「ノアのリュート?」 急に言い渡されて、騒ぎ出す四人。 ドーガは、キャンディの問いだけを的確に選び取って、答えた。 「『夢の世界』にも響き渡る魔法のリュートじゃ。それを使い、まずは『夢の世界』から ウネを連れてくるのだ。儂は今から、エウレカの鍵を取りに行く!」 「ま…待ってってば! ドーガ一人で!?」 慌てるアリスだ。 しかしドーガは、ここまで来れば後は大丈夫、ここからは手分けをした方が早い、などと断言する。 「お前たちはウネを起こし、巨大船インビンシブルを手に入れるのだ!」 巨大船? インビンシブル? ――一体、何のことだろう? 困惑したアリスだったが、咄嗟(とつさ)に手持ちの小袋をドーガに押しつける。 「なら、せめてこれを持っていって! あたしの作った丸薬です。 苦くないし、割と良く効くから。疲れたら一個、口に入れて!」 ドーガは、にこりと笑った。 「ありがとう」 「ドーガ様…」 心配そうに呼ばわるポポに、彼は頷いてみせる。 「案ずるな」 何の因果か、この少年の魔力の波長は師匠ノアとよく似ている――その彼を含む、 クリスタルが選び出したこの四人。まずはここから無事に送り出さねば。 「さあ行け! ノアのリュートで、ウネを起こすのじゃ!」 言うが早いか、四人に向けて放たれたドーガの転移呪文は完成した。 「また会おう! さらばじゃ!!」 びっくり顔の『光の四戦士』が、彼の目の前から消える。 それを見届けると、静まり返った闇の中で、ドーガはアリスに押しつけられた小袋の口を開けた。 真っ黒な丸薬を一つ摘まんで、匂いを嗅嗅ぎ――口に入れる。 「ほう」 悪くない。――ドーガは思った。 薬草茶と同じ香りがするが、こちらの方が甘くて美味い。そういえば、昔 ウネが作ってくれた丸薬も、飴玉のようで口にしやすかった。 ――『あんたの味覚は、子供みたいだからねぇ』 憮然としたドーガを笑う、ノアとウネ…そして、ザンデ。 だが、記憶の中にある彼らの懐かしい笑顔は、すぐに悲しみと怒りの表情に塗り替えられてしまう。 ――『お前に、儂の魔力をやる』 ――『あんまり、師匠からの贈り物に振り回されないようにね』 過去は変えられない。時は巻き戻せない。 ドーガほどの魔道師であっても、出来ぬことはある。 因果をねじ曲げる術を選べぬ以上、どうしようもない。 思い出す度に、ザンデのあの時の声が、表情が…強く強くドーガの胸を突く。 ――『人間の命なんぞ、要らなかった!』 「………」 思い出を振り切るように、ドーガは顔を上げる。静かに一歩、踏み出した。 彼が杖を一突きすると同時に、その長身が魔法陣の上から消えた。
|
||||||||
 |
 第5巻:天と礎へ |
 小説ページへ |
 サイトトップへ |